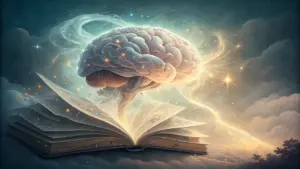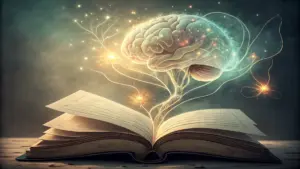仕事で疲れて、昔のように本が読めなくなったと感じるのは、あなたの意志が弱いからではありません。
この記事では、三宅香帆さんの著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』をわかりやすく要約し、多くの人が本から離れてしまう本当の理由と、読書のある生活を取り戻すための具体的な解決策を解説します。
本書が指摘するのは、個人の問題ではなく日本の「働き方」という根深い社会構造の問題なのです。
仕事でクタクタだと、本を読む気力なんて起きないよ…



その原因が、個人の意志の弱さではないとわかります
- 本が読めなくなるのは社会構造が原因であること
- 読書を妨げる「全身全霊で働く」といった3つの原因
- 読書を取り戻すための「半身で働く」などの解決策
あなたのせいではない、本が読めなくなった社会構造という本当の理由
「仕事で疲れて、昔のように本が読めなくなった」と感じるのは、あなたの意志が弱いからではありません。
その根本的な原因は、現代日本の「働き方」という社会構造そのものにあるのです。
本書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、この個人的な悩みを社会全体の問題として捉え直し、多くの人々が抱える息苦しさの正体を解き明かします。
この本を読むことで、自分を責める気持ちから解放され、問題の本当の姿が見えてくるでしょう。
読書から遠ざかるのは個人の意志の弱さではないという事実
「本を読む時間がないのは、自己管理ができていないせいだ」と思い込んでいませんか。
しかし、その罪悪感は不要です。
本書は、読書から遠ざかるのは個人の意志の弱さが原因ではないという事実を、明確な根拠とともに示してくれます。
実際にこの本は、発売からわずかな期間で発行部数20万部を突破し、「まさに自分のことだ」という共感の声が数多く寄せられています。
この反響の大きさこそが、多くの社会人が同じ悩みを抱えていることの証明です。
仕事で疲れて本を読む気力がないのは、自分がダメだからだと思ってた…



その罪悪感から解放してくれるのが、この本の大きな魅力です
問題はあなた個人にあるのではなく、心身の余裕を奪う社会の仕組みにあります。
本書は、その構造を理解するための第一歩となる一冊です。
問題の核心である日本の「働き方」
本書が指摘する問題の核心は、日本の労働史の中で形成されてきた特殊な「働き方」にあります。
それは、仕事に自分のすべてを捧げる「全身全霊で働く」という価値観です。
本書では明治時代から現代に至るまでの100年以上の歴史を辿り、いつから「仕事が自己実現の場」となり、プライベートを犠牲にすることが美徳とされるようになったのかを分析しています。
この「仕事がアイデンティティになる社会」では、読書のようなすぐに仕事の役に立たない活動は後回しにされがちです。
たしかに、趣味の時間でさえ「何か生産的なことをしないと」と考えてしまう…



その考え方こそが、私たちの心から余裕を奪っているのです
私たちの心身を疲弊させ、読書や趣味といった人生を豊かにする時間さえも奪っていく。
この根深い働き方の問題点を、本書は歴史的な視点から鋭くえぐり出します。
著者三宅香帆自身の経験から生まれた問題提起
本書の言葉がなぜこれほどまでに心に響くのか。
それは、著者である三宅香帆さん自身の痛切な経験から生まれた問題提起だからです。
文芸評論家として活躍する三宅さんも、会社員として働いていた時期に「本が全く読めなくなった」という経験をしています。
京都大学大学院で萬葉集を専門に研究していたほどの読書の専門家でさえ、過酷な労働環境の中では本を読む気力を失ってしまいました。
この原体験があるからこそ、本書の分析には机上の空論ではない、確かな説得力が宿っています。
本の専門家でも読めなくなるなんて、少し安心したかも



だからこそ、本書の分析は鋭く、悩める読者に寄り添う言葉は温かいのです
著者自身の苦しみから生まれた問いだからこそ、同じ悩みを抱える私たちの心に深く届き、自分だけではなかったのだという安堵感を与えてくれます。
書店員が選ぶノンフィクション大賞2024受賞という評価
本書は、読者からの共感だけでなく、本のプロフェッショナルからも客観的に高く評価されています。
その証拠に、全国の書店員が「いま一番読んでほしい本」を選ぶ「書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」を受賞しました。
発売から20万部を突破した売れ行きと合わせて、専門家と読者の両方から強い支持を得ていることがわかります。
この受賞は、本書が単なる個人の悩み相談ではなく、現代社会が向き合うべき重要なテーマを扱った一冊であることを示しています。
| 評価のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 受賞歴 | 書店員が選ぶノンフィクション大賞2024 |
| 発行部数 | 発売から20万部を突破 |
| 読者の反響 | 「私のことだ」「救われた」という共感の声が多数 |
これらの客観的な評価は、本書が現代を生きる多くの人にとって読む価値のある、重要な一冊であることを証明しています。
要約でわかる『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が示す3つの原因
本書が明らかにする「働いていると本が読めなくなる」原因は、決して個人の意志の弱さではありません。
その根底には、私たちの働き方や情報の受け取り方を規定する、大きな社会構造の変化があります。
本書が指摘する3つの原因を理解することで、なぜ自分が本から遠ざかってしまったのか、その本当の理由が見えてきます。
| 原因 | 概要 | キーワード |
|---|---|---|
| 原因1 | 効率を重視し、すぐに役立つ情報ばかりを求める社会の風潮 | 効率化、タイパ、自己啓発 |
| 原因2 | 仕事に全てを捧げることを良しとする、過剰な労働価値観 | 全身全霊、仕事がアイデンティティ |
| 原因3 | アルゴリズムが、未知の本と出会う機会を奪っている状況 | 偶然の出会い、ノイズ、フィルターバブル |
これらの原因は独立しているのではなく、互いに深く影響し合っています。
日々の仕事で効率を求められるうちに心身が疲弊し、限られた時間の中ではアルゴリズムが推薦する手軽な情報に頼ってしまう、という悪循環が生まれているのです。
原因1「すぐに役立つ情報」ばかりを求める社会の風潮
ここでいう「すぐに役立つ情報」とは、仕事の効率化や自己啓発に直結するような即効性のあるノウハウのことです。
現代社会では仕事の場面だけでなく、プライベートな時間でさえ、常に効率やタイムパフォーマンスが求められます。
三宅氏のインタビューによると、現代人は多忙であるため、すぐに役立つ「情報」を求める傾向が強くなっています。
その結果、結論に至るまでに時間がかかり、ときには寄り道を必要とする読書は「非効率」なものと見なされ、敬遠されがちになるのです。
【
確かに、仕事で調べ物をするときも、結論だけを早く知りたくなってしまいます…
〈
その感覚が、プライベートの読書にも影響を与えているのかもしれませんね
このような効率至上主義が、私たちの思考から「ノイズ」とも言える寄り道や、予期せぬ発見の機会を奪っていると本書は警鐘を鳴らします。
原因2「全身全霊で働く」価値観がもたらす心身の疲弊
本書が問題視する「全身全霊で働く」とは、仕事に自分の時間とエネルギーのすべてを捧げ、仕事を通じて自己実現を目指すべきだという価値観を指します。
この考え方が、私たちから読書に必要な心の余裕を奪っているのです。
本書は、日本の労働と読書の歴史を明治時代から丹念に辿り、2000年代には「仕事がアイデンティティになる社会」としてこの価値観が定着したと分析します。
仕事で疲れ果ててしまい、家に帰っても本を開く気力が残っていないという状況は、この働き方がもたらす必然的な結果なのです。
【
仕事でクタクタになって、家に帰ったら何もする気が起きないのは、まさにこれですね
〈
その疲れは、個人の体力だけの問題ではないと本書は教えてくれます
読書どころか趣味を楽しむ余裕さえ失わせるこの働き方こそが、多くの社会人が本から遠ざかる根本的な原因の一つだと本書は結論づけています。
原因3 インターネットが奪った本との「偶然の出会い」
かつて私たちは、目的もなく立ち寄った書店で、たまたま手に取った本に夢中になるという体験をしてきました。
本書は、このような予期せぬ本との「偶然の出会い」が、現代では失われつつあると指摘します。
その最大の要因はインターネットの普及です。
検索エンジンやSNS、通販サイトのアルゴリズムは、私たちの過去の閲覧履歴や購買履歴に基づいて、好みに合いそうな情報や商品を優先的に表示します。
三宅氏のインタビューによると、この仕組みによって意図しない情報や未知の作品に触れる機会が激減してしまいました。
【
そういえば、最近新しいジャンルの本って読んでいないかもしれません。
いつも同じような著者やテーマばかり選んでいます
〈
アルゴリズムは便利ですが、自分の興味の範囲を狭めてしまう側面もあるのです
自分の興味関心の範囲内で効率的に情報収集が完結してしまうため、かつて書店を散策する中で得られたような、世界を広げる読書体験が生まれにくくなっているのです。
「私のことだ」と共感を呼ぶ本書の感想・レビュー
本書が多くの読者の心を掴んだのは、その鋭い分析と共感性の高さにあります。
SNSやレビューサイトには「自分のことが書かれていると思った」という声が溢れています。
この見出しでは、実際に寄せられた様々な感想やレビューを紹介します。
共感の声だけでなく、異なる視点からの意見も見ることで、本書が投げかける問いの深さを感じられるはずです。
「疲れてスマホばかり見てしまう」への多くの共感の声
本書の帯に書かれた「疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ」という一文は、多くの読者の胸に突き刺さりました。
仕事で心身ともに疲れ果て、本を開く気力もなく、無意識にスマートフォンを手に取ってしまう…。
この現代人特有の姿を描き出したことで、多くの人が「これは自分の物語だ」と感じたのです。
まさに私のことだ…罪悪感があったけど、みんな同じだったんだ。



その罪悪感を和らげ、原因はあなただけではないと教えてくれるのが本書の魅力です。
本書の帯コピー「疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ」はまさに自分のことを言い当てられていてドキッとしました。
https://sunmarkweb.com/n/nb270294f925c
このように、個人的な悩みだと思っていたことが、実は社会全体が抱える問題であると気づかせてくれる点が、多くの共感を集める理由となっています。
読書は非効率という風潮への疑問を投げかける意見
現代社会では、何事においても「効率」が重視されます。
その風潮の中で、すぐに答えが出ない読書は「非効率なもの」と見なされがちです。
しかし、レビューの中には、その「非効率」の中にこそ価値があるのではないか、という意見が見られました。
すぐに役立つ情報は、すぐに役立たなくなるという本質を突いた指摘です。
ehirano1 763
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784087213126
社会では何かと「効率化」を求められがちなので、そりゃあなるはやで解が得られない(=むしろ問いが生まれる)読書は非効率に分類されてしまうのは自然なのかもしれません。しかしその「非効率」の中にこそ『成長』という得難いものがあるのではないと思ってます。だいたい、直ぐに役立つモノは直ぐに役に立たなくなるんじゃなかったっけ?
読書がもたらす問いや思考の深まりこそが、長期的な視点での人間的な成長につながるという考えは、本書のテーマと深く共鳴します。
資本主義社会の求める人間像と読書の関係性の指摘
本書は、読書という個人的な行為から、資本主義社会が個人に求める役割という大きなテーマにまで議論を広げます。
資本主義社会は、私たちを24時間働く労働者か、あるいは熱心な消費者であることを求めます。
その中で、別の生き方の可能性を示唆する教養や知識、つまり読書は「ノイズ」として扱われやすいという鋭い指摘があります。
塩崎ツトム 618
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784087213126
資本主義社会が人間に求めるものは「純粋」な存在であって、つまり24時間、勤め先の利益のために働く労働者であるか、24時間同じ娯楽にハマる消費者であるかのどちらかであり、「今の人生とは別の生き方があったかも」というものを見せる教養や知識、すなわち読書は「ノイズ」であり、社会に許容される読書とは、この純正であり続けるための読書「ひたすら効率よく行動し成長する」RTAのマニュアルみたいな自己啓発書だけらしい。基本ノイズばかりの脳味噌の持ち主で、そこから小説をひねり出す身としては困るのである。
このレビューは、本書が個人の悩みだけでなく、現代社会の構造的な問題にまで踏み込んでいることを示しています。
「読めなくなる」のではなく「読まなくなる」だけという批判的視点
本書は多くの共感を得る一方で、その問題設定自体に疑問を呈する批判的な意見も存在します。
「働いていると本が読めなくなる」のではなく、単に「読まなくなる」だけではないかという視点です。
これは、読書習慣の喪失を社会構造のせいにするのではなく、個人の選択の問題として捉える考え方と言えます。
trazom 562
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784087213126
著者の秘かなファンだっただけに、この本はガッカリ。「本を読む余裕がない社会」と言うが、本当か。明治から現代までの各年代毎に、労働と読書の変遷を整理しているが、読書の位置づけを、教養とか娯楽などと規定していることが悲しい。読書って、そんな即物的なものだったのか。文学を血沸き肉踊らせながら読み砕いてきた三宅さんが言うか…。私の経験からすれば「働いていると本が読めなくなる」なんて考えられない。「読めなくなる」のではなく「読まなくなる」だけではないのか。ならば、そもそも本書の問題設定が間違っているのではないか。
このように、様々な角度からの意見があること自体が、本書が多くの人にとって他人事ではないテーマを扱っている証拠です。
読書のある生活を取り戻すための3つの解決策
本書は、本が読めなくなる社会構造を分析するだけでなく、私たちが再び読書のある生活を取り戻すための具体的な解決策を提示している点が大きな魅力です。
それは個人の努力だけに頼るのではなく、働き方や読書に対する価値観そのものを見直すという、より本質的なアプローチを提案します。
解決策1 仕事にすべてを捧げる「全身全霊」という働き方からの脱却
本書が読書を妨げる根本原因として指摘するのが、仕事に身も心も捧げることをよしとする「全身全霊」という働き方です。
この価値観は、私たちのプライベートな時間を侵食し、趣味や休息に必要な心身のエネルギーを奪い去ります。
日本の労働史の中で、特に高度経済成長期以降に定着したこの働き方は、長時間労働を常態化させました。
その結果、仕事以外の活動は「息抜き」程度にしか捉えられなくなり、じっくりと向き合う時間が必要な読書は後回しにされてしまうのです。
仕事が最優先になるのは、仕方ないと思っていました…



その「当たり前」を疑うことが、豊かな生活を取り戻す第一歩になります
まずは、仕事が人生のすべてではないと認識し、意識的に仕事との間に距離を置くことが重要です。
全身全霊で働き続けることは、読書だけでなく、心の健康を損なう危険性もはらんでいます。
解決策2 仕事と私生活を両立する「半身で働く」という新提案
「全身全霊」という働き方から脱却するために、著者の三宅香帆さんが提案するのが「半身で働く」という新しい考え方です。
これは、仕事への責任や情熱を否定するものではなく、人生の半分は仕事に、もう半分は自分のための時間として大切にするというバランス感覚を指します。
「半身で働く」ことは、単に労働時間を減らすことだけを意味しません。
例えば、週に1日だけでも定時で帰る日を作り、書店に立ち寄る時間を作るといった小さな行動から始められます。
大切なのは、仕事以外の自分を育てるための「余白」を意識的に作ることです。
周りの目が気になって、なかなか早く帰れません…



あなたが「半身」で働くことが、社会の空気も変えていきます
最初は勇気がいるかもしれません。
しかし、あなたが「半身」で働くことで生まれた心の余裕は、新たな活力を生み出し、結果的に仕事の質を高めることにもつながります。
その余白こそが、再び本を手に取るためのエネルギー源となるのです。
解決策3 読書を人生の「ノイズ」ではなく豊かさと捉え直す視点
現代社会は効率を重視するあまり、仕事に直接役立たない知識や、すぐに結論が出ない思索の時間を「ノイズ(雑音)」と見なしがちです。
そして、体系的な知識の集合体である読書も、この「ノイズ」の一種として敬遠される傾向があります。
しかし、本書は、この「ノイズ」にこそ人生を豊かにする価値があると説きます。
すぐに役立つ情報だけを追い求めていては、予期せぬ発見や新しい視点を得る機会は失われます。
年間で数冊の本との出会いが、数年後の仕事のアイデアや人生の指針を与えてくれることは少なくありません。
読書を「情報を得るための手段」と限定せず、未知の世界に触れたり、自分の考えを深めたりするための豊かな時間と捉え直すことが大切です。
読書は非効率な「ノイズ」ではなく、あなたの人生に奥行きを与える、かけがえのない体験なのです。
書籍『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の基本情報
本書を手に取る前に、基本的な情報を知っておくことは大切です。
著者や出版社の情報、そしてどのような構成で話が進むのかを把握すると、より深く内容を理解できます。
ここでは、著者である三宅香帆さんのプロフィールや本書の概要、目次を紹介します。
著者三宅香帆のプロフィールと主な著作
本書の著者である三宅香帆(みやけ かほ)さんは、文芸評論家として活躍しています。
1994年生まれで、京都大学大学院で萬葉集を専門に研究していたという経歴の持ち主です。
本書以外にも、名作小説の解説書やオタク向けの文章術など、多彩なテーマで執筆活動を行っています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 香帆(みやけ かほ) |
| 生年月日 | 1994年 |
| 職業 | 文芸評論家 |
| 経歴 | 京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集) |
| 主な著作 | 『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』 『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない―自分の言葉でつくるオタク文章術―』 |
どんな人が書いている本なのか、気になっていました



ご自身の経験をもとに書かれているからこそ、言葉に説得力があります
読書への深い愛情と鋭い分析力が、本書の大きな魅力につながっています。
集英社新書からの発売日やページ数
本書は、集英社新書シリーズの一冊として刊行されました。
2024年4月に発売されて以来、大きな反響を呼び、発行部数は20万部を突破しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 出版社 | 集英社 |
| シリーズ名 | 集英社新書 |
| 発売日 | 2024年4月 |
| ページ数 | 288ページ |
| 価格 | 1,100円(税込) |
新書だから、手に取りやすい価格なのが嬉しいですね



コンパクトながら、内容はぎっしり詰まっています
新書サイズで持ち運びやすいため、通勤時間などの隙間時間にも読み進められる一冊です。
明治から現代までの労働と読書の歴史を辿る目次
本書は、なぜ現代人が本を読めなくなったのかを、日本の労働史を紐解くというユニークな視点から解き明かします。
序章から始まり、明治、大正、昭和、そして2000年代以降と、時代ごとの働き方と読書の関係性の変化を11の章で丁寧に追っていきます。
- まえがき 本が読めなかったから、会社をやめました
- 序章 労働と読書は両立しない?
- 第1章 労働を煽る自己啓発書の誕生―明治時代
- 第2章 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級―大正時代
- 第3章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?―昭和戦前・戦中
- 第4章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー―1950~60年代
- 第5章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン―1970年代
- 第6章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー―1980年代
- 第7章 行動と経済の時代への転換点―1990年代
- 第8章 仕事がアイデンティティになる社会―2000年代
- 第9章 読書は人生の「ノイズ」なのか?―2010年代
- 最終章 「全身全霊」をやめませんか
- あとがき 働きながら本を読むコツをお伝えします
目次を見るだけでも、個人の問題だと思っていた悩みが、実は長い歴史を持つ社会構造の問題であるとわかります。
よくある質問(FAQ)
- この本は、具体的な読書術や速読のコツを教えてくれる本ですか?
-
いいえ、この本は読書効率を上げるためのテクニック集ではありません。
なぜ社会人になると読書から遠ざかってしまうのか、その根本的な原因を日本の労働史から解き明かすノンフィクションです。
個人の努力で解決するのではなく、働き方という社会構造そのものに問題があると指摘しています。
ただし、あとがきでは著者の三宅香帆さんが実践している、働きながら本を読むコツも紹介されています。
- 「半身で働く」というのは、仕事を頑張らないということでしょうか?
-
仕事を頑張らない、ということとは少し違います。
「半身で働く」とは、仕事に自分のすべてを捧げる「全身全霊の働き方」を見直すための提案です。
人生の半分は仕事に、もう半分は趣味や休息といった自分のための時間にあてるという、新しいワークライフバランスの考え方を示します。
仕事以外の自分を大切にすることが、結果的に豊かな人生につながると本書は教えてくれます。
- 疲れてスマホばかり見てしまうのは、自分の意志が弱いからだと思っていました…。
-
そのようにご自身を責める必要は全くありません。
仕事で疲れ果てて、本を開く気力もなくスマートフォンを見てしまうのは、あなただけが抱える問題ではないのです。
本書には、同じような状況にある多くの読者から共感の声が寄せられています。
その原因が個人の意志の弱さではなく、心身の余裕を奪う社会構造にあることを理解するだけで、心が少し軽くなります。
- 自己啓発書を読むのに疲れてしまったのですが、この本も同じような内容ですか?
-
自己啓発書とは全く異なる一冊です。
多くの自己啓発書が「もっと頑張ろう」「効率を上げよう」と個人の努力を促すのに対し、本書は「頑張らなくていい」「問題はあなたではなく社会にある」という視点を提供します。
そのため、自己啓発に疲れを感じている人ほど、自分を肯定されているような気持ちになり、安心して読み進められます。
- 読書する余裕がないのは、やはり時間が足りないからではないのでしょうか?
-
社会人が読書から遠ざかる原因は、単に時間がないからだけではないと本書は分析しています。
より大きな問題は、仕事によって心身のエネルギーがすっかり奪われ、「本を読む 余裕がない」状態になっていることです。
本書で提案されている働き方の見直しを実践することで、心の余白が生まれ、自然と本を手に取る気力が湧いてくるはずです。
- 著者の三宅香帆さんは、なぜこの本を書こうと思ったのでしょうか?
-
著者である三宅香帆さん自身が、会社員時代に「大人になって本が読めなくなった」という辛い経験をしたことが、この本が生まれた大きなきっかけです。
文芸評論家という読書の専門家でさえも、過酷な労働環境の中では本が読めなくなるという実体験があったからこそ、本書の分析には強い説得力があります。
個人の悩みに寄り添いながら、社会構造の問題を鋭く指摘しています。
まとめ
この記事では、三宅香帆さんの著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を要約し、読書から遠ざかる本当の理由と解決策を解説しました。
本書が伝える最も重要なメッセージは、仕事で疲れて本が読めなくなるのは、あなたの意志が弱いからではなく、日本の「働き方」という社会構造に原因があるという事実です。
- 本が読めなくなるのは社会構造の問題
- 原因は仕事に全てを捧げる「全身全霊の働き方」
- 解決策は仕事と距離を置く「半身で働く」という考え方
- 人生を豊かにする「ノイズ」としての読書の価値
もしあなたが「疲れてスマホばかり見てしまう」自分に悩んでいるのなら、ぜひ本書を手に取ってみてください。
自分を責める気持ちから解放され、再び本と向き合うための最初の一歩になります。