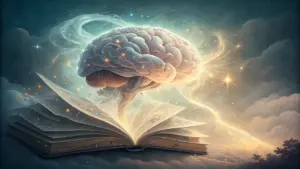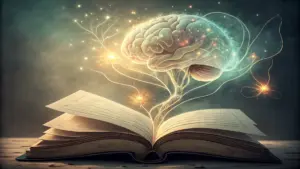会議や報告の場でうまく話せない原因は、話し方の技術ではなく、話す前の準備にあります。
コミュニケーションの成否は、話す前の「思考の質」で決まるのです。
この記事では、元コンサルタントの安達裕哉氏によるベストセラー書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』を要約し、その核心である「7つの黄金法則と5つの思考法」を誰にでも分かるように解説します。
会議で意見を求められると、頭が真っ白になってしまいます…



大丈夫です、話す前に少し考えるだけで誰でも論理的に話せるようになりますよ
- 『頭のいい人が話す前に考えていること』の要点
- 知性と信頼をもたらす7つの黄金法則
- 誰でも実践できる5つの思考法
- 学んだ内容を仕事で実践する具体的な方法
『頭のいい人が話す前に考えていること』の要点
この本が伝えるのは、単なる話し方のテクニックではありません。
コミュニケーションの質は話す前の「思考」で決まるという、根本的な事実です。
多くのビジネスパーソンが抱える「うまく伝えられない」という悩みの核心に迫ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 著者 | 安達 裕哉(元コンサルタント) |
| ポイント | 話し方以前の「思考のOS」を重視 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 提供形態 | 書籍、電子書籍、Audible |
これらの要素から、本書がなぜ多くの読者に支持されているのか、その理由が明らかになります。
著者・安達裕哉氏が伝える思考の本質
著者の安達裕哉氏は、コンサルティング会社や監査法人トーマツでの経験を持つ思考のプロフェッショナルです。
独立後に運営する個人ブログ「Books&Apps」は、累計1億2000万PVを達成しており、その鋭い洞察力が高く評価されています。
本書で語られる思考法は、著者がコンサルタントとして培った実践的な知見に基づいています。
コンサルタントの思考法って、難しそう…



大丈夫です、誰でも実践できるよう分かりやすく解説されていますよ。
著者の経験から生み出された思考法だからこそ、机上の空論ではなく、日々の仕事ですぐに使える内容になっているのです。
話し方の技術以前にあるべき思考のOS
本書が提唱するのは、話し方の技術という「アプリケーション」ではなく、その土台となる「思考のOS」をアップデートすることの重要性です。
多くの人が会話術やプレゼンの型を学ぼうとしますが、思考が整理されていなければ、どんな技術も効果を発揮しません。
本書では、まず自分の頭の中を整理し、考えを深めるプロセスに焦点を当てています。
| 本書の構成 | 主な内容 |
|---|---|
| 第1部 | 知性と信頼をもたらす7つの黄金法則 |
| 第2部 | 思考を深める5つの思考法(客観視、整理、傾聴、質問、言語化) |
この構成のように、思考のOSを整えることで、あらゆるコミュニケーションの場面で応用できる普遍的なスキルが身につきます。
ダイヤモンド社から出版のベストセラー
本書は、多くのビジネス書を手掛けるダイヤモンド社から2023年4月に出版されました。
発売からわずかな期間でベストセラーとなり、読書メーターでは5,800件以上の登録と1,300件を超える感想が集まるなど、幅広い層から注目されています。
みんなが読んでいるなら、やっぱり内容は良いのかな?



多くの人が同じ悩みを抱え、この本に解決策を見出している証拠ですね。
たくさんの読者からの支持が、本書の内容が現代のビジネスパーソンが抱える課題に的確に応えていることの証明です。
Audibleでの聴く読書も一つの選択肢
忙しくて本を読む時間がない方には、AmazonのサービスであるAudibleで「聴く読書」をするという方法もあります。
通勤中や家事をしながらでも、耳からインプットすることで効率的に本書の要点を学ぶことが可能です。
書籍版は330ページを超えるボリュームですが、音声なら隙間時間を有効活用できます。
| Audible版のメリット | 詳細 |
|---|---|
| 時間の有効活用 | 通勤や移動中に学習可能 |
| ながら聴き | 他の作業をしながらでもインプットできる |
| 内容の定着 | 繰り返し聴くことで記憶に残りやすい |
自分のライフスタイルに合わせて学習方法を選べる点も、本書が多くの人に受け入れられている理由の一つです。
知性と信頼をもたらす7つの黄金法則
本書の核心となるのが、コミュニケーションの土台を築く7つの黄金法則です。
これらは小手先のテクニックではなく、話す前の思考OSをアップデートするための原則といえます。
これらを意識するだけで、あなたの言葉は相手に深く届き、知性と信頼を同時に得られるようになります。
| 法則 | 内容の要約 |
|---|---|
| 法則1 | 感情に流されず事実と意見を区別 |
| 法則2 | 相手を打ち負かす論破の不毛さ |
| 法則3 | 人は自分と違う考えを持つという前提 |
| 法則4 | 相手が理解できる言葉での伝達 |
| 法則5 | 伝わらない原因は自分にあるという意識 |
| 法則6 | 相手の本当の目的や関心の探求 |
| 法則7 | 知識を知性に変える思考の深め方 |
7つの法則は、どれも特別な能力を必要とするものではありません。
日々のコミュニケーションの中で少し意識を向けるだけで、誰でも実践できるものばかりです。
法則1-感情に流されず事実と意見の区別
頭のいい人は、事実と、自分が感じた意見や感情を明確に分けて考えています。
この2つを混同すると、感情的な議論に陥り、建設的な対話ができなくなってしまいます。
例えば、「この資料は分かりにくい」というのは意見です。
一方、「この資料は専門用語が1ページに平均10個使われており、注釈がない」というのは誰が見ても変わらない事実です。
事実をベースに話すことで、冷静で論理的なコミュニケーションが可能になります。
会議で反論されると、ついカッとなってしまいます…



まずは事実だけを冷静に受け止める練習から始めましょう
感情的にならず、事実と意見を切り分ける習慣をつけることが、知的な対話への第一歩です。
法則2-相手を打ち負かす論破の不毛さ
コミュニケーションの目的は、相手を言い負かすことではなく、合意形成をして物事を前に進めることです。
議論で相手を論破しても、その場はスッキリするかもしれませんが、相手の恨みを買い、長期的な人間関係を損なうだけです。
議論に勝っても、その後のプロジェクトで相手の協力が得られなくなるケースは少なくありません。
それでは仕事という目的を達成することはできないのです。
本当に賢い人は、議論の勝ち負けにこだわりません。
相手の意見にも耳を傾け、お互いの妥協点を探りながら、より良い結論を導き出すことを目指します。
法則3-人は自分と違う考えを持つという前提
人はそれぞれ異なる経験や価値観、知識を持っています。
そのため、自分と他人の考え方が違うのは当然である、という前提に立つことが重要です。
この前提がないと、「なぜ分かってくれないんだ」と不要なストレスを感じたり、自分の意見を一方的に押し付けたりしてしまいます。
例えば、営業部門と開発部門で意見が食い違うのは、それぞれの立場から見える景色や優先順位が全く違うからです。
自分の意見が正しいはずなのに、なぜか反対されます



相手には相手の「正しさ」があるのかもしれませんよ
自分と相手は違うという前提に立ち、その違いの背景を理解しようとする姿勢が、円滑なコミュニケーションを築きます。
法則4-相手が理解できる言葉での伝達
どんなに素晴らしい考えを持っていても、それが相手に伝わらなければ存在しないのと同じです。
自分の言いたいことをそのまま話すのではなく、相手が理解できる言葉に「翻訳」する意識が求められます。
例えば、IT部門のあなたがマーケティング部門の担当者に話す場面を想像してください。
「この件はAPIを叩いてデータを取得します」と伝えるのではなく、「AのシステムとBのシステムを自動でつなぎ、必要な情報を取り出します」と説明するだけで、相手の理解度は全く変わります。
相手の知識レベルや立場、関心事を考慮し、言葉を選ぶことが賢い人の話し方の特徴です。
法則5-伝わらない原因は自分にあるという意識
話がうまく伝わらなかったとき、「相手の理解力がない」と他人のせいにするのは簡単です。
しかし、それでは何の進歩もありません。
賢い人は、伝わらない原因は自分の伝え方にあると考え、改善しようと努めます。
「なぜ伝わらなかったのだろう?」「どの言葉が分かりにくかったのか?」「説明の順序を変えた方が良かったか?」と自問自答することで、自分のコミュニケーションの課題が見えてきます。
この試行錯誤のプロセスが、あなたを伝え上手へと成長させてくれるのです。
何度も説明しているのに、分かってもらえないんです…



伝え方を一つ変えるだけで、相手の反応が変わることもあります
常に自分の伝え方を改善しようとする当事者意識を持つことが、信頼される話し手になるための鍵です。
法則6-相手の本当の目的や関心の探求
人は必ずしも、言葉にしていることが本心とは限りません。
相手の言葉の表面だけをなぞるのではなく、「なぜこの人はこう言うのだろう?」とその裏にある本当の目的や関心事を探る姿勢が重要になります。
上司から「この資料、もっと見やすくして」と指示されたとします。
このとき、言葉通りに色やフォントを修正するだけでは不十分です。
上司の本当の目的が「経営会議で、数字のインパクトを伝えやすくすること」だと探り当てれば、重要なデータをグラフ化したり、結論を最初に持ってきたりといった、より的確な対応ができます。
相手の隠れたニーズを汲み取ることで、期待を超える成果を出し、深い信頼を得られるようになります。
法則7-知識を知性に変える思考の深め方
多くの知識を持っているだけでは「物知り」なだけで、「頭がいい」とは言えません。
得た知識を自分なりに解釈し、応用し、行動に移すことではじめて「知性」に変わるのです。
例えば、この本を読んで「なるほど」と感じるだけでは、何も変わりません。
「法則1の事実と意見の区別を、明日の〇〇さんとの打ち合わせで実践してみよう」と具体的な行動目標に落とし込むことが大切です。
その経験を通じて、知識はあなた自身の生きたスキルへと変わります。
知識をインプットするだけでなく、常に「なぜ?」「だから何?」「どう使う?」と自問し、思考を深める習慣が、あなたを本質的に賢い人へと導きます。
賢い人になるための5つの思考法
本書の第2部では、知性と信頼を同時に手に入れるための具体的な思考法が5つ紹介されています。
これらは特別な才能ではなく、誰でも意識してトレーニングすることで身につけられる思考のスキルです。
このスキルを習得することで、コミュニケーションの質が向上します。
| 思考法 | 概要 | 目的 |
|---|---|---|
| 客観視 | 自分を第三者の視点から冷静に見つめる | 感情的な判断を避け、事実に基づいた行動を選択 |
| 整理 | 頭の中の情報を構造化し、話の骨組みを作る | 相手に分かりやすく、論理的に考えを伝える |
| 傾聴 | 相手の言葉の裏にある本音や背景を深く理解する | 信頼関係を築き、より有益な情報を引き出す |
| 質問 | 議論を深め、物事の本質に迫る問いかけをする | 相手に気づきを与え、建設的な対話を生み出す |
| 言語化 | 曖昧な思考を具体的な言葉にして明確にする | 自分の考えを客観的に捉え、説得力を高める |
これらの思考法を日々の仕事や人間関係で実践することで、あなたの印象は「頭のいい人」へと変わっていくのです。
思考法1-自分を冷静に見る客観視
「客観視」とは、自分自身の感情や状況を、まるで他人事のように第三者の視点から冷静に分析するスキルを指します。
感情に流されてしまうと、正しい判断ができなくなってしまいます。
腹が立ったときや焦ったときでも、一度立ち止まって「なぜ自分は今、このように感じているのだろう?」と自問自答することが大切です。
怒りの感情のピークは長くて6秒と言われており、この短い時間を乗り切れば、冷静な自分を取り戻せます。
つい感情的になって、後で後悔することがあります…



まずは事実と自分の感情を紙に書き出して、切り離す練習から始めましょう
自分を客観視する癖をつけることで、どんな場面でも落ち着いて対処できるようになり、周りからの信頼を得られるようになります。
思考法2-考えを構造化する整理
思考の「整理」とは、頭の中に散らばった情報を構造化し、話の骨組みを組み立てる作業のことです。
話が分かりにくい人は、この整理ができていないまま話し始めてしまいます。
本書では、コンサルタントが実践する思考の型として「結論→根拠→たとえば」の3点セットで話す方法が紹介されています。
最初に結論を伝えることで、相手は話のゴールを理解し、安心して聞くことができるのです。
話がまとまらず、いつも「何が言いたいの?」と言われてしまいます



話す前に、この3つのポイントだけをメモする癖をつけるのがおすすめです
この型を意識するだけで、あなたの話は驚くほど論理的で分かりやすくなります。
相手にストレスを与えることなく、短時間で正確に意図を伝えられるようになるでしょう。
思考法3-相手の本音を引き出す傾聴
「傾聴」とは、ただ相手の話を聞くのではなく、言葉の裏にある本当の目的や感情まで深く理解しようとする積極的な姿勢を意味します。
自分の意見を言う前に、まず相手を理解することが重要です。
賢い人は、自分が話す時間よりも相手が話す時間を大切にします。
理想的な会話の割合は、自分が話すのが2割、相手が話すのが8割です。
相手に関心を持ち、真摯に耳を傾けることで、初めて本音を引き出せます。
自分の意見を言うのに必死で、相手の話をあまり聞けていないかもしれません



相手の発言を繰り返す「バックトラッキング」を試すと、聞く姿勢が伝わりますよ
傾聴を実践すると、相手は「この人は自分のことを分かってくれる」と感じ、深い信頼関係が生まれます。
その結果、より有益な情報を得られるようになります。
思考法4-本質を突く的確な質問
賢い人が行う「質問」とは、単に情報を求めるものではありません。
議論を深め、相手に新たな気づきを与え、物事の本質に迫るための問いかけです。
良い質問をするための簡単な方法として、「なぜ?」を少なくとも5回繰り返して深掘りすることが挙げられます。
トヨタ自動車でも実践されているこの手法を使うことで、表面的な事象の奥にある根本原因を探り当てることができます。
会議で的外れな質問をして、場を白けさせてしまったことがあります



まずは「なぜそう思うのですか?」や「他にはどんな可能性がありますか?」といった開かれた質問を心がけましょう
的確な質問ができると、相手に「この人は深く考えている」という印象を与えられます。
質問力は、あなたの知性を示す強力なコミュニケーションツールになるのです。
思考法5-思考を明確にする言語化
「言語化」とは、頭の中にあるぼんやりとした思考や感情を、具体的な言葉にして明確な形に落とし込むスキルです。
考えているだけでは、思考は整理されません。
アウトプットすることで、思考は初めて明確になります。
例えば、自分の考えを毎日15分間、誰にも見せずにただ書き出すという習慣を持つだけでも、思考力は向上します。
書くことで、自分の考えを客観的に見つめ直せるようになります。
考えていることはあるのに、うまく言葉にできません



誰かに説明することを前提に文章を書いてみると、論理の穴が見つかりやすくなります
言語化のトレーニングを重ねることで、自分の考えに自信を持つことができます。
その自信が、コミュニケーションにおける説得力を生み出すのです。
学んだ思考法を仕事で実践する方法
本書で学んだ思考法は、知識として知っているだけでは意味がありません。
実際の仕事の場で意識的に使うことで、初めて自分のスキルになります。
特に、日々の何気ないコミュニケーションの場面で実践することが、あなたの評価を大きく変えるきっかけになるのです。
会議での発言、上司への報告、同僚との人間関係といった具体的なシーンで、7つの黄金法則や5つの思考法をどのように応用できるかを見ていきましょう。
これらの方法を試すことで、単に「話がうまい人」ではなく、「周りから信頼されるビジネスパーソン」へと成長できます。
会議で発言する前の思考整理術
会議での発言には、話す前に頭の中を構造化して整理することが不可欠です。
考えがまとまらないまま話し始めると、自分でも何を言いたいのか分からなくなってしまいます。
本書で紹介されている「整理」の思考法を使い、発言内容を組み立てる癖をつけましょう。
意見を求められたら、まず「①結論 → ②根拠 → ③提案」の順番で頭の中を整理します。
例えば、「私の結論はA案に賛成です。
なぜなら、先月の売上データを見ると、A案のターゲット層の購入率が前月比で15%上昇しているという事実があるからです。
つきましては、A案を軸に具体的な施策を検討することを提案します」のように、結論と根拠をセットで話すことを意識してください。
会議で急に話を振られると、頭が真っ白になってしまいます…



まずは「結論から話す」と決めておくだけで、驚くほど冷静になれますよ
この思考整理術を日頃からトレーニングすることで、どんな状況でも自信を持って論理的な意見を述べられるようになります。
上司への報告や説明での応用
上司への報告や説明の場面では、相手が知りたい情報を簡潔かつ正確に伝える「言語化」のスキルが求められます。
自分の頭の中にある情報を、相手が理解できる言葉に変換する作業が重要になるのです。
報告する前に、伝えたい内容を「客観視」して、事実と自分の意見や感情を切り分けてみましょう。
その上で、以下の表のように情報を整理すると、分かりやすさが格段に向上します。
特に、30秒で要点を伝えられるかを意識して準備するのがおすすめです。
| 項目 | 悪い報告の例 | 良い報告の例 |
|---|---|---|
| 冒頭 | プロジェクトの進捗が少し遅れていて… | Aプロジェクトの納期遅延に関するご報告 |
| 内容 | 色々あって大変で…(感情や経緯が中心) | 原因はB社の仕様変更。対策として人員を2名追加 |
| 結論 | なんとか頑張ります | 対策により、遅れは3営業日で解消できる見込み |
このように思考を整理し言語化する習慣をつけることで、上司は状況をすぐに把握でき、あなたへの信頼も高まります。
人間関係を良好にするコミュニケーションへの活用
職場の人間関係を円滑にする鍵は、相手の立場や考えを深く理解しようとする「傾聴」の姿勢です。
自分の意見を主張する前に、まず相手の話に真剣に耳を傾けることで、無用な対立を避けられます。
相手が話しているときは、途中で話を遮ったり、自分の意見をかぶせたりしないことが大切です。
相手が話し終えたら、「なぜそのように考えるのですか?」といった本質を探る「質問」を投げかけてみましょう。
この問いかけによって、相手の考えの背景にある目的や価値観を理解できます。
同僚と意見がぶつかると、つい感情的になってしまいます…



相手を打ち負かすのではなく、目的を共有する仲間だと考えてみましょう
傾聴と質問を実践することで、相手を尊重する姿勢が伝わり、建設的な意見交換が生まれます。
結果として、職場全体の協力体制が強固なものになります。
よくある質問(FAQ)
- この本で紹介されている思考法は、コンサルタントのような専門職でないと実践は難しいですか?
-
本書の著者、安達裕哉氏は元コンサルタントですが、紹介されている思考法は職種を問わず誰でも実践できる普遍的なものです。
専門的な知識は必要なく、日常生活や仕事のコミュニケーションで意識するだけで、人間関係を円滑にするヒントが得られます。
- すぐに使える話し方のテクニックだけを知りたいのですが、この本は合っていますか?
-
この本は、小手先のテクニックよりも、その土台となる思考法に重点を置いています。
なぜなら、頭の中が整理されていなければ、どんな話し方の技術も効果を発揮しないからです。
コミュニケーションの根本から改善し、本質的な信頼を得たい方に最適な一冊となります。
- 賢い人の特徴を真似すれば、すぐに仕事で成果を出せますか?
-
本書の教えを実践しても、すぐに魔法のように成果が出るわけではありません。
大切なのは、学んだ方法を意識し、日々の仕事の中で試し続けることです。
例えば、相手の話を最後まで聞く「傾聴」を心がけるだけでも、相手との信頼関係は少しずつ変わっていきます。
継続的な実践が、大きな成果につながるのです。
- この本でいう「知性」とは、単に知識が豊富なことですか?
-
本書における「知性」とは、単に物知りであることとは異なります。
持っている知識を、相手や状況に合わせて使いこなし、課題解決に結びつける実践的な力を指します。
事実と感情を分けて客観視したり、自分の考えを分かりやすく言語化したりするスキルこそが、本当の知性であると解説しています。
- 「7つの黄金法則」と「5つの思考法」の違いがよく分かりません。
-
「7つの黄金法則」は、コミュニケーションにおける基本的な心構えや、守るべき原則を示しています。
一方で、「5つの思考法」は、その黄金法則を実践するための、より具体的なスキルや道具だと考えてください。
法則という土台の上に、思考法という技術を積み上げていくイメージになります。
- 読書が苦手なのですが、Audibleで聴くだけでも本書の要点を理解できますか?
-
はい、十分に理解できます。
Audibleなら通勤中などの隙間時間を活用して、耳からインプットが可能です。
本書はコミュニケーションにおける「傾聴」の重要性も説いており、音声で集中して聴く体験は、内容の理解をさらに深める助けになるでしょう。
繰り返し聴くことで、大切なポイントが記憶に定着しやすくなります。
まとめ
この記事では、安達裕哉氏のベストセラー書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』の要点を解説しました。
コミュニケーションの成否は小手先の話し方ではなく、話す前の思考をどれだけ整理できているかで決まります。
- 知性と信頼をもたらす7つの黄金法則
- 誰でも実践できる5つの具体的な思考法
- 学んだことを日々の仕事に活かす方法
本書で紹介されている思考法は、特別な才能を必要としません。
まずは明日の会議で意見を言う際に、「結論から話す」ことだけでも意識して実践してみませんか。