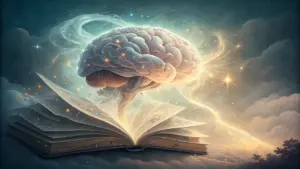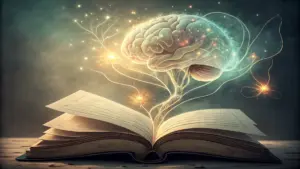特定の部下に業務が集中し、その人がいないと仕事が進まない状況に悩んでいませんか。
本書が提唱するのは、問題の原因を「人」の能力ではなく「仕組み」に見出し、ルールで解決する思考法です。
この記事では、安藤広大氏の著書『とにかく仕組み化』を要約し、3500社以上が導入するマネジメント法「識学」に基づいた、属人化を解消する具体的な方法を解説します。
ベテラン社員に頼りきりのチーム、どうすれば変えられるんだろう…



本書の思考法を実践すれば、誰が担当しても安定して成果を出せるチームを作れます
- 『とにかく仕組み化』が提唱する思考法の核心
- 属人化を解消する5つの具体的な思考法
- 本書がどのようなリーダーの悩みを解決するのか
属人化から脱却するための『とにかく仕組み化』という思考法
『とにかく仕組み化』の核心は、個人の能力や資質に頼る組織運営から脱却することです。
本書が提唱するのは、問題の原因を「人」ではなく「仕組み」に見出し、ルールによって解決するという思考法です。
この考え方を身につけることで、チームは安定して成果を出せるようになります。
この思考法は、組織運営における4つの重要な柱に基づいています。
これらを実践することで、属人化という根深い問題を解消し、チームを次のステージへと導くことが可能です。
個人の能力に依存しない組織運営
個人の能力に依存しない組織運営とは、特定のスタープレイヤーがいなくても業務が滞りなく進む状態を目指す考え方です。
カリスマ的なリーダーや優秀な個人の頑張りに頼る体制は、その人がいなくなると崩壊するもろさを抱えています。
本書は、属人化のリスクを指摘し、業務を標準化・マニュアル化することの重要性を説きます。
実際に、本書のマネジメント法「識学」は3500社以上に導入されており、その効果が証明されています。
でも、優秀な人のやる気を削いでしまわないか心配です…



役割と責任が明確になることで、むしろ全員が自分の仕事に集中しやすくなりますよ
仕組みを整えることは、個人の能力を否定するのではなく、むしろ誰もが安心して能力を発揮できる土台作りにつながるのです。
問題の原因を「人」ではなく「ルール」に求める姿勢
問題が発生した際、「なぜできないんだ」と個人を責めるのではなく、「なぜ問題が起きたのか」という視点でルールや仕組みそのものを見直すことが、『とにかく仕組み化』の基本姿勢です。
例えば、ミスが多発する場合、担当者の注意力を問う前に、「ミスの起きやすい手順になっていないか」「確認プロセスに不備はないか」を疑います。
本書では、このような5つの思考法(責任と権限、危機感、比較と平等、企業理念、進行感)を通じて、問題の根本原因にアプローチする方法が解説されています。
| アプローチ | 概要 |
|---|---|
| 人に求める | 個人の能力や意識、やる気に原因を帰属させる |
| ルールに求める | 問題が発生した背景にある仕組みや手順、環境に原因を探す |
この姿勢を貫くことで、チーム内に無用な対立が生まれず、建設的な問題解決ができるようになります。
誰が担当しても同じ成果を出せる再現性の実現
再現性とは、業務の手順や判断基準を明確にすることで、担当者が変わっても品質やスピードが維持される状態を指します。
ベテランの「勘」や「経験」といった曖昧なものに頼るのではなく、誰でも同じ結果を出せる仕組み作りが目標です。
本書では、マニュアル作成の重要性が強調されています。
単なる作業手順書ではなく、判断に迷ったときの基準やNG例まで言語化することで、新人でも入社初日から即戦力として動ける環境を整えることが可能です。
マニュアル作りって、なんだか面倒なイメージがあります…



一度作ってしまえば、教える手間が大幅に省け、長期的に見て生産性が向上します
再現性を高めることは、業務の属人化を防ぐだけでなく、新人の早期育成や組織全体の知識レベルの底上げにも直結します。
感情的な対立を避けるための客観的なマネジメント
『とにかく仕組み化』が目指すのは、上司の好き嫌いや気分といった主観を排除し、明確なルールに基づいた客観的なマネジメントです。
評価やフィードバックを感情ではなく「事実」ベースで行うことで、部下との健全な関係を築きます。
例えば、評価面談で「頑張りが足りない」と伝えるのではなく、「目標達成率が80%だった」「マニュアルの手順が守られていなかった」という事実を指摘します。
これにより、部下は感情的に反発するのではなく、改善すべき点を冷静に受け入れられるようになります。
| スタイル | 特徴 |
|---|---|
| 感情的なマネジメント | 上司の主観や気分で評価が変動し、部下が不公平感を感じやすい |
| 客観的なマネジメント | 設定されたルールや目標に基づいて評価が行われ、公平性と納得性が高い |
公平なルールのもとでの客観的なコミュニケーションは、部下の無用なストレスを減らし、組織への信頼感を高める効果があります。
著者・安藤広大とベストセラー『とにかく仕組み化』の概要
チームの成果が特定個人の能力に依存している状況は、多くのリーダーが抱える悩みです。
本書は、その属人化の問題を解決するために、3500社以上が導入するマネジメント法「識学」に基づいた思考法を解説しています。
まずは、この本の著者と概要について見ていきましょう。
株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏
本書の著者である安藤広大氏は、人と会社の成長を促すマネジメント理論「識学」を提唱する、株式会社識学の代表取締役社長です。
早稲田大学を卒業後、NTTドコモなどを経て、2015年に識学を設立しました。
識学は口コミで広がり、2023年5月時点で約3500社を超える企業に導入された実績を持ちます。
この事実は、安藤氏の提唱するマネジメント法が、業種や規模を問わず多くの組織で効果を発揮することを示しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 安藤 広大(あんどう こうだい) |
| 生年月日 | 1979年 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 最終学歴 | 早稲田大学 |
| 現職 | 株式会社識学 代表取締役社長 |
| 主な経歴 | NTTドコモなどを経て2015年に株式会社識学を設立 |
識学って、結局どういう考え方なの?



個人の頑張りや才能に頼るのではなく、ルールや仕組みで組織を動かすという思考法です。
安藤氏は一貫して、問題の原因を「人」ではなく「仕組み」に求める姿勢を貫いています。
そのブレない軸が、多くの経営者や管理職から厚い信頼を得ているのです。
ダイヤモンド社から出版された320ページのマネジメント指南書
『とにかく仕組み化』は、ビジネス書の出版で定評のあるダイヤモンド社から発行されています。
全320ページというボリュームで、仕組み化の思考法を基礎から応用まで深く学べる構成です。
発売されたのは2023年5月ですが、読書管理サービス「読書メーター」では既に2600人以上が登録しており、注目度の高さがうかがえます。
多くの読者が、組織の問題を解決するヒントを求めて手に取っているのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書名 | とにかく仕組み化 人の上に立ち続けるための思考法 |
| 著者 | 安藤広大 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 定価 | 1,870円(税込) |
| 発行年月 | 2023年5月 |
| ページ数 | 320ページ |
| ISBN | 9784478117743 |
本書は、単なるテクニック集ではありません。
リーダーが持つべき「思考のOS」をアップデートするための、実践的な指南書と言えます。
『リーダーの仮面』『数値化の鬼』に続くシリーズの集大成
本書は、ベストセラーとなった『リーダーの仮面』『数値化の鬼』に続く、安藤広大氏のマネジメント哲学の集大成と位置づけられています。
前2作で語られたリーダーの心構えや評価手法を、組織全体に落とし込むための方法論が展開されます。
これまでの作品で、安藤氏はリーダーが個人的な感情を排して役割に徹すること(リーダーの仮面)や、客観的な事実に基づいて評価すること(数値化の鬼)の重要性を説いてきました。
本書では、それらの考え方を組織の「ルール」として実装する方法を解説しています。
| 書籍名 | 主なテーマ |
|---|---|
| リーダーの仮面 | リーダーが取るべき役割と振る舞い |
| 数値化の鬼 | 結果を客観的に評価するための考え方 |
| とにかく仕組み化 | 組織全体で成果を出すためのルール作り |
もちろん、シリーズを読んだことがなくても内容は十分に理解できます。
組織の属人化に悩み、再現性のあるチーム作りを目指すすべてのリーダーにとって、最初の一冊としても最適な本です。
人を責めずに問題解決へ導く「仕組み化」5つの思考法
本書で解説されている5つの思考法は、組織運営における問題解決の羅針盤です。
その根幹にあるのは、問題が起きたときに個人の能力や意識を責めるのではなく、すべての原因はルールにあるという考え方になります。
この思考法を身につけることで、感情的な対立を避け、客観的な事実に基づいてチームを正しい方向へ導けるようになります。
| 章 | テーマ | 目的 |
|---|---|---|
| 第1章 | 責任と権限 | 役割の明確化と責任の所在 |
| 第2章 | 危機感 | 健全な緊張感による成長促進 |
| 第3章 | 比較と平等 | 公平な評価基準の構築 |
| 第4章 | 企業理念 | 全員が従うべき行動指針の設定 |
| 第5章 | 進行感 | モチベーション維持と目標達成 |
これらの思考法は、単独で機能するのではなく、相互に関連し合って組織を強化します。
一つずつ理解し、実践していくことで、あなたのチームは誰が抜けても揺るがない、再現性の高い組織へと変わっていきます。
第1章「責任と権限」で役割を明確にする線引き
仕組み化の第一歩は、役割を明確に線引きすることから始まります。
本書でいう「責任」とは結果に対する義務、「権限」とはその責任を果たすために必要な権利を指します。
多くの組織では、部下に目標達成という責任だけを負わせ、値引き交渉や予算執行といった権限を与えないケースが散見されます。
責任と権限が一致していない状態では、部下は板挟みになり、本来のパフォーマンスを発揮できません。
部下に仕事を任せても、結局自分で確認しないと不安になるのはなぜだろう…



それは責任と権限の範囲が曖昧だからです。明確なルールがあれば、安心して任せられますよ。
誰が何に対して責任を持ち、そのためにどこまでの権限を持つのかをルールとして定めること。
その設定により、メンバーは自律的に行動できるようになり、上司は過剰な管理から解放されます。
第2章「危機感」で組織に健全な緊張感をもたらす方法
馴れ合いの組織からは、成長は生まれません。
本書が説く「危機感」とは、恐怖でメンバーを縛り付けるものではなく、設定された目標を達成できなかった場合に自身の評価が下がるという健全な緊張感のことです。
目標を達成しなくても特にペナルティがない環境では、メンバーは「次頑張ればいい」と考え、成長の機会を逃してしまいます。
一方で、ルール通りに行動すれば必ず評価されるという仕組みがあれば、メンバーは安心して挑戦できます。
評価が保証されているからこそ、達成できなかった時の危機感が生まれ、それが個人の成長を促すのです。
明確なルールに基づく危機感は、組織に良い緊張感をもたらし、パフォーマンスを底上げします。
第3章「比較と平等」に基づいた公平な評価基準の作り方
メンバーの不満が生まれる大きな原因は、評価の不公平さにあります。
本書における「比較」は他者との相対評価、「平等」は全員が同じルールのもとで評価される機会の均等を意味します。
上司の主観や好き嫌いで評価が左右される組織では、メンバーのモチベーションは著しく低下します。
例えば、営業成績が同じ2人の社員がいたとして、上司との関係性だけで評価に差がつけば、組織への信頼は失われます。
頑張りを評価したいけど、人によって評価がブレてしまう…



評価は「過程」ではなく「結果」で行うルールを作れば、誰が見ても公平な評価が実現します。
「結果」という客観的な事実に基づいて評価するルールを定めることで、全てのメンバーが納得できる公平な環境が生まれます。
健全な競争意識が芽生え、組織全体の成長につながります。
第4章「企業理念」による行動の拠り所の設定
日々の業務では、判断に迷う場面が必ず訪れます。
その際に道標となるのが「企業理念」です。
本書では、企業理念を単なるお題目ではなく、組織のメンバー全員が従うべき最終的な判断基準であり、行動の拠り所として位置づけています。
例えば、短期的な利益と長期的な顧客満足のどちらを優先すべきか迷った時、「顧客第一主義」という理念があれば、答えは明確です。
100回判断が必要な場面があっても、理念という絶対的なルールが存在すれば、100回とも組織として一貫した意思決定ができます。
企業理念を正しく設定し、組織の末端まで浸透させる仕組みを作ること。
そうすることで、社員一人ひとりが自律的に、かつ会社と同じ方向を向いて行動できるようになります。
第5章「進行感」でメンバーの目標達成を後押しする仕掛け
高い目標を掲げても、そこに至る道筋が見えなければ、メンバーは途中で挫折してしまいます。
そこで重要になるのが、目標に向かって自分が着実に前進していると実感できる「進行感」という感覚です。
1年後の大きな目標だけでは、日々のモチベーションを維持するのは困難です。
最終目標に至るまでに、最低でも月に1回は達成できる短期目標(マイルストーン)を設定し、それをクリアしていく成功体験が進行感を生み出します。
部下のモチベーションをどうやって維持すればいいんだろう?



ゴールまでの道のりを細分化し、小さな成功体験を積み重ねられる仕組みを作りましょう。
上司がやるべきことは、精神論で部下を鼓舞することではありません。
メンバーが進行感を味わいながら、ゲームをクリアするように楽しく目標達成できる仕組みを設計することです。
『とにかく仕組み化』が特に役立つリーダーや管理職の特徴
個人の能力や経験に依存した組織運営に限界を感じ、誰が担当しても同じ成果を出せる再現性のあるチームを作りたいと考えているすべての人に、本書は役立ちます。
もしあなたが日々のマネジメント業務に課題を感じているなら、本書がその解決策を示してくれます。
本書は、以下のような悩みを抱えるリーダーや管理職にとって、特に価値のある一冊です。
| 悩みの特徴 | 本書が役立つポイント |
|---|---|
| 特定の部下に業務が集中している | 業務の標準化とマニュアル作成の方法 |
| 新人や部下の育成に時間がかかりすぎている | 誰が教えてもブレない育成ルールの作り方 |
| 部下のモチベーション管理に疲弊している | 感情ではなく仕組みで行動を促す方法 |
| 会社のルール作りに悩んでいる | 組織の成長段階に応じた公平なルール設計 |
これらの特徴に一つでも当てはまるなら、『とにかく仕組み化』を読むことで、チームや組織が抱える問題の根本原因を特定し、解決への道筋を見つけられます。
特定の部下に業務が集中しているチームのマネージャー
「あの人がいないと仕事が進まない」という状況は、チームにとって大きなリスクです。
これを業務の属人化と呼びます。
例えば、特定の営業担当者しか知らない顧客情報や、ベテランデザイナーしか修正できない制作データが存在する場合、その担当者が急に1週間休んだだけでプロジェクトが完全に停止する恐れがあります。
このような状態は、チーム全体の生産性を著しく低下させる原因となります。
ベテラン社員に頼りきりで、その人がいないと仕事が進まないんです…



その状況こそ、「仕組み化」で解決すべき典型的な課題です
本書の思考法を実践すれば、業務を細かいタスクに分解し、誰でも実行可能なマニュアルを作成できます。
作業手順を標準化することで、特定の個人への依存から脱却し、安定した組織運営を実現します。
新人や部下の育成に時間がかかりすぎている指導者
OJTという名の下で、現場での指導が指導者任せになっていると、教える側の負担が増え、教わる側の成長を遅らせる原因になります。
指導者によって言うことが違ったり、「見て覚えろ」という曖昧な指示が横行したりする環境では、新人は何を基準にすればよいか分からず混乱します。
その結果、本来であれば3ヶ月で習得できる業務に半年以上かかってしまい、育成コストが想定の2倍以上になることも珍しくありません。
教える人によって指示が違うせいで、新人が混乱してしまって…



評価基準と手順をルール化すれば、誰が教えても同じ品質で育成できます
本書で解説されている公平なルールと評価基準を設定することで、指導内容のブレをなくせます。
全員が同じ基準で業務を学ぶ環境は、新人の早期戦力化を促し、指導者の育成にかかる時間と労力を大幅に削減します。
部下のモチベーション管理に疲弊している管理職
部下の「やる気」といった、目に見えず、コントロールできない感情に頼ったマネジメントには限界があります。
成果が出ない原因を「やる気がないからだ」と個人の感情のせいにしていては、いつまで経っても問題は解決しません。
例えば、週初めの朝礼でどれだけ熱意を込めて語っても、具体的な行動が変わらなければ成果は生まれないのです。
部下のやる気を引き出すのが、本当に難しくて疲れます…



感情ではなく、「仕組み」で行動を促すのが識学の考え方です
『とにかく仕組み化』では、個人の感情に介入するアプローチを否定します。
代わりに、目標達成までのプロセスを明確にする「進行感」や、適切な競争を生む「危機感」など、人が自然と行動したくなる仕組み作りを解説します。
この方法論は、管理職を感情的な疲弊から解放し、客観的な事実に基づいたチーム運営を可能にします。
会社のルール作りに悩む経営者や人事担当者
企業の成長に伴い、かつては機能していた暗黙の了解が通用しなくなり、新たなルール作りや既存ルールの見直しに迫られる場面が増えます。
創業メンバーだけで回っていた頃のやり方は、社員が50人、100人と増えるにつれて機能不全に陥ります。
評価制度や権限の範囲、報告ルートなど、組織の土台となるルールをどう設計し、浸透させるかは、多くの経営者や人事担当者が直面する課題です。
会社が大きくなるにつれて、どんなルールを作ればいいのか分からなくなってきました



本書で解説される「責任と権限」の線引きが、ルール作りの出発点になります
本書は、企業理念という抽象的な概念から、日々の業務における具体的な評価基準まで、組織の根幹となるルール作りの思考法を体系的に提供します。
会社の規模や成長段階に合わせて、公平で機能的な仕組みを構築するための実践的な指針となる一冊です。
よくある質問(FAQ)
- 『リーダーの仮面』や『数値化の鬼』との違いは何ですか?
-
安藤広大氏の他の著作、『リーダーの仮面』はリーダー個人の振る舞いに、『数値化の鬼』は客観的な評価手法に焦点を当てています。
それに対し本書は、それらの考え方を組織全体のルールとして実装する「組織 仕組み化」の具体的な方法を解説する内容です。
シリーズの集大成であり、チーム全体の生産性向上を目指す方に最適なビジネス書となります。
- 識学というマネジメント理論を全く知らなくても内容は理解できますか?
-
はい、問題なく理解できます。
本書は識学の前提知識がなくても読み進められるように、仕組み化という思考法の基本から具体例を交えて解説されています。
そのため、マネジメントの本を初めて読む方でも、日々の業務に活かせるヒントを見つけられます。
- 『とにかく仕組み化』を読んだ人の感想や評価はどうですか?
-
多くの読者から、「属人化 解消の具体的なアプローチがわかった」「部下との感情的な対立が減り、本質的な議論ができるようになった」といった肯定的な感想が寄せられています。
特に、問題の原因を個人ではなくルールに求めるという視点が、多くのリーダーにとって新しい気づきとなっているようです。
- デザイナーなど、クリエイティブな職種にも仕組み化は有効ですか?
-
有効です。
仕組み化は創造性を制限するものではなく、むしろ創造的な業務に集中するための環境を整えます。
例えば、案件の進行管理やフィードバックのルールを標準化することで、デザイナーは雑務から解放されます。
その結果、本来のデザイン作業により多くの時間を投入できるようになるのです。
- 本書は、どのような役職の人に特におすすめですか?
-
経営層から現場のチームリーダーまで、人の上に立つすべての方におすすめできます。
特に、数名の部下をまとめる管理職の方が、チームの生産性向上や効率的な人材育成の方法を学ぶのに最適な一冊です。
もちろん、これからリーダーシップを発揮したいと考えている方にも、役立つ思考法が満載です。
- 『とにかく仕組み化』を実践する上で、注意すべき点は何ですか?
-
最初から完璧なルール作りを目指さないことが大切です。
まずは一つの業務の標準化やマニュアル作成から着手し、チームの状況を見ながら改善を重ねていく進め方がよいでしょう。
仕組みは一度作って終わりではなく、組織の成長に合わせて常に見直し続ける姿勢が目標達成には不可欠となります。
まとめ
この記事では、安藤広大氏の著書『とにかく仕組み化』について解説しました。
本書の核心は、問題が起きたときに個人の能力を責めるのではなく、すべての原因は「仕組み」にあるという考え方です。
- 問題の原因を人ではなくルールに求める思考法
- 誰が担当しても同じ成果を出せる再現性の実現
- 感情ではなく客観的な事実に基づくマネジメント
もしあなたが特定の部下に頼りきりのチーム運営に限界を感じているなら、本書を手に取り、感情論から脱却した具体的なルール作りを始めてみてください。