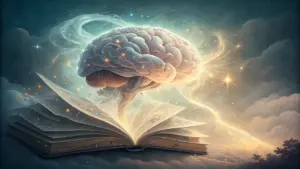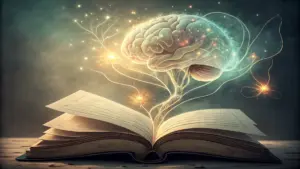日々の仕事が繰り返しに感じられ、やりがいを見失っていませんか。
デイル・ドーテンの名著『仕事は楽しいかね?』が教えるのは、壮大な目標ではなく、日々の小さな「試すこと」こそが現状を打破する鍵であるということです。
この記事では、多くのビジネスパーソンに影響を与えた『仕事は楽しいかね?』のあらすじや要約、心に響く名言をわかりやすく解説します。
本書の教えは、仕事への行き詰まりを感じているあなたの心を軽くし、明日から行動を変えるヒントを与えてくれます。
毎日同じことの繰り返しで、このままでいいのかな…



大丈夫です、本書は壮大な目標がなくても始められる具体的な方法を教えてくれます
- 『仕事は楽しいかね?』が教える「試すこと」の重要性
- 老人マックスとの出会いで変わる主人公の物語あらすじ
- 明日からの仕事が変わる5つの名言
- 2025年に復刊される新版と旧版(中古)の違い
『仕事は楽しいかね?』が教える行き詰まりを打破するヒント
日々の仕事が同じことの繰り返しのようで、やりがいを見いだせないと感じていませんか。
この本が教えてくれるのは、壮大な目標を掲げることよりも、日々の仕事の中で「とにかく試してみること」の重要性です。
現状を打破するヒントは、意外と身近な行動の中に隠されています。
目標設定より「試すこと」が重要な理由
多くのビジネス書では明確な目標設定が成功への鍵だと説かれますが、本書はその考え方に一石を投じます。
なぜなら、完璧な計画を立てても、未来は予測不可能な出来事で満ちているからです。
大切なのは、壮大な目標を探し続けることではなく、今できる小さな「試み」を始めることです。
壮大な目標なんて、なかなか見つからない…



大丈夫です、本書は目標がなくても始められる方法を教えてくれますよ
その試行錯誤のプロセス自体が、予期せぬ発見や新しい目標へとつながっていきます。
立ち止まって悩むよりも、まず一歩を踏み出す勇気が、あなたの仕事を面白くするのです。
変化を恐れず偶然を楽しむ姿勢
本書は、変化を恐れず、むしろ偶然の出会いや出来事を楽しむ姿勢を教えてくれます。
これは「セレンディピティ」、つまり偶然の幸運を発見する能力に近い考え方です。
毎日決まったやり方を繰り返すだけでは、新しい発見は生まれません。
毎日同じことの繰り返しで、新しい発見なんてあるのかな…



本書の教えは、日常に隠れたチャンスを見つける視点を与えてくれます
例えば、いつもの資料作成に一つだけ新しいグラフ表現を試す、といった「遊び感覚」での挑戦が重要です。
そうした小さな変化が、仕事の中に新たな面白さや改善のヒントをもたらしてくれます。
仕事がつまらなくなる思考の癖
仕事が行き詰まる原因は、環境だけでなく「自分自身の思考の癖」にあることも少なくありません。
特に、「完璧でなければならない」「失敗してはいけない」という完璧主義は、新しい挑戦からあなたを遠ざけてしまいます。
失敗するのが怖くて、新しいことに挑戦できない…



その気持ち、よくわかります。完璧を目指さない勇気を本書は与えてくれます
100点満点の成果を目指すあまり、行動できずに0点の結果に終わってしまうのは本末転倒です。
本書は、60点の出来でもいいから、まずやってみることの大切さを説いています。
その思考の癖に気づき、手放すことが、仕事を楽しむための第一歩になります。
山中伸弥教授も学んだ行動の哲学
本書の教えは、単なる心構えにとどまりません。
ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授も、本書から大きな影響を受けたと公言しており、その哲学は世界的な成果にもつながるものです。
まずは試してみて、結果を楽しむことをこの本から学びました。
https://eijipress.co.jp/products/2351
そのおかげでできたのがiPS細胞です。
──山中伸弥(ノーベル生理学・医学賞受賞)
iPS細胞という世紀の大発見が、「試すこと」を繰り返す姿勢から生まれたという事実は、この哲学の普遍的な価値を証明しています。
あなたの仕事においても、小さな試みが大きなブレークスルーを生む可能性を秘めているのです。
物語のあらすじ-老人マックスとの出会いと教え
この物語の核心は、日々の仕事に情熱を失いかけていた主人公が、一人の老人と出会うことで仕事観を根底から覆される点にあります。
偶然の出会いから始まる対話を通して、私たちは仕事を楽しむための本質的なヒントを得られます。
物語の結末は、特別な成功物語ではありません。
しかし、主人公が老人マックスとの対話を通じて、「試すこと」の重要性に気づき、明日からの仕事に対する姿勢を新たにする姿が描かれています。
この出会いは、読者自身の働き方を見つめ直すきっかけを与えてくれます。
主人公が抱える仕事への停滞感
物語の主人公は、あなたと同じように日々の業務をそつなくこなせるようになった一方で、仕事に対する新鮮さや成長実感を失っていました。
キャリアの先行きが見えず、かといって新しい挑戦に踏み出す勇気もない、そんなジレンマを抱えているのです。
特に、社会人として7年目を迎える頃には、多くの人が同様のキャリアの停滞感を覚えます。
この物語は、そんな誰の心にも潜むであろう焦りや不安にそっと寄り添ってくれます。
毎日同じことの繰り返しで、このままでいいのかな…



物語の主人公も、あなたと全く同じ悩みを抱えていました
この誰もが共感できる停滞感こそが、物語の出発点であり、マックスの教えが深く心に響く理由なのです。
吹雪の空港での運命的な出会い
物語が大きく動き出すのは、出張帰りの主人公が猛烈な吹雪によって空港に足止めされる場面です。
すべての便が欠航となり、ロビーで途方に暮れていたその時、一人の老人から声をかけられます。
この出会いこそが、主人公の運命を変えるきっかけとなります。
その謎めいた老人マックス・エルモアとの出会いがなければ、主人公は停滞感から抜け出せなかったかもしれません。
予期せぬアクシデントが、人生を好転させる出会いにつながるという展開は、変化を恐れずに偶然を楽しむことの大切さを象徴しています。
対話で変わっていく主人公の価値観
マックスは主人公に「仕事は楽しいかね?」と問いかけ、そこから二人の対話が始まります。
主人公が信じてきた「目標を立て、計画通りに進めるべき」という仕事の常識は、マックスの言葉によって次々と覆されていきます。
マックスが説くのは、計画に縛られるのではなく、「とにかく試してみて、偶然を楽しむ」という考え方です。
昨日と違う小さな工夫を続けることで、やがて予想もしなかった結果にたどり着くと教えます。
計画なしに、ただ試すだけでうまくいくのかな?



その「試す」ことの積み重ねが、予想もしなかった未来につながるのです
最初は半信半疑だった主人公も、マックスの言葉に耳を傾けるうちに、自身の凝り固まった思考が少しずつほぐれていくのを感じます。
物語の結末と得られる教訓
一夜が明け、吹雪が去るとともに、マックスは主人公の前から姿を消します。
しかし、主人公の心には、仕事を楽しむための確かな指針が残されていました。
この物語から得られる最大の教訓は、日々の小さな「試み」こそが仕事を楽しむ秘訣であるという点です。
壮大な目標や完璧な計画がなくても、昨日より今日、今日より明日と、少しずつ違う自分になることを目指す姿勢が大切なのです。
物語を読み終えたとき、あなたもきっと、明日の仕事で何か新しいことを一つ試してみたくなるはずです。
明日からの仕事が変わる5つの名言
『仕事は楽しいかね?』には、日々の仕事への向き合い方を考えさせられる言葉が散りばめられています。
中でも、現状に行き詰まりを感じているあなたの心を軽くしてくれる5つの名言を厳選して紹介します。
| 名言 | どんなときに心に響くか |
|---|---|
| 「明日は今日と違う自分になる、だよ」 | 毎日の繰り返しに飽き飽きしているとき |
| 「本当の目標は、ある日、偶然に発見するものだ」 | 明確な目標が見つからず焦っているとき |
| 「遊び感覚でいろいろやってみる必要があるんだ」 | 新しい挑戦に臆病になっているとき |
| 「たいていの人は、自分から変化を起こそうとしない」 | 現状維持に甘んじている自分に気づいたとき |
| 「もし、きみが完璧なものを作ろうとしたら、きっと永遠に完成しないだろう」 | 失敗を恐れて一歩を踏み出せないとき |
これらの言葉は、仕事の停滞感を打破し、明日からまた新しい一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。
名言1「明日は今日と違う自分になる、だよ」
これは、昨日と全く同じ今日を過ごすのではなく、ほんの少しでもいいから何か新しいことを試してみようという、マックスからのシンプルな提案です。
例えば、通勤ルートを1本変えてみる、ランチで普段は選ばない店に入る、資料のフォントを少し変えてみるといった小さな変化で構いません。
1日1%の改善を続ければ、1年後には約37倍も成長できるという考え方にも通じます。
毎日同じことの繰り返しで、成長している実感がありません…



大きな変化でなくて大丈夫。昨日とは違う「試すこと」を一つだけやってみましょう。
この言葉は、壮大な目標を立てなくても、日々の小さな試行錯誤こそが自分を成長させ、仕事の楽しさにつながることを教えてくれます。
名言2「本当の目標は、ある日、偶然に発見するものだ」
多くの人が「まずは目標を立てなさい」と教わる中で、この言葉は目標は無理に見つけるものではなく、行動する中で自然と見つかるものだという真実を突いています。
探検家コロンブスがインドを目指して航海に出た結果、アメリカ大陸を発見したように、歴史的な発見の多くは偶然の産物でした。
予期せぬ出会いや出来事の中にこそ、人生を懸ける価値のある目標が隠れているのです。
周りは昇進や転職で目標があるのに、自分だけ何もなくて焦ります。



焦る必要はありません。まずは目の前のことに面白がって取り組むことが、目標への近道です。
目標が見つからないと悩んでいる人にとって、心が軽くなる言葉です。
無理に探すのをやめて、目の前の「試すこと」に集中してみましょう。
名言3「遊び感覚でいろいろやってみる必要があるんだ」
「遊び感覚」とは、失敗を恐れず、結果を気にせず、純粋な好奇心から行動してみることを意味します。
Googleには、業務時間の20%を本来の業務とは異なるプロジェクトに使える「20%ルール」という有名な制度がありました。
この制度から、GmailやGoogleマップといった画期的なサービスが生まれたのです。
これはまさに「遊び感覚」を仕組み化した例と言えます。
仕事は「やらなければならない義務」だと考えがちですが、「楽しんでもいい遊び」と捉え直すことで、新しいアイデアや解決策が生まれやすくなります。
名言4「たいていの人は、自分から変化を起こそうとしない」
この言葉は、多くの人が現状維持を好み、変化を避ける傾向があるという人間の本質を鋭く指摘しています。
現状維持は一見すると安全な道に思えますが、市場や技術が絶えず変化する現代では、変わらないこと自体が最大のリスクになります。
かつて携帯電話市場を席巻したノキアや、フィルムカメラで有名だったコダックが、デジタル化の波に対応できずに衰退した事例が、そのことを物語っています。
周りが動かないから自分も動かないのではなく、自らが小さな変化の起点になることが重要です。
その小さな一歩が、自分自身と周りの環境を変えるきっかけになります。
名言5「もし、きみが完璧なものを作ろうとしたら、きっと永遠に完成しないだろう」
これは、完璧主義の罠に警鐘を鳴らす言葉です。
100点を目指すあまり、いつまでも行動に移せないでいることほど、もったいないことはありません。
Facebookの初期のスローガンは「Done is better than perfect(完璧よりまず終わらせろ)」でした。
まずは60点の完成度でも世に出してみて、利用者からの反応を見ながら改善を繰り返していく方が、結果として良いものが生まれるという考え方です。
失敗するのが怖くて、なかなか新しい企画を提案できません。



完璧な企画書なんてありません。まずは叩き台として提案してみる勇気を持ちましょう。
失敗は成功へのプロセスの一部です。
完成度を気にしすぎるよりも、まずは行動を起こし、そこから学ぶ姿勢が大切だと、この名言は教えてくれます。
著者デイル・ドーテンと書籍の概要
本書のメッセージを深く理解するためには、著者の人物像や書籍の背景を知ることが重要です。
2025年5月には、英治出版から待望の新版が復刊されます。
きこ書房から出ていた旧版との違いも解説するので、どちらを手に取るべきか考える参考にしてください。
| 項目 | 英治出版(新版) | きこ書房(旧版) |
|---|---|---|
| 出版社 | 英治出版 | きこ書房 |
| 発売日 | 2025年5月9日 | 不明(現在は中古品のみ流通) |
| 翻訳者 | 野津智子 | 不明 |
| 特徴 | 新訳、挿絵追加、ツール掲載 | シンプルな構成 |
| 価格 | 1,980円(税込) | 不明(中古価格は変動) |
これから本書を読むなら、現代的な表現で読みやすく、内容も充実している新版から手に取るのが良い選択です。
著者デイル・ドーテンの経歴と人物像
著者デイル・ドーテン氏は、成功者とイノベーションの研究者として知られています。
彼はThe Innovators’ Labという研究機関を創設し、NASA(アメリカ航空宇宙局)をはじめとする数多くの組織に対してコンサルティングを行ってきました。
彼の鋭い洞察は、単なる精神論ではなく、数々の成功事例の分析に基づいています。
だからこそ、本書で語られるマックスの教えには、普遍的な説得力があるのです。
英治出版から復刊される新版の特徴
2025年5月9日に英治出版から復刊される新版は、本文が加筆修正され、野津智子氏による新しい翻訳で生まれ変わった点が最大の特徴です。
価格は1,980円(税込)で、ページ数は224頁となっています。
旧版にはなかった挿絵が追加されたり、仕事に役立つツールが掲載されたりするなど、読者が物語の世界に没入し、より実践的な学びを得られる工夫が施されています。
これから『仕事は楽しいかね?』を読む方にとって、最適な一冊と言えるでしょう。
きこ書房の旧版との違い
新版と旧版の最も大きな違いは、翻訳者と出版社です。
旧版はきこ書房から出版されていましたが、新版は『恐れのない組織』などの翻訳で知られる野津智子氏を迎え、英治出版からの刊行となります。
これにより、文章全体の表現や言葉のニュアンスが新しくなりました。
旧版は現在、中古市場でしか手に入らないため、状態や価格が変動します。
新版と旧版のどちらを読むべきか迷います



メッセージの核は同じなので、古本で安価に手に入る旧版から試すのも一つの手です
すでに旧版を読んだことがある方も、新しい翻訳で読み返すことで、物語から新たな発見を得られるはずです。
この本がおすすめな人の特徴
この本は特に、日々の業務が繰り返しに感じられ、仕事への情熱を失いかけている方に響きます。
明確な目標が見つからずに焦っている方や、キャリアの停滞感を覚えている方にもおすすめです。
本書は、旧版が181ページと比較的短く、物語形式で構成されているため、普段あまり本を読まない方でもスムーズに読み進められます。
| おすすめな人 |
|---|
| 今の仕事に行き詰まりを感じている |
| 仕事が楽しくない、つまらないと感じる |
| 明確な目標が見つからず悩んでいる |
| 失敗を恐れて新しい挑戦ができない |
| 働く意味ややりがいを見失っている |
もし一つでも当てはまるなら、本書があなたの背中をそっと押してくれる一冊になります。
よくある質問(FAQ)
- この本は自己啓発本が苦手な人でも読めますか?
-
はい、物語形式で進むため、小説を読むような感覚で楽しめます。
難しい理論を学ぶというより、主人公と一緒に老人マックスの教えを体験していく構成です。
そのため、一般的な自己啓発本が合わないと感じる方にも、おすすめの一冊となっています。
- 『仕事は楽しいかね?』に漫画版はありますか?
-
現在、公式の漫画版は出版されていません。
しかし、本書は会話を中心とした物語であり、非常に読みやすい内容です。
2025年に復刊される新版には挿絵も追加されるため、活字だけではイメージしにくいと感じる方でも、物語の世界に入り込みやすくなっています。
- 本で紹介される「試すこと」とは、具体的にどんなことですか?
-
壮大な挑戦である必要はありません。
例えば、いつもと違う道で通勤する、会議で使う資料のデザインを少し変える、普段話さない同僚に声をかけてみるといった、ごく小さな変化のことです。
失敗を恐れず、遊び感覚で昨日とは違う行動を一つ取り入れることが、仕事を楽しむコツになります。
- 著者のデイル・ドーテンとは、どのような人物なのでしょうか?
-
デイル・ドーテンは、成功者や新しいアイデアが生まれるプロセスを研究する専門家です。
彼自身が創設した研究機関を通じて、NASA(アメリカ航空宇宙局)をはじめとする多くの組織に助言を行っています。
本書の教訓は、そうした彼の深い知見に基づいています。
- 新版と旧版(中古)では、どちらを読むべきですか?
-
本書の核となるメッセージはどちらを読んでも受け取れますので、安価に内容を知りたい場合は中古の旧版を探すのも一つの方法です。
一方で、2025年5月に出版される新版は、現代的な表現の新しい翻訳で書かれており、内容も加筆修正されています。
より深く理解したいなら新版が最適です。
- 明確な目標がないことに焦りを感じている人にも役立ちますか?
-
はい、まさにそのような方にこそ響く内容です。
本書は「立派な目標は、無理に探すものではなく、日々の試行錯誤の中で偶然見つかるものだ」と教えてくれます。
目標がないことで行動できずにいる方の、心を軽くして最初の一歩を後押ししてくれる一冊です。
まとめ
この記事では、仕事に行き詰まりを感じている方へ向けて、デイル・ドーテンの名著『仕事は楽しいかね?』の要約と心に響く教えを解説しました。
本書が伝える最も大切なメッセージは、壮大な目標を探し求めるのではなく、昨日とは違う小さな「試すこと」を日々積み重ねることで、仕事はもっと楽しくなるという考え方です。
- 壮大な目標より日々の「試すこと」の重要性
- 失敗を恐れず遊び感覚で行動する姿勢
- 昨日とは違う自分になることを目指し変化を楽しむ心
今の仕事にやりがいを見失いかけているなら、まずは本書を手に取ってみてください。
明日から何か一つ、新しいことを試してみることが、あなたの毎日を少しずつ変える確かな一歩となります。