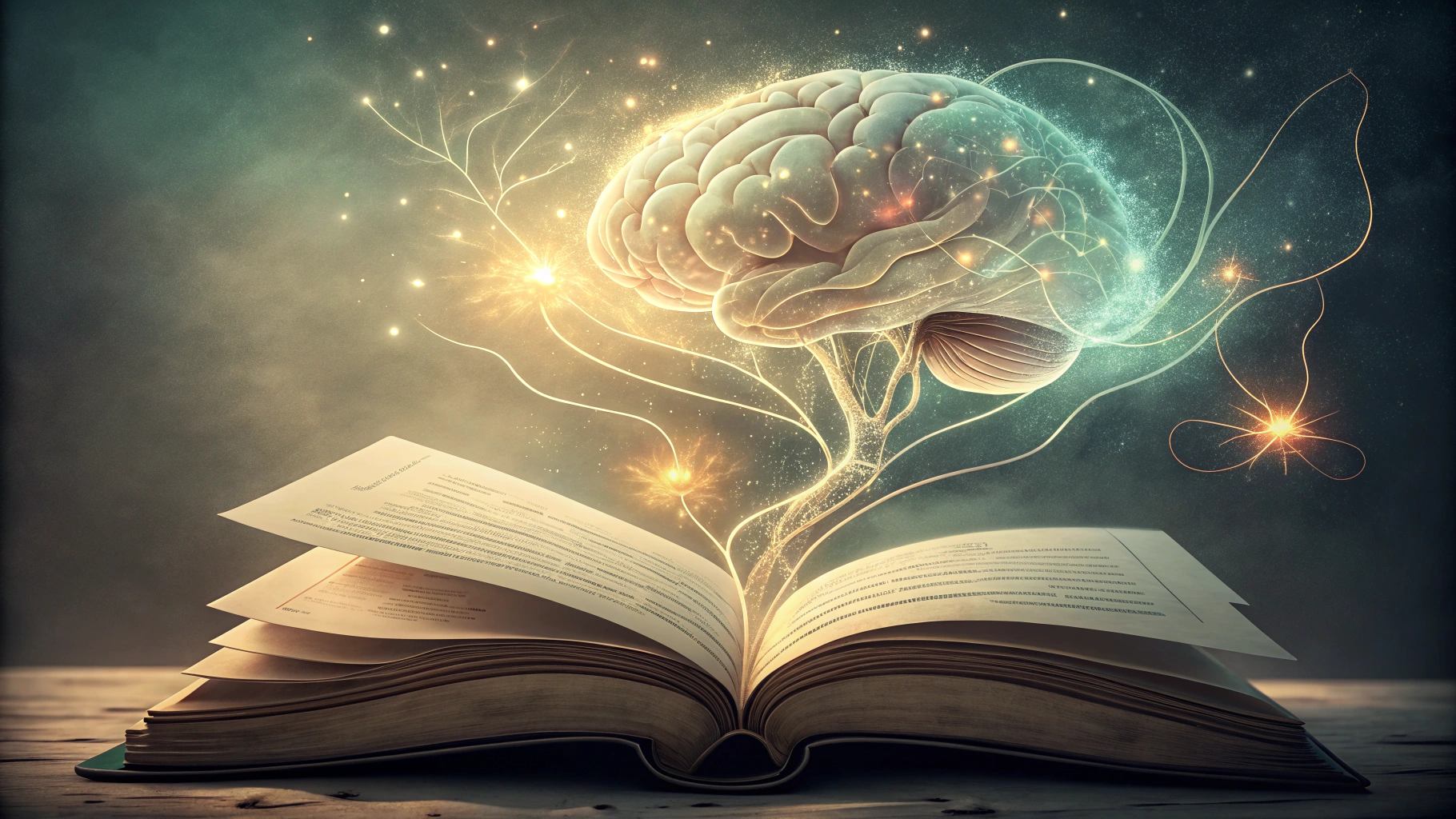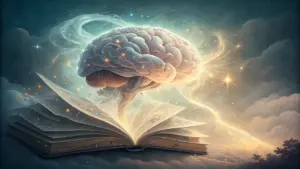毎日コツコツ勉強しているのに、思うように成果が出ないと焦りを感じますよね。
その原因はあなたの努力不足ではなく、努力の方向性が間違っていることにあるのです。
この記事では、書籍『科学的根拠に基づく最高の勉強法』の内容を基に、多くの人が陥りがちな非効率な勉強法と、脳科学が証明したアウトプット中心の学習法をわかりやすく解説します。
毎日2時間も勉強してるのに、なんで記憶に定着しないんだろう…



大丈夫です、この記事であなたの努力を成果に変える具体的な方法がわかりますよ
この記事でわかること
- 努力が報われない非効率な勉強法
- 脳に記憶を刻む5つの科学的テクニック
- 書籍『科学的根拠に基づく最高の勉強法』の概要
努力が報われない勉強からの脱却
毎日コツコツ勉強しているのに、思うように成果が出ないと焦りを感じますよね。
その原因は、あなたの努力不足ではなく、努力の方向性が間違っていることにあるのかもしれません。
『科学的根拠に基づく最高の勉強法』は、そんなあなたの頑張りを正しく成果へ導くための道しるべとなる一冊です。
この章では、まず多くの人が陥ってしまっている非効率な勉強法の正体と、本当に効果のある学習法の考え方について解説していきます。
頑張りが成果に繋がらない本当の理由
「これだけやっているのに覚えられないのは、自分の能力が低いからだ」と自分を責めてしまうこともあるでしょう。
しかし、本当の原因は、学習方法そのものに潜んでいます。
例えば、毎日2時間勉強しているとしたら、1ヶ月で60時間もの時間を費やしている計算になります。
それだけの時間をかけても成果が出ないのは、脳が記憶を定着させる仕組みに合っていない方法で学習しているからです。
コロラド大学の研究では、文章を1回だけ読んだ学生と2回読んだ学生とで、2日後のテストの成績に統計的な差はなかったという結果が出ています。
つまり、ただ時間をかけてインプットを繰り返すだけでは、努力が報われにくいのです。
毎日頑張っているのに、やり方が間違っていたなんて…



大丈夫です。それに気づけた今が、学習法を見直す絶好の機会ですよ。
努力を無駄にしないために、まずは「なぜ成果が出ないのか」という根本的な原因を正しく理解することが、脱却への第一歩となります。
多くの人が信じる非効率な学習の常識
私たちは、学校教育などを通じて「繰り返し読む」「ノートをきれいにまとめる」「マーカーで線を引く」といった勉強法を当たり前のように教わってきました。
しかし、本書ではこれらの方法は「やった気」にはなっても、記憶の定着という点では効率が低いと指摘しています。
これらの方法は、脳にあまり負荷がかからない「受動的な学習」だからです。
内容を理解したつもりになったり、情報を整理したりするだけで、脳が「これは重要な情報だ」と認識して長期記憶に保存するプロセスが働きにくいのです。
| よくある勉強法 | 非効率とされる理由 |
|---|---|
| 繰り返し読む | 内容を理解したと錯覚しやすい |
| ノートに書き写す・まとめる | 情報を整理するだけで記憶する作業ではない |
| ハイライト・下線を引く | 重要部分を把握するだけで記憶には繋がらない |
もちろん、これらの方法が全くの無意味というわけではありません。
しかし、学習の中心にこれらの方法を据えている限り、かけた時間に見合う成果を得るのは難しいでしょう。
脳科学が導き出すアウトプット中心の学習法
では、どのような学習法が効率的なのでしょうか。
本書が一貫して主張しているのが、アウトプット中心の学習法です。
アウトプットとは、学んだ知識を脳の中から「思い出す」作業を指します。
「思い出す」という行為は、脳にとって負荷のかかる能動的な作業です。
この負荷こそが脳の神経回路を強化し、「この情報は生きていく上で必要だ」と判断させて記憶を強固に定着させます。
この「思い出す」トレーニングは、認知心理学でアクティブリコール(想起練習)と呼ばれており、その効果は数多くの研究で証明されているのです。
読むんじゃなくて、思い出す方が大事だったのか!



その通りです。脳に心地よい汗をかかせるイメージで取り組むと効果的です。
インプットした知識を自分の言葉で説明してみる、参考書を閉じて内容を書き出してみる。
こうしたアウトプットの機会を増やすことこそが、あなたの努力を確実な成果へと繋げる鍵となります。
まずはやめるべき3つの非効率な勉強法
多くの人が良かれと思って実践している勉強法の中には、実は科学的に効果が低いと証明されているものが存在します。
もしあなたが「時間をかけているのに成果が出ない」と感じているなら、その原因は努力の量ではなく、その方法にあるのです。
これから紹介する勉強法は、一見すると熱心に学習しているように見えますが、脳にとっては受動的な作業に過ぎず、記憶の定着には繋がりにくいものです。
まずは非効率な勉強法を手放すことで、あなたの学習効果は大きく変わります。
読んだ気で終わる「繰り返し読む」作業
参考書を何度も読み返す方法は、内容を覚えるための受動的な学習であり、記憶の定着率が低いことがわかっています。
文字を目で追っているだけでは、脳は内容を深く処理せず、「知っている」という感覚だけが残ってしまうのです。
実際に、コロラド大学で行われた研究では、文章を続けて2回読んだ学生と1回だけ読んだ学生とで、2日後に行ったテストの成績に統計学的に意味のある差はなかったと報告されています。
何度も読む時間があるなら、次に紹介するアウトプット中心の学習法に時間を使いましょう。
参考書を何度も読めば覚えられると思っていました…



「読んだ回数」ではなく「思い出した回数」が記憶の鍵です
ただ読む作業は、脳に内容を理解したと錯覚させる「流暢性の錯覚」を引き起こすだけです。
本当に知識を自分のものにするためには、本を閉じて内容を思い出す作業が必要不可欠です。
記憶の定着に繋がらない「ハイライトや下線」
教科書や参考書の重要な部分にハイライトや下線を引く行為も、脳に負荷がかからないため記憶に残りにくい勉強法です。
線を引くという単純作業に集中してしまい、内容を能動的に理解しようとする思考が停止しがちになります。
多くの人が経験するように、最初は重要な部分だけに線を引いていたはずが、最終的にはページの8割以上がマーカーで埋め尽くされ、結局どこが大切かわからなくなるケースは少なくありません。
これは、情報を処理したのではなく、ただ色を塗る作業をしただけになっている証拠です。
重要な部分にマーカーを引くと、勉強した気になっていました



線を引く作業が目的になってしまうと、脳は思考を停止します
線を引く行為そのものに学習効果はほとんどありません。
重要なのは、どの情報が本当に大切なのかを自分の頭で考え、取捨選択する思考のプロセスなのです。
脳に記憶を刻み込む科学的なテクニック5選
本書で紹介されている、脳科学に基づいた本当に効果のある勉強法を5つ紹介します。
これらのテクニックで最も重要なのは、学んだ情報を脳から「思い出す」作業を意識的に行うことです。
| テクニック名 | 概要 | 効果 |
|---|---|---|
| アクティブリコール | 情報を見ずに思い出す | 記憶の定着を促進 |
| 分散学習 | 時間を空けて復習する | 長期記憶を強化 |
| インターリービング | 複数の科目を交互に学ぶ | 応用力や思考力を養成 |
| 精緻的質問 | 「なぜ?」を自問する | 理解を深める |
| 自己説明 | 自分の言葉で説明する | 知識の構造化を促進 |
これら5つのテクニックは単独でも効果を発揮しますが、組み合わせることで学習効率はさらに向上します。
思い出す作業で知識を強化するアクティブリコール
アクティブリコールとは、教科書や参考書を見ずに、学んだ内容を自分の頭の中から思い出す学習法です。
「想起練習」とも呼ばれます。
例えば、単語帳で英単語を覚える際、答えをすぐに見るのではなく、10秒間じっくりと思い出す努力をするだけで、記憶への定着率が向上するという研究結果があります。
本書では、具体的な方法として「白紙勉強法」が紹介されています。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 覚えたいことを元の情報を見ずに書き出す |
| ② | 分からない部分や忘れている部分を教科書などで確認する |
| ③ | ①と②を繰り返す |
| ④ | 時間をおいて、再度①〜③を繰り返す |
参考書を閉じて思い出すなんて、時間がかかりそう…



最初は大変ですが、この「思い出す苦労」こそが記憶を強力にするんです。
この思い出すプロセスが脳を刺激し、神経回路を強化するため、知識が忘れにくい長期記憶として脳に刻み込まれます。
忘れることを前提とした最適な復習タイミングの分散学習
分散学習とは、一度にまとめて勉強するのではなく、適切な間隔を空けて復習することで記憶を強化するテクニックです。
脳が一度忘れかけた情報を再び思い出すことで、記憶がより強固になります。
心理学者ヘルマン・エビングハウスの研究によると、人は学習した内容を1日後には約74%忘れてしまいます。
忘れることを前提に計画的な復習が不可欠です。
| 復習回数 | タイミングの目安 |
|---|---|
| 1回目 | 学習した翌日 |
| 2回目 | 1回目の復習から1週間後 |
| 3回目 | 2回目の復習から2週間後 |
| 4回目 | 3回目の復習から1ヶ月後 |
復習のタイミングって、具体的にどう決めればいいんだろう?



まずは「1日後、1週間後、1ヶ月後」を目安にスケジュールを組んでみましょう。
応用情報技術者試験のように出題範囲が広い試験では、この分散学習を取り入れることで、試験日当日まで知識を着実に維持できます。
複数科目を交互に学び思考力を養うインターリービング
インターリービングとは、一つの科目を長時間集中して学習するのではなく、複数の異なる科目や分野を交互に織り交ぜながら学習する方法を指します。
ある研究では、数学の問題を分野ごとにまとめて解くグループよりも、複数の分野の問題を混ぜて解いたグループの方が、テストの成績が25%も高かったという結果が出ています。
| 集中学習(効果が低い) | インターリービング(効果が高い) | |
|---|---|---|
| 学習計画の例 | 午前:ネットワーク、午後:セキュリティ | 1時間ごとにネットワークとセキュリティを交互に学習 |
| メリット | 一時的な習得感を得やすい | 思考の柔軟性が高まり、応用力が身につく |
| デメリット | 応用力が身につきにくい | 学習の進捗を感じにくく、最初は難しく感じる |
一つのことに集中した方が効率的な気がするんだけど…



脳が毎回違う情報に対応しようとすることで、本質的な違いや共通点を見抜く力が鍛えられます。
毎回脳のスイッチを切り替える必要があるため負荷はかかりますが、この切り替えこそが知識を実践で使える「応用力」へと変化させるのです。
なぜを繰り返し深い理解を促す精緻的質問
精緻的質問とは、学習している内容に対して「なぜそうなるのか?」「どういうことか?」と自分自身に問いかけ、その答えを探すプロセスのことです。
例えば、プログラミングで新しいアルゴリズムを学ぶ際、単にコードを暗記するのではなく「なぜこのロジックで問題が解決できるのか?」と最低でも5回は「なぜ」を繰り返すことで、表面的な理解から脱却できます。
| 質問の例 | 対象 |
|---|---|
| この技術が生まれた背景は何か? | 新しいIT技術 |
| この単語と似た意味の単語の違いは何か? | 英単語 |
| なぜこの公式で答えが導き出せるのか? | 数学の公式 |
質問を考えるのが面倒で、つい読み進めてしまう…



立ち止まって考える時間こそが、知識を自分のものにするための近道ですよ。
このように学習内容を深く掘り下げることで、情報同士の繋がりが生まれ、単なる知識の断片が体系的な理解へと変わります。
自分の言葉で説明し記憶に定着させる自己説明
自己説明とは、学んだ内容をあたかも誰かに教えるかのように、自分の言葉で説明してみる学習法です。
「プロテジェ効果」とも関連が深く、人に教えることで学習効果が高まる現象を利用します。
ある研究では、学習した内容を後で誰かに教えると伝えられた学生は、テストを受けるとだけ伝えられた学生に比べて、内容をより深く、構造的に理解していたことが分かっています。
| ポイント | 具体的な行動 |
|---|---|
| 相手を想定する | 専門知識のない友人や家族に説明するつもりで |
| 専門用語を避ける | 15歳でもわかるような簡単な言葉に言い換える |
| 図や例え話を使う | 複雑な概念は身近なものに例えて説明する |
一人でブツブツ説明するのは、ちょっと恥ずかしいかも…



声に出すのが難しければ、ブログに書いたり、学習仲間と説明し合ったりするのもおすすめです。
自分の言葉で再構築する過程で、理解が曖昧な部分が明確になり、知識の穴を埋めることができるため、記憶への定着が促進されます。
書籍「科学的根拠に基づく最高の勉強法」の概要
本書は、多くの学習者が信じてきた「繰り返し読む」「ノートをきれいにまとめる」といった勉強法が、実は科学的に非効率であることを数多くの論文を基に解説しています。
そして、その代わりに学んだ知識を思い出すアウトプット中心の学習法こそが、記憶を定着させ成果に繋げる鍵であると教えてくれる一冊です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 著者 | 安川 康介 |
| 出版社 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2024年02月15日 |
| ページ数 | 256ページ |
| 定価 | 1,760円(税込) |
この本に書かれている内容を実践することで、あなたの学習は「努力が報われる」ものへと変わります。
本書の信頼性や具体的な内容について、さらに詳しく見ていきましょう。
著者安川康介氏の経歴と本書の信頼性
著者である安川康介氏は、アメリカで臨床医として働く現役の医師です。
ご自身の医学部受験や国家試験といった過酷な経験から得た知見と、認知心理学などの最新研究データを組み合わせた勉強法を発信しています。
本書は、YouTubeで414万回以上再生された同名の動画を、さらに詳しく解説し書籍化したものです。
個人の体験談だけじゃなくて、本当に信頼できる情報なのかな?



本書は著者の経験に加え、認知心理学などの最新研究データが豊富に引用されているので、信頼性は抜群ですよ。
著者の経歴がすごい。目標を立てて一握りのトップになった人の勉強法は、参考にならない訳がない。アクティブリコール・想起練習、分散学習、プロダクション効果、プロテジェ効果、精緻性質問、自己説明、インターリービング、イメージ記憶術、睡眠や運動の学習への効果など、さまざまな方法につき論文を参照に推奨をあげている。学んだことを白紙にアウトプットして、場所も変えながら、メタ認知を働かせて客観的な評価をし、運動をした後に勉強して、睡眠を7時間以上とること。「今日、一日の区切りで生きる」著者の姿勢を見習いたいです。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322310000993/
このように、医師としての専門性と科学的根拠が本書の信頼性を裏付けており、多くの学習者にとって実践する価値のある内容となっています。
学習効果を最大化する心と体の整え方
本書では、単なる勉強テクニックだけでなく、学習効果の土台となる心と体のコンディション管理がいかに重要かを科学的根拠と共に解説しています。
特に、記憶の定着に不可欠な睡眠と、脳の働きを活性化させる運動の役割について詳しく述べられています。
レビューにもあるように、最低でも7時間以上の睡眠を確保することが推奨されています。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 睡眠 | 脳が日中に学んだ情報を整理し、長期記憶として定着させるための重要な時間 |
| 運動 | 脳の血流を促進し、記憶や学習に関わる神経伝達物質の分泌を促す効果 |
| メタ認知 | 自分の学習状況を客観的に把握し、計画を修正する能力 |
| 環境 | 勉強に集中できる場所を選んだり、複数の場所を使い分けたりする工夫 |
根性論じゃなくて、体調管理も大事なんだな。



脳のパフォーマンスを最大限に引き出すには、適切な休息と運動が科学的に見ても不可欠なんです。
どんなに優れたテクニックを用いても、心と体が疲れていては効果は半減します。
最高のパフォーマンスを発揮するために、まずは生活習慣から見直すことが大切です。
資格試験から日々の学習まで応用できる実践例
本書で紹介されている勉強法は、特定のテスト対策に留まらず、日々のあらゆる学習に応用できる普遍性を持っています。
例えば、覚えた知識を思い出す「アクティブリコール」や、学習間隔を空ける「分散学習」は、様々な場面で効果を発揮します。
応用情報技術者試験のように広範囲の知識が求められる資格試験では、分散学習で計画的に復習し、知識の抜け漏れを「白紙勉強法」で洗い出すといった応用が考えられます。
第2章までを読了した感想です。黒板の内容を書き写したり、重要箇所を必死にマーカーしたりしても、なかなか記憶できなかったのは、覚える手段として効果的でなかったからかもしれない。記憶を定着するためのアウトプットの方法はいろいろとあるらしい。個人的に、仕事のことは長期間、多くのことを覚えられているのに、読書の記憶がすぐに消えていくのはなぜだろうと感じていたけど、理解できた気がする。仕事で実践していたことは、比較的適した方法だったということ。子どもたちが繰り返す、なぜという疑問も、知識の定着に役立つ、それも納得。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322310000993/
| テクニック | 応用できる学習シーンの例 |
|---|---|
| アクティブリコール | 資格試験の知識確認、英単語の暗記、読んだ本の内容の要約 |
| 分散学習 | 長期的な試験対策、語学学習の単語復習、プログラミングの文法習得 |
| 精緻的質問・自己説明 | 専門書の内容理解、プレゼンテーションの準備、後輩への業務説明 |
本書のテクニックを実践することで、資格試験の合格はもちろん、読書や仕事でのスキルアップといった生涯にわたる学習の質を高めることができます。
まとめ
この記事では、書籍『科学的根拠に基づく最高の勉強法』を基に、あなたの努力を成果に変える学習法を解説しました。
最も大切なのは、参考書を繰り返し読むインプットではなく、学んだ内容を自分の頭で「思い出す」アウトプットを学習の中心に据えることです。
- 努力が報われない非効率な勉強法
- 記憶を定着させるアウトプット中心の学習法
- 具体的な5つの科学的テクニック
- 学習効果の土台となる心と体の整え方
まずは、今日学習した内容を参考書を閉じて白紙に書き出すことから始めてみてください。
脳に汗をかくこの小さな習慣が、あなたの未来を大きく変える第一歩となります。