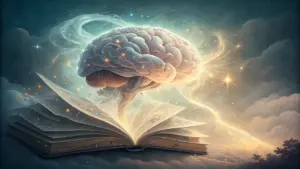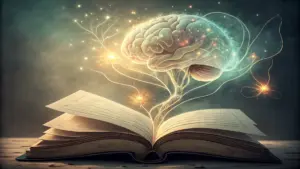「企画の軸がブレて、結局何が言いたいの?と指摘される…」そんな悩みは、多くの企画担当者が抱えるものです。
『コンセプトの教科書』は、コンセプト作りをセンスではなく誰でも再現できる「技術」として解説した一冊です。
当記事では、本書の要約を通じて、新しい価値を生むための思考法を具体的な作り方や事例と共にわかりやすく解説します。
毎回アイデアが散らばって、企画の軸が作れないんだ…



本書の思考法を学べば、誰でもブレない企画の軸を作れるようになります
- 『コンセプトの教科書』の要点
- センスに頼らないコンセプトの作り方
- ビジネスで役立つ具体的な事例
- この本がおすすめな人の特徴
企画の軸がブレる悩みからの脱却
企画書を作成するたびに、「結局何が言いたいの?」と指摘されてしまう経験はありませんか。
その悩みの根本原因は、企画の「軸」となるコンセプトが定まっていないことにあります。
本書『コンセプトの教科書』を読めば、センスに頼らず、誰でもブレない企画の軸を作る技術が身につきます。
この章では、企画がなぜ伝わらないのか、その根本的な理由を解き明かし、ブレない軸がいかに重要であるかを解説します。
企画が伝わらない根本的な理由
あなたの企画が伝わらないのは、プレゼン能力の問題ではありません。
そもそも「コンセプト」が曖昧なため、話の前提が共有できていないことが一番の原因です。
コンセプトとは、商品やサービスの核心となるアイデアや思想であり、関係者全員の目印となる北極星のようなものを指します。
例えば、プロジェクトメンバーが10人いれば、10人全員が同じ方向を向いて進めるようにするのがコンセプトの役割です。
この共通認識がないままでは、どんなに優れたアイデアもバラバラになり、誰の心にも響かない企画になってしまいます。
確かに、いつも途中で「あれも良いな、これも良いな」ってアイデアが散らばっちゃうんだよな…



その散らばったアイデアを束ねるのが、まさにコンセプトの力です
まずは、自分の企画に明確なコンセプトが存在するかどうかを見直すことから始めましょう。
それが、伝わる企画への第一歩となります。
センスに頼らないコンセプト立案の技術
「コンセプト作りはセンスが必要だ」と思われがちですが、本書はそれを否定します。
コンセプト立案は、誰でも学び、実践できる「技術」であると断言しているのです。
本書では、そのための具体的な思考法が体系的に解説されています。
その技術の第一歩が、「良い問い」を立てることです。
例えば、「エレベーターの待ち時間が長い」という課題に対し、「エレベーターを速くするには?」と問うのではなく、「エレベーターの待ち時間を気にならなくするには?」と問い直すだけで、生まれるアイデアの方向性は大きく変わります。
なるほど、問いの立て方次第で解決策が変わってくるのか!



はい、優れたコンセプトは、優れた問いから生まれるのです
このように、視点を変える思考法を学ぶことで、ひらめきに頼らず、論理的に新しい価値を生み出すコンセプトを立案できるようになります。
顧客の心を動かすブレない軸の重要性
なぜ、ブレない軸、つまり強力なコンセプトが重要なのでしょうか。
それは、コンセプトが顧客の購買意欲や共感を直接的に引き出すからです。
人々は単にモノやサービスを買うのではなく、その裏にある思想や価値観に心を動かされます。
Amazon Kindleの成功事例を考えてみましょう。
もし彼らのコンセプトが「高性能な電子書籍リーダー」だったら、ここまで普及しなかったかもしれません。
しかし、彼らは「どこでも手軽に読書を」というコンセプトを掲げ、読書体験そのものを変える価値を提案したことで、多くの顧客の心を掴みました。
優れたコンセプトは、他社との明確な差別化を生み出すだけでなく、顧客との強い絆を築く源泉となります。
ブレない軸を持つことで、あなたの企画は単なるアイデアから、人の心を動かす力を持つビジネスへと進化するのです。
『コンセプトの教科書』の要約-新しい価値を生む思考法
本書で解説されているのは、単なるアイデア出しの技術ではありません。
新しい価値を生み出すための思考のプロセスそのものを体系的に学べる点に、最大の価値があります。
企画の出発点となる「問い」の立て方から、視点を変える「リフレーミング」、核心を突く「一行化」、そして戦略に落とし込む「4C分析」まで、一連の流れを身につけることが可能です。
| 思考法 | 概要 |
|---|---|
| 良い問い | 新たな可能性を切り開く出発点となる、現状への深い洞察から生まれる疑問 |
| リフレーミング | 物事を今までとは違う枠組みで捉え直し、新しい解決策を生む思考法 |
| 一行化 | コンセプトの核心を、シンプルかつ魅力的な一文で表現する技術 |
| 4C分析 | 従来の3C分析にコンセプトを加え、戦略の軸とするアプローチ |
これらの思考法を実践することで、センスに頼らず、誰でも再現性のある形で強力なコンセプトを生み出せるようになります。
すべての始まりとなる「良い問い」の立て方
コンセプト作りにおける「良い問い」とは、現状への深い洞察から生まれ、新たな可能性を切り開く出発点となるものです。
問いの質が、その後に続くアイデアの質と量を決定づけるため、すべての始まりと言えます。
例えば「エレベーターの待ち時間が長い」という課題に対し、「エレベーターを速くするには?」と問うと解決策は限られます。
しかし、「待ち時間を気にならなくするには?」と問い直すことで、鏡を設置して身だしなみを整える時間にするなど、全く新しい解決策が生まれるのです。
問いの立て方だけで、そんなにアイデアが変わるものなのかな?



はい、問いの質がアイデアの質を決定づけます。良い問いは、思考の制約を外し、創造性を飛躍させるきっかけになりますよ。
表面的な問題解決ではなく、課題の本質を見抜く「良い問い」を立てる習慣こそが、凡庸な企画と優れた企画を分ける最初の分岐点となります。
視点を変える思考法「リフレーミング」
リフレーミングとは、ある事柄を今までとは違う枠組みで捉え直す思考法です。
行き詰まった状況を打開し、誰も気づかなかった価値を発見するためのカギとなります。
この思考法を用いると、例えば「過疎化が進む地方」という課題を「手つかずの自然が残る静かな場所」と捉え直すことができます。
これにより、ネガティブな状況をワーケーションやグランピングといったポジティブな価値へと転換させることが可能です。
いつも同じような切り口のアイデアしか出なくて困っているんだ…



リフレーミングを意識すれば、凝り固まった視点をリセットし、思考の行き詰まりを打破するきっかけになります。
物事を見る角度を意識的に変えるリフレーミングは、常識や前提にとらわれない、新しいコンセプトを生み出すための強力な武器になるのです。
核心を突く「一行化」のノウハウ
一行化とは、複雑なコンセプトの核心を、誰にでも伝わるシンプルで魅力的な一文に要約する技術です。
どんなに優れたアイデアも、その価値が伝わらなければ意味がありません。
Amazon Kindleの「どこでも手軽に読書を」という一行は、まさにその好例です。
この言葉は、Kindleが提供する新しい読書体験という価値を明確に伝え、多くのユーザーの心を掴みました。
優れた一行は、企画に関わる全ての人の認識を統一し、プロジェクトを推進する力を持つようになります。
自分の企画も、一言で言い表せたら説得力が増すんだろうな。



その通りです。一行化は、企画の価値を上司やクライアントに瞬時に理解させ、賛同を得るための最も効果的な方法です。
練り上げたコンセプトを、人の心を動かす「一行」に磨き上げるノウハウを学ぶことで、あなたの企画の伝達力は格段に向上します。
従来の3C分析を超える「4C分析」という戦略
4C分析とは、従来の3C(Customer:顧客、Competitor:競合、Company:会社)に、本書の核となるConcept(コンセプト)を加えた独自の戦略フレームワークです。
この分析法は、顧客や競合、自社の分析結果をバラバラに扱うのではありません。
コンセプトを戦略の中心に据えることで、3つのCが有機的に結びつき、一貫性のある強力なマーケティング戦略を立てることが可能になります。
| 分析要素 | 説明 |
|---|---|
| Customer | ターゲットとなる顧客のニーズやインサイト |
| Competitor | 競合の強みや弱み、市場での立ち位置 |
| Company | 自社の持つ技術やリソース、企業理念 |
| Concept | これら3Cを束ね、新しい価値を定義する中心的な思想 |
4C分析をビジネスに取り入れることで、小手先の戦術ではなく、事業の根幹からぶれないブランドを構築し、顧客から選ばれ続けるための道筋が見えてきます。
ビジネスを動かすコンセプトの作り方と事例
『コンセプトの教科書』で解説されている思考法は、理論だけでなく実際のビジネスシーンで大きな力を発揮します。
優れたコンセプトがいかにして新しい価値を生み出し、事業を成功に導くのかを具体的な事例と共に見ていきましょう。
ここからは、学んだ知識を実務に活かすためのヒントを紹介します。
Amazon Kindleの成功を導いたコンセプト
Amazon Kindleは、「どこでも手軽に読書を」というシンプルなコンセプトを掲げ、電子書籍市場を切り拓きました。
このコンセプトは、単に紙の本を電子化する技術的な側面だけを捉えたものではなく、「読書体験そのものを、場所や時間に縛られずにもっと自由にする」という新しい価値を顧客に提供したのです。
この考え方に基づき、Kindleは数百冊の本を1台の端末で持ち運べる利便性や、読みたい本をその場ですぐに購入できる手軽さを実現しました。
その結果、多くの人々にとって読書がより身近なものになったのです。
どうすればこんなに強いコンセプトが作れるんだろう?



本書で解説されている「良い問い」を立てる技術が、その答えを示してくれます。
Kindleの成功は、顧客が潜在的に抱えていた不便さを解消するコンセプトが、新しい市場を創造する力を持つことを証明しています。
商品開発やサービスを成功に導くマーケティング戦略
どんなに良い商品やサービスでも、その価値が顧客に伝わらなければ意味がありません。
本書では、従来の3C分析(顧客・競合・自社)に「コンセプト」を加えた「4C分析」という独自のフレームワークを提唱しています。
これは、コンセプトを全ての戦略の出発点に置く考え方です。
コンセプトを最初に固めることで、ターゲット顧客に響くメッセージからプロモーションの手段まで、一貫性のあるマーケティング活動を展開できます。
例えば、商品開発の方向性が定まり、広告で伝えるべき内容もブレなくなります。
コンセプトを最初に決めれば、企画の方向性がブレなくなるんですね。



その通りです。コンセプトが、全ての施策の判断基準になります。
この4C分析を用いることで、他社との差別化が明確になり、顧客の心に深く響く強力なブランドを構築する土台ができます。
あなたの企画書を変えるための第一歩
本書で学んだ思考法を、あなたの仕事に活かすための最初のステップは、企画の核心を短い言葉で表現する「一行化」を実践することです。
複雑な企画内容も、たった一行でその価値を伝えられるようになると、説得力が大きく増します。
例えば、次の会議で提案する企画について、「この企画を一言で表すと何か?」と自問自答してみてください。
このプロセスを経るだけで、企画の骨子が明確になり、上司やクライアントへの説明も驚くほどスムーズになるはずです。
本書で紹介されている「問いを立てる」「リフレーミングする」「一行化する」といった技術は、一度身につければあらゆるビジネスシーンで応用できます。
まずは小さな企画からでも、この思考法を試してみることが、あなたの企画書を根底から変える確実な一歩となるのです。
著者・細田高広『コンセプトの教科書』の書籍情報と読者の感想
企画のアイデアは浮かぶのに、どうも形にならないと悩んでいませんか。
本書は、単なるノウハウ本ではなく、新しい価値を生み出すための思考法そのものを体系的に学べる一冊です。
ここでは、本書の基本情報から、著者である細田高広氏の経歴、そして実際に読んだ人々の感想まで、購入を検討する上で知りたい情報をまとめました。
あなたの企画立案プロセスを根底から見直すきっかけになる書籍です。
書籍のあらすじと基本情報
『コンセプトの教科書』は、商品やサービスの核心となるアイデア、すなわち「コンセプト」の作り方を、具体的な思考のステップに沿って解説したビジネス書です。
センスやひらめきに頼るのではなく、誰でも実践可能な技術として、「問い」の立て方から「一行化」による表現方法までを丁寧に説明しています。
どんなことが書かれている本なんだろう?



単なるアイデア出しのテクニックではなく、価値を生むための思考法そのものが学べます
本書の基本的な情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書名 | コンセプトの教科書 あたらしい価値のつくりかた |
| 著者 | 細田高広 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 形式 | 単行本(ソフトカバー) |
| ページ数 | 288ページ |
288ページにわたり、豊富な事例とともにコンセプト作りの神髄が詰まっています。
企画の根幹をしっかりと固めたいと考えるすべての人にとって、心強い味方となるでしょう。
著者・細田高広氏の経歴
本書の著者である細田高広氏は、大手広告代理店の博報堂で長年クリエイティブディレクターとして活躍してきた人物です。
数々の有名企業のブランディングやマーケティング戦略、商品開発に携わってきた実績を持ちます。
その豊富な経験から導き出された、実践的で再現性の高いノウハウが本書には凝縮されているのです。
机上の空論ではない、現場で磨き上げられた思考法だからこそ、多くのビジネスパーソンの心に響きます。
実際に読んだ人々のレビューや評判
本書は多くの読者から高い評価を得ています。
「読書メーター」では488人が登録しており、その注目度の高さが分かります。
具体的な感想としては、「これまで感覚で進めていた企画立案に、明確な指針ができた」「アイデアを言語化するプロセスが分かり、上司やクライアントへの説明が驚くほどスムーズになった」といった声が数多く寄せられています。
みんなは、この本をどう評価してるの?



思考が整理され、企画書が書きやすくなったという感想が多く見られます
コンセプトという掴みどころのないものを、具体的な技術として習得できる点が、多くの読者から支持される理由です。
この本がおすすめな人の特徴
本書は、特に企画の軸がブレてしまい、アイデアを上手く形にできないと感じている人にとって、突破口となる一冊です。
もしあなたが以下のような課題を抱えているなら、きっと役立つはずです。
| おすすめな人の特徴 |
|---|
| 企画を立てるたびに話の方向性がブレてしまう人 |
| 自分のアイデアを上手く言葉にして伝えられない人 |
| マーケティングや商品開発の担当者で、提案の説得力を高めたい人 |
| センスやひらめきに頼らない、再現性のある企画力を身につけたい人 |
これらの悩みに一つでも当てはまるのであれば、『コンセプトの教科書』はあなたのビジネススキルを一段階引き上げてくれるでしょう。
よくある質問(FAQ)
- コンセプト作りにはセンスが必要だと思ってしまいますが、本当に技術だけで大丈夫なのでしょうか?
-
はい、大丈夫です。
『コンセプトの教科書』は、コンセプト作りがセンスではなく誰でも習得できる「技術」であると明確に示します。
その核心は、良い「問い」を立て、視点を変える「リフレーミング」を行い、最後に「一行化」するという具体的なノウハウにあります。
この思考法を実践すれば、ひらめきに頼らず、論理的に新しい価値を生み出すことが可能です。
- 本書に出てくる「リフレーミング」という思考法がよくわかりません。具体的にどういうことですか?
-
リフレーミングとは、物事を今までとは違う枠組みで捉え直す思考法です。
例えば、「欠点」と見られていたことを「他にはない個性」という価値に捉え直すことを指します。
このように視点を変えることで、行き詰まった状況を打開し、誰も気づかなかった新しいアイデアを発見するきっかけになります。
- 『コンセプトの教科書』を読んだら、マーケティングや商品開発にどう活かせますか?
-
本書で提唱される「4C分析」は、マーケティング戦略の根幹を定めるのに役立ちます。
コンセプトを軸に顧客、競合、自社を分析することで、一貫性のあるメッセージを顧客に届けられます。
このアプローチは、ブレないブランディングを実現し、他社との差別化を図る強力な武器となるのです。
- この本は、企画のアイデア出しに悩んでいる人にもおすすめできますか?
-
もちろんおすすめです。
本書は、単なるアイデアの数を増やすための本ではありません。
企画の出発点となる「問い」の立て方を学ぶことで、アイデアの「質」そのものを高めることができます。
アイデアが散らばってまとまらないと感じている方こそ、思考を整理し、企画の核心を突くための指針を得られます。
- 本書はどのようなビジネスパーソンに特におすすめですか?
-
企画や商品開発、ブランディングに関わるすべての方におすすめできます。
特に、自分の企画に自信が持てない方や、チームの向かうべき方向性を一つにまとめたいリーダー、顧客の心に響くサービスを作りたいと考えている方に最適です。
本書の思考法は、あらゆるビジネスの土台となります。
- この本の効果的な読み方のコツはありますか?
-
ただ知識として読むだけでなく、ご自身のビジネスや企画の課題を一つ思い浮かべながら読み進めるのがおすすめです。
本書で紹介されている「問いを立てる」「リフレーミングする」といった思考法を、実際の課題に当てはめてみましょう。
アウトプットを意識することで、ノウハウがより深く身につきます。
まとめ
この記事では、『コンセプトの教科書』で解説されている、企画の軸を作るための思考法を要約しました。
本書の核心は、コンセプト作りをセンスに頼るのではなく、誰でも再現できる「技術」として体系的に学べる点にあります。
- センスではなく技術として学ぶコンセプトの作り方
- 「問い・リフレーミング・一行化」という思考のプロセス
- コンセプトを戦略の軸に据える「4C分析」
企画の軸がブレてしまうと悩んでいるなら、本書で解説されている「一行化」をご自身の企画で試してみてください。