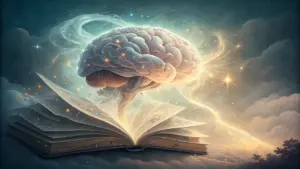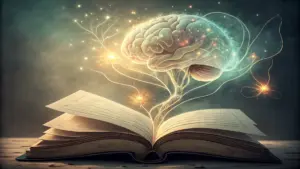『不安をなくさなければ』と必死に頑張りすぎて、かえって苦しくなっていませんか。
本書は、不安をゼロにしようと戦うのではなく、人生のパートナーとして受け入れるという新しい視点を提供します。
精神科医と当事者の両視点から書かれており、認知行動療法に基づいた精神論ではない具体的な対処法がわかります。
不安に振り回される毎日から抜け出したい…



本書が示す、不安との新しい付き合い方を紹介します
- 不安をなくすのではなく受け入れるという考え方
- 不安の正体を7つの感情に分解する方法
- 具体的な行動目標の立て方
- 周囲の人との関係を楽にするためのヒント
「不安症でも大丈夫」が示す不安との新しい付き合い
本書は、「不安をなくさなければ」という考えに縛られて苦しんでいる方へ、全く新しい視点を提供します。
それは、不安をゼロにしようと戦うのではなく、人生のパートナーとして受け入れるという考え方です。
この本を読むことで、不安との距離感が変わり、心が少し軽くなるのを感じられます。
本書の著者や、どのような方に向けた本なのかを見ていきましょう。
著者である原井宏明氏と松浦文香氏の紹介
本書は、精神科医と当事者という二人の著者によって書かれている点が大きな特徴です。
専門的な知見と当事者自身の経験が融合しているため、内容に深みと説得力があります。
一人は、精神科専門医であり日本認知・行動療法学会認定専門行動療法士でもある原井宏明氏です。
数多くの不安に関する著書を執筆しており、専門家としての豊富な知識と臨床経験に基づいた解説がされています。
もう一人の松浦文香氏は、10歳頃から強迫症を経験し、治療を経て回復したご自身の経験を持つ方です。
現在は自助グループの世話人としても活動しており、当事者の気持ちに寄り添った視点が本書に反映されています。
| 氏名 | 肩書き・経歴 | 特徴 |
|---|---|---|
| 原井 宏明 | 精神科専門医・指導医、原井クリニック院長 | 認知行動療法を専門とし、不安に関する多数の著書を執筆 |
| 松浦 文香 | 原井クリニック勤務、自助グループ「京橋強迫の会」世話人 | 10歳頃から強迫症を経験し、治療により回復した当事者 |
専門家と経験者、両方の視点から書かれているからこそ、理論だけでなく実践的な温かみのあるアドバイスが得られます。
本書の対象読者と当事者が読む上でのポイント
本書を手に取る上で最も大切な点は、主に不安症の方を支える家族向けに書かれているということです。
この点を理解せずに読み進めると、「少し思っていた内容と違う」と感じるかもしれません。
ソースにある口コミでも、「不安症の家族を持つ人向けの本でした」と書かれているように、精神科を受診しない本人に代わって家族が知識を得ることを目的の一つとしています。
当事者が読む場合は、この前提を頭に入れておくことが重要です。
じゃあ、不安で悩んでいる僕が読んでも意味がないのかな?



いえ、そんなことはありません。家族向けの視点だからこそ得られる新しい気づきがあるんです。
周りの人が自分の状態をどう理解し、どう接すれば助けやすいのかを知ることは、客観的に自分を見つめ直す良い機会になります。
不安をなくすのではなく受け入れるという発想の転換
本書が繰り返し伝える中心的なメッセージは、「不安をなくそうとすればするほど、不安は強くなる」という逆説的な仕組みです。
私たちは不安を感じると、それを悪いものだと考え、すぐに消し去ろうと焦ってしまいます。
しかし、その「なくそう」とする行為自体が不安に注意を向けさせ、かえって不安を増幅させてしまうのです。
本書では、不安は危険を知らせるための自然な感情であり、完全になくすことはできないと解説します。
不安な気持ちが出てくると、すぐに消さなきゃって焦ってしまうんです…



まずは「不安になっても大丈夫」と、自分に許可を出すところから始めてみましょう。
不安を無理に抑えつけるのではなく、「今、不安を感じているな」と認識して受け入れる姿勢が、結果として心の平穏につながります。
家族向けの視点から得られる客観的な自己理解
本書は家族向けに書かれているため、当事者のあなたにとっては、自分を客観的に見つめ直す鏡のような役割を果たします。
普段、自分が周りの人にどう見えているのか、どういう言動が相手を困らせているのかを知るきっかけになります。
例えば本書には、家族へのアドバイスとして「相手のネガティブな言葉には同調せず、できたことに目を向けて声をかける」という接し方が紹介されています。
この一文を読むだけでも、「自分の不安な言葉が、周りの人を疲れさせていたのかもしれない」といった新たな気づきが得られるでしょう。
僕が不安を話したとき、相手が困っているのはそういうことだったのかも…



周りの人にどうしてほしいか具体的に伝えやすくなりますし、相手の反応に一喜一憂することも減りますよ。
この視点は、一人で悩みを抱え込む状態から抜け出し、周囲と良好な関係を築きながら不安に対処していくための大切なヒントになります。
5分でわかる「不安症でも大丈夫」の要点3選
本書が提唱する、不安との新しい付き合い方の核心に迫ります。
重要なのは、不安を敵と見なして「なくそう」とするのではなく、人生の一部として受け入れ、行動を変えていくという発想の転換です。
この視点を理解することで、心が少し軽くなるはずです。
これから紹介する3つの要点は、漠然とした不安の正体を突き止め、具体的な行動へとつなげるための道しるべとなります。
要点1 不安の正体を7つの感情に分解
漠然とした「不安」という感情を、本書では7つの具体的な感情が混ざり合ったものだと定義しています。
仕事のミスを引きずってしまう時、それは単なる不安ではなく、「同じ失敗をするのではないか」という恐怖や、「なぜあんなことをしてしまったんだ」という後悔かもしれません。
このように自分の感情を細かく分析することで、漠然とした悩みの正体がはっきりします。
| 感情の種類 |
|---|
| 恐怖 |
| 嫌悪 |
| 焦燥感 |
| 後悔 |
| 憂うつ |
| 悲しみ(哀しみ) |
| 絶望・失望 |
漠然と「不安」としか感じられなかった…



感情に名前をつけることで、冷静に対処する第一歩になります
自分の感情を言葉にして客観視する習慣をつけることが、不安と上手に付き合うための基礎となります。
要点2 認知行動療法に基づく肯定的な目標設定
本書では、精神論ではなく自分でできる具体的な対処法として、認知行動療法の考え方に基づいた目標設定を提案しています。
多くの人がやりがちな「間食をしない」「失敗しない」といった否定的な目標は、かえって意識をその行動に縛り付けてしまうのです。
本書が推奨するのは、「野菜をたくさん食べる」「まずは1日15分だけ情報収集する」というような、肯定的で具体的な行動目標を立てることです。
| 否定的な目標(NG例) | 肯定的な目標(OK例) |
|---|---|
| 間食をしない | 3食きちんと野菜を食べる |
| 失敗しないように頑張る | 新しい仕事の情報を1日15分集める |
| 不安にならないようにする | 好きな音楽を聴く時間を作る |
失敗が怖くて、新しい挑戦ができない…



小さな成功体験を積み重ねることが、大きな自信につながりますよ
この方法は、不安で動けなくなっているあなたの背中をそっと押し、次の一歩を踏み出すきっかけを与えてくれます。
要点3 周囲との関係を楽にするためのヒント
本書は、不安症の当事者を支える家族や周囲の人に向けて書かれている点が大きな特徴です。
しかし、この視点は当事者であるあなたにとっても、多くの気づきを与えてくれます。
周りの人があなたの不安をどう受け止め、どう接するのが良いのかを知ることは、あなたが助けを求めやすくなることにつながるのです。
例えば、あなたがネガティブな言葉を口にした時、相手はそれに同調するのではなく、あなたができた行動に焦点を当てて声をかけるのが良いと本書は説いています。
| 家族や友人のNGな対応 | 家族や友人のOKな対応 |
|---|---|
| 「大丈夫だよ」と安易に励ます | 気持ちを受け止め、できたことを具体的に褒める |
| 不安の原因を問いただす | 行動の変化など肯定的な側面に焦点を当てる |
| ネガティブな言葉に同調する | 「買い物に行けたんだね」と行動自体を認める |
周りにどう思われているか、いつも不安になってしまう…



相手の立場を理解することで、円滑なコミュニケーションの糸口が見つかります
この本を通じて周囲の人の視点を知ることで、一人で悩みを抱え込まず、より良い人間関係を築くためのヒントが得られます。
読者のレビューからわかる本書の評価と感想
実際に本を読んだ人の声は、購入を検討する上でとても参考になります。
本書には様々な感想が寄せられていますが、特に当事者の方が読んだ際に感じやすいポイントと、そこから得られる学びについて解説します。
口コミからは、本書の対象読者に関する注意点と、それでも当事者が読む価値がある理由の両方が見えてきます。
「家族向けの本だった」という正直な口コミ
まず、本書を手に取った不安症の当事者の方が最初に感じやすいのは、「思っていた内容と少し違った」という点です。
これは、本書が主に不安症の方を支えるご家族や周囲の人に向けて書かれているという特徴があるためです。
実際に読んだ方のレビューからも、その点がよくわかります。
ちょっと思っていたのとは違ったかなぁ。
『「不安症」でもだいじょうぶ 不安にならない、なくすという目標は間違いです』というタイトルに引きつけられて、手に取ってみましたが、読んでびっくり。本書は不安症の人ではなく、不安症の家族を持つ人向けの本でした。不安症の本人が精神科を受診しないかぎり精神科医や(家族は)無力ということから、本なら何かの役に立つのではないかと作られたのが、この本なのだそうです。ちょっと勘違いからのスタートでしたが、少しだけレビューしたいと思います。
読んでいると、私自身は大の虫嫌い・大の病院嫌いなので、「極限性恐怖症」というものに当てはまっていると思いました。病院なんて悪いところを放置しすぎて怒られるくらい苦手です。基本はネットで症状を調べまくって、一番効く市販薬を飲んでおわり。なので昔から医者にガンガン要望を伝えられる人をカッコイイと思っていたのですが、あれはあれで「不安症」の一種だったのですね。
私は高いところも苦手で、子どもの頃からひとりだけハシゴや木に登れませんでした。美容院も苦手で髪を自分で切っちゃったり。本当に苦手やできないが多すぎて困っています。これもまた遺伝的なものが関係しているらしいです。
個人的に気になるのは、「強迫症」とまではいかないけれど、「鍵かけたっけな」「水とめたっけな」と気になって確認することが多いこと。手洗いの頻度や、お風呂に入るまでベッドで寝たくないなど結構スレスレのラインにいる自覚はあります。ただ、人間はストレスがないことにも不安を抱えてしまうらしく、色んなことを知っている人ほど不安になりやすいこともわかっています。
このように、タイトルから当事者向けの実践的なワークブックなどを想像していると、少し戸惑うかもしれません。
それでも当事者が読む価値のある理由
では、当事者であるあなたがこの本を読む意味はないのでしょうか。
答えは「いいえ」です。
視点を変えれば、客観的に自分と周囲の関係を見つめ直すためのヒントが詰まっています。
家族向けの記述を読むことで、「周りの人は自分の不安をこう感じているのかもしれない」「こうして欲しいと伝えれば、もっと楽になるかもしれない」と、コミュニケーションを円滑にする糸口を見つけることができます。
本書から学んだ対処法のひとつで参考にしたいのが、「不安にならない」という目標を持たないことです。これは「イライラしない」とか「落ち込まない」などの「しない」ことを目標にするのではなく、「〇〇する」という目標にするという方法です。
https://ameblo.jp/mylibrary1/entry-12860127784.html
たとえばダイエットするときに、「間食をしない」ではなく、「野菜をたくさん食べる」といった肯定文にするのです。「~したくない」の反対は、「~したい」なので、ポジティブに不安と付き合っていけたらと思いました。
最後に不安症の人が身近にいる人へのアドバイス。それはズバリ、相手のネガティブな言葉にはスルーする、です。「今日は買い物に行ったら、レジの人が感じ悪くて・・」と言われたら、後半の部分には触れず、「買い物に行ったんだ。調子悪くても外出できたんだね!」というように相手が変化したポジティブな部分にだけ触れるのがいいとのこと。これが共依存にもならないベストな方法らしいので、困っている人は試してみてください。
自分をどうにかできるのは、自分だけ。自分を変えられるのは、自分だけ。
結局はこれですね。
尚、不安度が重症な人は本書ではなく、病院を受診してください。
以上、『「不安症」でもだいじょうぶ』のレビューでした!
他者からの視点を知ることは、一人で悩みを抱え込まず、周囲のサポートを上手に受けながら回復を目指す上で大切なステップになります。
どんな悩みを持つ人におすすめか
ここまでの内容を踏まえ、本書が特にどのような悩みを持つ人におすすめできるかをまとめます。
何よりもまず、「不安をなくさなければ」と必死に頑張りすぎて、心身ともに疲れ果ててしまった人です。
不安を敵視するのをやめ、新しい付き合い方を見つけたいと考えているなら、本書はこれまでの考え方を大きく変えるきっかけを与えてくれます。
自分の不安を家族やパートナーにどう説明したらいいか分からない…



この本を一緒に読んだり、内容を共有したりすることで、あなたの状況を理解してもらう手助けになりますよ
| こんな人におすすめ |
|---|
| 不安を消そうとして、かえって苦しくなっている |
| 自分の考え方のクセを客観的に見直したい |
| 周囲の人に自分の状態を理解してもらえず悩んでいる |
| 具体的な行動目標の立て方がわからない |
| 不安症の家族やパートナーとの関わり方に困っている |
もしあなたがこれらの項目に当てはまるなら、本書はきっとあなたの心を少し軽くしてくれる一冊です。
日常生活で試せる不安を和らげる実践方法
本書では、不安と上手く付き合うための具体的な方法が紹介されています。
精神論で終わらせず、日々の生活の中で実践できる考え方のコツが満載です。
特に重要なのは、不安な気持ちそのものを変えようとするのではなく、自分の行動を変えることに集中する点です。
これから、あなたも今日から試せる4つの実践方法を解説します。
「〜しない」ではなく「〜する」で行動を変える習慣
つい「ミスをしないようにしよう」「不安にならないようにしよう」と考えていませんか。
このような「〜しない」という否定的な目標は、かえって意識を失敗や不安へ向けてしまいます。
目標を「〜する」という肯定的で具体的な行動に置き換えることが、状況を好転させる第一歩となります。
例えば、ダイエットで「間食をしない」と決めるより、「1日3食、野菜をたくさん食べる」と決める方が、前向きな行動につながります。
仕事でミスが怖いなら、「失敗しない」と考えるのではなく、「業務マニュアルを1日15分読む時間を作る」という行動目標を立てるのです。
この小さな成功体験の積み重ねが、不安を乗り越える自信を育てます。
「〜しない」と考えると、余計にそのことばかり考えてしまう…



そうなんです。だからこそ、やるべき行動に意識を向けることが大切ですよ
この習慣は、不安に思考を支配される状態から抜け出し、自分で自分の行動を選択しているという感覚を取り戻させてくれます。
自分の感情を言葉にして客観視するトレーニング
あなたが感じている「不安」は、実は一つの感情ではありません。
漠然とした不安の正体を探るには、自分の感情を具体的な言葉にして客観視するトレーニングが有効です。
本書では、不安を構成する7つの異なる感情が紹介されています。
例えば、仕事で上司に指摘された後のモヤモヤした気持ちは、ただの不安ではありません。
「また同じミスをするかもしれない」という恐怖や、「なぜあんなことをしてしまったんだ」という後悔が入り混じった感情です。
このように感情を分解すると、対処の糸口が見えてきます。
| 感情の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 恐怖 | これから起こるかもしれない悪いことへの恐れ |
| 嫌悪 | 受け入れがたい物事に対する強い拒否感 |
| 焦燥感 | じっとしていられない、落ち着かない気持ち |
| 後悔 | 過去の行動や選択を悔やむ気持ち |
| 憂うつ | 気分が沈み、何事にも興味が持てない状態 |
| 悲しみ | 失ったものや思い通りにならないことへの嘆き |
| 絶望・失望 | 希望を失い、どうにもならないと感じる気持ち |
ただ「不安」としか思っていなかったけど、分解すると分かりやすいかも



感情に名前をつけるだけで、冷静に対応しやすくなります
自分の感情を言葉にして認識することで、感情の渦に飲み込まれることなく、一歩引いた視点から自分を見つめ直せます。
パニック症や強迫症など症状別の考え方の紹介
本書は、特定の症状に悩む人にもヒントを与えてくれます。
ひとくちに不安症といっても、その現れ方は人それぞれです。
代表的なものとして、パニック症、社交不安症、強迫症などが挙げられ、それぞれのメカニズムについて解説されています。
例えば、「家の鍵を閉めたか何度も確認してしまう」のは強迫症の傾向かもしれません。
また、レビュー投稿者のように「病院が極端に苦手」というのは、特定の対象に強い恐怖を感じる極限性恐怖症に当てはまります。
本書を読むと、自分の悩みがどのタイプに近いのかを知り、なぜそのような思考や行動に陥るのかを理解できます。
| 症状の名称 | 主な特徴 |
|---|---|
| パニック症 | 突然の激しい動悸や息苦しさ(パニック発作)を繰り返す |
| 社交不安症 | 人前で注目される状況に強い恐怖や不安を感じる |
| 強迫症 | 無意味だとわかっていても特定の考えや行動を繰り返す |
| 極限性恐怖症 | 特定の対象や状況(高所、閉所、虫など)に過剰な恐怖を感じる |
自分の状態を客観的に知ることは、漠然とした不安を軽減し、適切な対処法を見つけるための重要な手がかりになります。
専門の病院やカウンセリングへ相談するタイミングの判断
セルフケアは大切ですが、自分一人で抱えきれない時もあります。
本書も、症状が重い場合は専門家への相談を推奨しています。
そのタイミングを見極める上で最も重要な基準は、不安によって日常生活に支障が出ているかどうかです。
具体的には、「不安で会社を休むことが増えた」「1週間以上、夜眠れない日が続いている」「人付き合いを避けるようになった」といった状態が続く場合は、受診を検討するサインです。
精神科や心療内科、カウンセリングルームなど、専門機関の扉を叩くことは決して特別なことではありません。
病院に行くのは少し怖いけど、我慢しすぎるのもよくないんですね



専門家に相談することは、自分を大切にするための正しい選択です
適切なタイミングで専門家の助けを借りることは、回復への確実な一歩であり、より早く心穏やかな日々を取り戻すための有効な手段です。
よくある質問(FAQ)
- この本で紹介されている「認知行動療法」とはどのようなものですか?
-
認知行動療法とは、自分の考え方のクセや物事の受け取り方に気づき、それを変えることで行動を変化させ、心の負担を軽くしていくアプローチです。
この本では、精神論ではなく具体的な行動目標を立てる方法として紹介されており、不安を感じやすい思考パターンから抜け出すための実践的なヒントが得られます。
- 心配性でまだ起きてもいないことを考えてしまいます。この本の心配性の治し方は役立ちますか?
-
この本は、心配性を完全になくすことを目指すのではなく、心配や不安と上手に関わっていく方法を提案します。
「不安は危険を知らせる自然な感情」と捉え、無理に消そうとしない考え方が中心です。
心配な気持ちを受け入れつつ、具体的な行動に意識を向けることで、過剰な心配に振り回されにくくなるでしょう。
- 家族が不安症で悩んでいます。この本から学べる家族の接し方を教えてください。
-
この本は、主に不安症の方を支えるご家族に向けて書かれています。
重要なのは、本人の不安な言葉に同調しすぎず、できた行動や肯定的な側面に目を向けて声をかけることです。
相手の不安に巻き込まれず、健全な関係を保ちながらサポートするための具体的な接し方を解説しています。
- この本を読めば、病院に行かなくても不安障害は治りますか?
-
いいえ、この本はあくまで不安との付き合い方を学ぶためのものであり、医学的な治療の代わりにはなりません。
もし不安によって仕事や学校に行けない、眠れないなど日常生活に大きな支障が出ている場合は、セルフケアで解決しようとせず、心療内科や精神科といった専門の病院を受診することが重要です。
- 突然の動悸や息苦しさに襲われることがあります。パニック発作への対処法は書かれていますか?
-
本書では、パニック症を含めた様々な不安症のメカニズムについて解説しています。
特定の症状への対処法を学ぶ前に、なぜそうした反応が起きるのかを理解することは、冷静に対応するための第一歩です。
本書には、自分でできる不安への対処法が具体的に書かれているため、発作への向き合い方のヒントも見つかります。
- 仕事のミスが怖くて新しい業務に挑戦できません。この本は社交不安症で悩む人にも有効ですか?
-
はい、社交不安症などで仕事に悩む方にも多くの気づきを与えてくれます。
本書は、失敗を恐れて動けなくなっている状況に対し、「失敗しない」という目標ではなく「まず15分だけ関連情報を集める」といった肯定的で小さな行動目標を立てることを推奨します。
この考え方は、新しい挑戦へのハードルを下げ、一歩を踏み出すきっかけになります。
まとめ
この記事では、書籍『不安症でも大丈夫』の要点を解説しました。
本書が提案する最も大切な考え方は、不安をゼロにしようと戦うのではなく、人生のパートナーとして受け入れるという新しい視点です。
- 不安を敵ではなくパートナーと捉える考え方
- 漠然とした不安を7つの感情に分解する方法
- 「〜する」で考える肯定的な行動目標の立て方
- 周囲の視点から自分を客観的に見つめ直す機会
不安を無理に消そうとして苦しんでいるなら、この本は新しい付き合い方を見つけるきっかけになります。
まずは本書を手に取り、心を軽くする第一歩を踏み出しましょう。