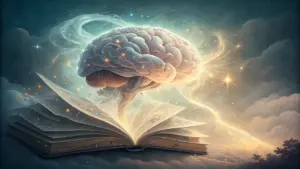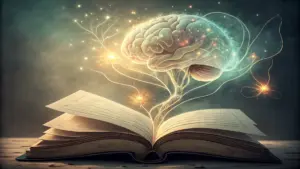チームの人間関係、特に年上の部下とのコミュニケーションに悩んでいませんか。
デール・カーネギーの名著『人を動かす』には、小手先の技術ではなく、時代を超えて通用する人間関係の普遍的な原理原則が書かれています。
この記事では、あなたのリーダーシップの土台となる本書の30原則を7分で読めるように要約し、明日から職場で実践できる具体的な行動まで解説します。
年上の部下にどう接すれば、チームがうまく回るんだろう?



本書の原則を学べば、相手を尊重しながら信頼を得る具体的な方法が分かりますよ
- なぜ『人を動かす』が80年以上も読み継がれるのか
- 人間関係の悩みを解決する30原則の要点
- リーダーが明日から職場で実践できる3つの行動
なぜ今も『人を動かす』がリーダーの必読書なのか
デール・カーネギーの不朽の名著『人を動かす』が、なぜ発行から80年以上経った今もなお、リーダーを目指すすべての人にとって必読書とされ続けるのでしょうか。
その理由は、この本が単なるコミュニケーション術を解説したものではなく、時代や文化を超えて通用する人間関係の普遍的な原理原則を解き明かしているからです。
この本に書かれている知恵は、現代のビジネスシーンであなたが直面するであろう、あらゆる対人関係の悩みを解決する糸口となります。
80年以上読み継がれる世界的ベストセラー
本書は、1936年にアメリカで初版が発行されて以来、今日まで絶えることなく世界中の人々に読まれ続けている、まさに自己啓発書の原点です。
これまでに世界累計で1500万部以上、日本国内だけでも430万部以上という驚異的な発行部数を記録しています。
2011年にはアメリカのTime誌が選ぶ「最も影響力のある100冊の本」で19位にランクインするなど、その価値は公的にも高く評価されているのです。
そんなに昔の本が、今の時代にも役立つのかな?



時代が変わっても変わらない「人間の本質」を突いているからこそ、今も価値があるのです。
これほど長い年月、多くの人々に支持され続けている事実こそが、本書で語られる原則が普遍的であり、かつ実践的であることの何よりの証明です。
ウォーレン・バフェットも学んだ人間関係の原理原則
世界で最も成功した投資家として知られるウォーレン・バフェット氏が、自身の成功の基盤の一つとして本書の教えを挙げていることは有名です。
彼は、20歳の時に『人を動かす』の原型となった「デール・カーネギーの演説コース」を受講し、その卒業証書を今でも自身のオフィスに飾っています。
バフェット氏は、この講座で学んだ人との付き合い方が、その後の人生を大きく変えたと公言しているのです。
世界のトップを走り続ける人物が大切にしている原則だからこそ、私たちビジネスパーソンにとっても学ぶ価値は計り知れません。
心理学や偉人の逸話から生まれた実践的な内容
本書で紹介される原則は、机上の空論ではありません。
著者のデール・カーネギーが15年という長い歳月を費やし、徹底的なリサーチを重ねて体系化したものです。
その過程では、エイブラハム・リンカーンをはじめとする歴史上の偉人たちの伝記を入念に研究し、当時の心理学の学術論文を読み込み、各界で成功を収めた人々への直接の聞き取り調査も行われました。
このように、数多くの具体的なエピソードに裏打ちされているため、一つひとつの原則に強い説得力があります。
理論だけじゃなくて、具体的な話が多いと分かりやすいな。



豊富なエピソードがあるからこそ、原則がすんなりと頭に入ってくるのが本書の魅力です。
理論と実例が巧みに織り交ぜられている構成によって、読者は内容を深く理解し、自身の状況に置き換えて考えやすくなっています。
対人関係の悩みを解決する普遍的なヒントの数々
『人を動かす』がリーダーに推奨される最大の理由は、部下や上司、顧客、さらには家族との関係といった、あらゆる人間関係に応用できる「原理原則」が示されている点にあります。
例えば、チームメンバーのやる気を引き出したい時、意見が対立する相手を説得したい時、職場の雰囲気を良くしたい時など、あなたが直面するであろう様々な課題に対して、具体的な行動指針を見つけ出すことが可能です。
この本は、あなたのリーダーシップの土台を築き、人生のあらゆる場面における人間関係をより豊かにするための、知恵の宝庫と言えます。
【一覧】『人を動かす』の根幹をなす4つのパート
『人を動かす』は、大きく4つのパートに分かれており、それぞれが人間関係を築く上で欠かせない要素を解説しています。
これらは小手先の技術ではなく、相手の心を開き、信頼を得るための原理原則です。
これらを理解するだけで、あなたのコミュニケーションは大きく変わります。
| パート | 概要 | こんなリーダーにおすすめ |
|---|---|---|
| 人を動かす三原則 | 人間関係の土台となる基本的な心構え | まずは何から手をつければ良いか分からない方 |
| 人に好かれる六原則 | 周囲から好意を持たれ、円滑な関係を築くための行動 | チームに一体感を生み出したい方 |
| 人を説得する十二原則 | 相手を傷つけずに自分の意見を受け入れてもらうための技術 | 会議や交渉で意見を通す必要がある方 |
| 人を変える九原則 | 相手の行動を良い方向へ導き、成長を促すための指導法 | 部下の育成やマネジメントに悩んでいる方 |
これらの原則は、それぞれ独立していながらも密接に関連しています。
まずは最初の「人を動かす三原則」から意識することが、周囲との関係性を変える第一歩になるでしょう。
人を動かす三原則
人間関係におけるすべての基本であり、相手と良好な関係を築くための大前提となるのが「人を動かす三原則」です。
人を動かしたいと思うなら、まず自分の行動や考え方から変える必要があります。
相手を尊重し、理解しようと努める姿勢がなければ、どんな言葉も相手の心には響きません。
つい相手の悪い点を指摘してしまうのですが、どうすれば良いですか?



まずは相手を批判しないと決めるだけで、あなたの言葉は大きく変わりますよ。
これらの原則は、相手の「自己重要感」を満たすことに繋がります。
人は誰でも自分を価値ある存在だと認められたい欲求を持っています。
その欲求を満たすことが、相手の心を開く鍵となるのです。
| 原則 | 要点 |
|---|---|
| 1. 批判も非難もせず、苦情も言わない | 批判は相手の防御姿勢を引き出し、恨みしか生まない |
| 2. 率直で、誠実な評価を与える | 人が最も渇望している「認められたい」という欲求を満たす |
| 3. 相手の立場に立ち、強い欲求を起こさせる | 相手が自ら「やりたい」と思うように導く |
人に好かれる六原則
次に紹介するのは、あなたの周りに自然と人が集まってくるようになる「人に好かれる六原則」です。
これは、相手に対する誠実な関心が、いかに人間関係を豊かにするかを教えてくれます。
特別な才能は必要なく、今日から誰でも実践できる行動ばかりです。
笑顔で挨拶する、相手の名前を覚えるといった行動は、一見すると些細なことに思えるかもしれません。
しかし、世界一の投資家ウォーレン・バフェットも若い頃にデール・カーネギーの講座でこれらの重要性を学び、その教えを大切にしています。
| 原則 | 要点 |
|---|---|
| 1. 誠実な関心を寄せる | 相手に関心を持つことで、相手からも関心を持たれる |
| 2. 笑顔を忘れない | 笑顔はコストのかからない最高のコミュニケーションツール |
| 3. 相手の名前を覚える | 名前はその人にとって最も心地よい響きを持つ言葉 |
| 4. 聞き手にまわる | 相手に気持ちよく話をさせることが信頼に繋がる |
| 5. 相手の関心事を見抜く | 相手が関心を持っている話題を話す |
| 6. 心から褒める | 相手の自己重要感を満たし、好意を得る |
これらの原則を意識的に行うことで、職場の雰囲気は明るくなり、チームの心理的安全性も高まります。
その結果、メンバーはあなたを信頼し、活発な意見交換が生まれるようになります。
人を説得する十二原則
自分の意見を通したい時、相手を言い負かそうとしていませんか。
「人を説得する十二原則」は、議論で相手に勝つのではなく、相手が喜んであなたの意見に協力してくれるようになるための原則です。
議論に勝っても相手の好意は得られません。
会議で意見が対立したとき、どうすれば相手を納得させられますか?



議論で勝つのではなく、相手に「自分で思いついた」と感じさせることが重要です。
この原則の中心にあるのは、相手の意見や感情を尊重する姿勢です。
たとえ相手が間違っていても、真正面からそれを指摘するのではなく、穏やかな態度で対話を始めることが、相手を説得するための最短距離となります。
| 原則 | 要点 |
|---|---|
| 1. 議論を避ける | 議論に勝っても人の心は変えられない |
| 2. 相手の誤りを指摘しない | 相手の自尊心を傷つけ、反発を招くだけ |
| 3. 自分の誤りを認める | 素直に誤りを認めると、相手も寛容になる |
| 4. 穏やかに話す | 優しい態度は怒りや反発を溶かす |
| 5. 相手が「イエス」と答える問題を選ぶ | 小さな同意を積み重ねて、最終的な同意を得る |
| 6. 相手にしゃべらせる | 相手に話させることで、問題点や本音が見えてくる |
| 7. 相手に思いつかせる | 人は自分で思いついたアイデアを大切にする |
| 8. 相手の身になる | 相手の視点で物事を考えることが理解の第一歩 |
| 9. 相手の考えに同情を寄せる | 相手の感情に寄り添うことで、心を開かせる |
| 10. 人の美しい心情に呼びかける | 人は誰しも自分を正直で公正な人間だと思いたい |
| 11. 演出を考える | 事実をより効果的に見せる工夫をする |
| 12. 対抗意識を刺激する | 優劣を競う気持ちは、人の意欲を引き出す |
人を変える九原則
リーダーとして最も難しい仕事の一つが、部下やメンバーの行動を変え、成長を促すことです。
「人を変える九原則」は、相手を傷つけずに誤りを正し、やる気を引き出すための具体的な方法を示します。
命令や批判では、人は決してついてきません。
これらの原則は、特に年上の部下や経験豊富なメンバーと仕事をする上で大きな効果を発揮します。
一方的に指示するのではなく意見を求めることで、相手のプライドと経験を尊重する姿勢が伝わり、主体的な協力を引き出せます。
| 原則 | 要点 |
|---|---|
| 1. まず褒める | 良い点から話すことで、相手は注意を受け入れやすくなる |
| 2. 遠回しに注意する | 直接的な批判を避け、相手に気づかせる |
| 3. 自分の誤りを話してから、相手に注意する | 自分の失敗談が、相手の反感を和らげる |
| 4. 命令せず、意見を求める | 相手に考える機会を与え、主体性を育てる |
| 5. 相手の顔を立てる | 人前で恥をかかせず、相手の自尊心を守る |
| 6. わずかなことでも心から褒める | 具体的な賞賛は、相手の成長の糧となる |
| 7. 期待をかける | 良い評価を与え、その評価に応えたいと思わせる |
| 8. 激励して自信を持たせる | 欠点を直すのは簡単だと伝え、やる気を引き出す |
| 9. 喜んで協力させる | 相手の利益を考え、協力したいと思わせる |
相手の成長を心から願う気持ちが根底にあれば、あなたの言葉は相手の心に届き、ポジティブな行動の変化に繋がります。
これらの原則は、信頼されるリーダーになるための必修科目と言えるでしょう。
リーダーの悩みを解決する3つの実践法
『人を動かす』に書かれている原則は、あなたのチームが抱える問題を解決する鍵となります。
重要なのは小手先のテクニックではなく、相手に誠実な関心を寄せ、一人の人間として尊重する姿勢です。
本書で紹介されている数々の原則の中から、明日からすぐにあなたの職場で実践できる3つの行動を紹介します。
批判せず相手を理解する姿勢で信頼を得る
チームメンバー、特に経験豊富な年上の部下に対して、つい誤りを指摘したくなる場面は少なくありません。
しかし、そこで相手を批判することは、最も避けるべき行動です。
『人を動かす』の根幹をなす三原則の第一は「批判も非難もせず、苦情も言わない」ことです。
人は誰でも、自分が正しいと思っています。
たとえ間違いを犯したとしても、それを正面から指摘されると反発心が生まれ、心を閉ざしてしまいます。
大切なのは、相手の行動を責める前に「なぜそうなったのか」を理解しようと努める姿勢です。
相手の立場や考えに耳を傾けることで、あなたの言葉はただの「指摘」から「対話」へと変わり、深い信頼関係を築く第一歩となります。
年上の部下にどう接すれば良いか分からず、気まずいです…



まずは相手の話を最後まで真剣に聞くことから始めてみましょう
相手を正そうとするのではなく、理解しようとするあなたの姿勢が、チームメンバーの心を開き、円滑な人間関係の土台を築きます。
命令ではなく意見を求める会話で主体性を引き出す
メンバーが指示待ちで、なかなか自発的に動いてくれないと悩んでいませんか。
その状況は、あなたの言葉のかけ方一つで変えることが可能です。
『人を動かす』で紹介されている「人を変える九原則」の一つに、「命令せず、意見を求める」というものがあります。
「このタスクを明日までにやってください」と指示する代わりに、「この課題を解決するために、何か良いアイデアはありますか?」と問いかけてみてください。
この問いかけは、相手に考える機会を与え、当事者意識を芽生えさせます。
特にキャリアのあるメンバーに対しては、彼らの知識や経験を尊重することになり、プライドを保ちながらチームに貢献する喜びを感じてもらえるでしょう。
意見を求めても、良いアイデアが出てこなかったらどうしよう…



大切なのは答えではなく、一緒に考えるというプロセスそのものです
一方的な指示を双方向のコミュニケーションに変えるだけで、メンバーは受け身の姿勢から抜け出し、チームの目標達成に向けて主体的に動き始めます。
笑顔と名前を覚える行動でチームの雰囲気作り
リーダーの役割は、業務の進捗管理だけではありません。
チームが最高のパフォーマンスを発揮できるような、心理的に安全な雰囲気を作ることも求められます。
そのために有効なのが、「人に好かれる六原則」で示されている「笑顔を忘れない」「相手の名前を覚える」といった、ごく基本的な行動です。
日々の挨拶で「〇〇さん、おはようございます」と、相手の名前を呼んで笑顔を向ける。
これだけの行動でも、相手に「あなたは大切な存在です」というメッセージが伝わります。
このような小さなコミュニケーションの積み重ねが、職場の心理的安全性を高め、メンバーが安心して発言できる風通しの良い環境を生み出します。
そんな当たり前のことで、本当にチームの雰囲気が変わるのでしょうか?



はい、当たり前のことを意識して毎日続けることに大きな価値があります
リーダーであるあなたの前向きな態度は、必ずチーム全体に伝わります。
明日からの挨拶に一工夫加えることが、活気あるチーム作りの確かな一歩となるのです。
デール・カーネギーの名著『人を動かす』の基本情報
『人を動かす』というタイトルを知っていても、著者やこの本が生まれた背景まで理解している人は少ないです。
この本がなぜ80年以上もの間、世界中の人々に影響を与え続けているのか、その普遍的な価値の源泉となる基本情報から解説します。
| 項目 | 新訳版 | 旧訳版 | 漫画版 | オーディオブック |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 現代的な言葉遣いで読みやすい | 原書の格調高い雰囲気を味わえる | ストーリー形式で要点を掴める | ながら聞きでインプットできる |
| おすすめの人 | 初めて読む人、若手ビジネスパーソン | 長年読み継がれてきた名訳に触れたい人 | 活字が苦手な人、短時間で学びたい人 | 通勤時間や家事をしながら学びたい人 |
| 発行元(代表例) | 創元社 | 創元社 | 日本文芸社 | Audible |
自分の読書スタイルや学習目的に合わせて、最適な形式を選ぶことが理解への近道となります。
著者デール・カーネギーの人物像
デール・カーネギーは、作家でありながら、もともとは話し方や人間関係に関する講座の講師でした。
彼の教えは、机上の空論ではなく、多くの受講生と向き合う中で生まれた実践的な知見の集大成です。
カーネギーは1912年からYMCAで弁論術の講座を受け持ち始め、受講生たちの悩みに応える形で教材を自ら作り上げました。
偉人たちの伝記や心理学の研究、著名人への聞き取り調査などを通じて、15年という歳月をかけて本書の内容を体系化しました。
どんな経験からこの本を書いたんだろう?



自身の講座での経験と15年にも及ぶ人間性の研究成果が詰まっています
受講生一人ひとりの悩みに真摯に向き合ったカーネギーの情熱が、時代や文化を超えて通用する人間関係の原則を生み出したのです。
書籍の概要と発行までの歴史
『人を動かす』(原題: How to Win Friends and Influence People)は、1936年にアメリカで出版された、自己啓発書というジャンルの元祖ともいえる一冊です。
単なるテクニックではなく、人間性の深い理解に基づいたコミュニケーションの原則を説いています。
初版発行以来、日本国内で430万部、世界累計では1500万部以上を発行する世界的ベストセラーであり、今なお多くのビジネスパーソンにとっての必読書とされています。
ウォーレン・バフェットのような著名な経営者にも影響を与えてきました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原題 | How to Win Friends and Influence People |
| 著者 | デール・カーネギー |
| ジャンル | 自己啓発書 |
| 初版発行 | 1936年10月(アメリカ) |
| 日本語版発行元 | 創元社 |
| 発行部数(世界累計) | 1500万部以上 |
2013年にはアメリカ議会図書館から「アメリカ史において影響力のある本」の1冊に選ばれるなど、その歴史的価値は公にも認められています。
新訳版と旧訳版の主な違い
現在、創元社から出版されている『人を動かす』には、新訳版と旧訳版の2種類があります。
両者の最も大きな違いは、現代の読者に合わせた言葉遣いになっているかどうかという点です。
新訳版は、より現代的で平易な日本語に翻訳されており、特に若い世代や初めて本書を手に取る人にとって、内容がすんなりと頭に入ってきやすい構成になっています。
一方、旧訳版は格調高い文語調の表現が多く、長年読み継がれてきた翻訳の歴史や重みを感じさせます。
初めて読むなら、どっちを選べばいいの?



まずは現代的で分かりやすい言葉で書かれた新訳版から読むことをおすすめします
内容の核となる原則に違いはありませんので、まずは読みやすい新訳版で全体像を掴み、さらに深く味わいたくなったら旧訳版を読んでみるのが良い選択です。
隙間時間で学べる漫画版やオーディオブック
『人を動かす』の学び方は、活字を読むだけではありません。
忙しいあなたのライフスタイルに合わせて、学習効率を高めるための選択肢が用意されています。
特に人気なのが、要点をストーリー仕立てで学べる漫画版や、通勤時間などを有効活用できるオーディオブックです。
漫画版は、登場人物の具体的な行動を通して原則をイメージしやすく、活字が苦手な人でも楽しみながら学べます。
オーディオブックは、プロのナレーターによる朗読を耳からインプットするため、繰り返し聞くことで内容が記憶に定着しやすいのがメリットです。
| 形式 | メリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 漫画版 | 要点が視覚的にわかる、短時間で読める | 活字が苦手な人、要点だけ知りたい人 |
| オーディオブック | 通勤中など「ながら聞き」できる、繰り返し聞きやすい | 忙しくて読書時間が取れない人、聴覚でインプットしたい人 |
プロジェクトで多忙な毎日を送るあなたにとって、こうした多様な学習方法は、無理なく人間関係の原則を身につけるための心強い味方になります。
よくある質問(FAQ)
- 『人を動かす』の原則を実践しても、すぐに効果が出ないときはどうすれば良いですか?
-
結果がすぐに出なくても焦る必要はありません。
デール・カーネギーが示す原則は、人間関係を一夜で変える魔法ではなく、日々の積み重ねで信頼を築くための心構えです。
まずは「笑顔を忘れない」など、自分にできる一つのことから意識して続けてみてください。
小さな成功体験を重ねることで、あなたのコミュニケーションは着実に良い方向へ向かいます。
- 部下を褒めるのが苦手です。わざとらしく聞こえてしまわないか心配です。
-
「褒める」ことに難しさを感じるなら、無理に大げさな言葉を選ぶ必要はありません。
大切なのは、相手の行動や成果に対して、具体的かつ誠実に評価を伝えることです。
例えば「昨日の資料、データが整理されていて分かりやすかったです」のように事実を伝えるだけでも、相手の自己重要感を満たし、良い関係を築く一歩になります。
- 「議論を避ける」とは、自分の意見を主張してはいけないということでしょうか?
-
そうではありません。
「議論を避ける」というのは、相手を言い負かすための感情的な対立をやめるという意味です。
仕事において自分の意見を伝えることは重要ですが、相手の考えを尊重し、穏やかな話し方を心がけることが大切です。
目的は議論に勝つことではなく、相手に気持ちよく協力してもらい、共に良い結論を出すことにあります。
- 新訳版や漫画、オーディオブックがありますが、どれから始めるのがおすすめですか?
-
初めて『人を動かす』を読む方には、現代的な言葉で書かれ、内容を理解しやすい新訳版から始めることをおすすめします。
活字を読むのが苦手な方や、あらすじを素早く知りたい場合は漫画版が良いでしょう。
また、通勤時間などを有効活用したいビジネスパーソンには、耳から学べるオーディオブックが適しています。
- チャットやメールなど、文章のコミュニケーションでもこの本の原則は使えますか?
-
はい、十分に活用できます。
文章でのやり取りは表情が見えない分、より意識することが効果的です。
例えば、相手の名前を文頭に入れる、感謝の言葉を添えるといった行動は、画面の向こうの相手への敬意を示します。
特に「批判しない」という原則は、意図しない誤解を避ける上で非常に重要です。
- この本はリーダーシップやマネジメント以外にも役立ちますか?
-
もちろんです。
『人を動かす』の原則は、上司や部下との関係だけでなく、お客様との信頼を築く営業活動や、家族・友人とのプライベートな人間関係にも広く応用できます。
相手の立場になって考え、誠実な関心を寄せるといった考え方は、あらゆるコミュニケーションの土台となるからです。
まとめ
この記事では、デール・カーネギーの名著『人を動かす』に記された、時代を超えて通用する人間関係の原理原則を解説しました。
本書で最も重要なのは、小手先の技術ではなく、相手を批判せず、まず理解しようと努める誠実な姿勢を持つことです。
- 人を動かすための普遍的な原理原則
- 批判せずに相手を尊重する基本姿勢
- 命令ではなく意見を求めるコミュニケーション
この本に書かれている多くの原則を一度に実践するのは大変です。
まずは明日、チームの誰か一人に笑顔で名前を呼んで挨拶をすることから始めてみましょう。