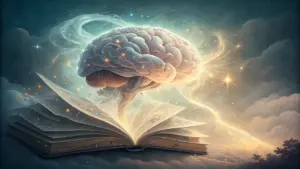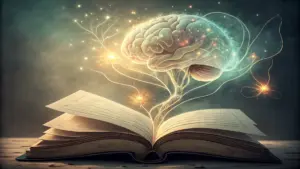毎日がむしゃらに働いているのに成果が出ず、徒労感を抱えていませんか。
その働き方を根本から変える鍵は、作業量ではなく「本当に解くべき問題」を見極めることにあります。
この記事では、多くのビジネスパーソンに支持される安宅和人氏の名著『イシューから始めよ』の要点を、誰にでもわかるように5分で解説します。
本書が示す「やるべきことを100分の1にする」思考法の本質を学び、最小の労力で最大の成果を生み出す働き方を手に入れましょう。
がむしゃらに働くことから、どうすれば抜け出せるんだろう?



本書の思考法で、あなたの仕事は「量」から「質」へと変わります。
- 成果が出ない働き方「犬の道」の正体
- 仕事の価値を決める「イシュー」の本質
- イシューから始める問題解決の具体的な4ステップ
- 2024年発売の改訂版と旧版の明確な違い
『イシューから始めよ』が示す生産性の高い働き方
毎日がむしゃらに働いているのに、なかなか成果に繋がらない…。
もしあなたがそんな徒労感を抱えているなら、その働き方を根本から変える一冊が、安宅和人氏の『イシューから始めよ』です。
この本が示す生産性の高い働き方の本質は、本当に価値のある仕事は、解くべき問題を見極めることから始まるという考え方にあります。
この章では、なぜ多くの人が成果の出ない働き方に陥ってしまうのか、そして仕事の価値を根底から変える思考法について解説します。
成果が出ない働き方の共通点
本書では、成果が出ない働き方を「犬の道」と表現しています。
これは、目の前のタスクをとにかくがむしゃらにこなすことで、いつか成果につながると信じてしまう働き方のことです。
例えば、100個のタスクをこなしても、そのほとんどが本質的でなければ、生み出される価値はゼロに近いという事態に陥ります。
がむしゃらに働くことがダメなのはなぜ?



労働時間とアウトプットの価値は比例しないからです。
多くの人がこの「努力すれば報われる」という思い込みによって、貴重な時間を浪費してしまっています。
仕事の価値を決める「イシュー度」と「解の質」
仕事の価値は「イシュー度」と「解の質」という2つの軸で決まります。
「イシュー度」とは「今本当に答えを出すべき問題か」という論点の質、「解の質」とは「そのイシューに対してどれだけ明確に答えを出せているか」という解決策の質を指します。
多くの人は「解の質」を高めることに注力しますが、本書では「イシュー度」の低い問題は、どれだけ質の高い答えを出しても価値がゼロになると指摘しています。
まずはイシュー度を上げることが最優先です。
| 解の質が低い | 解の質が高い | |
|---|---|---|
| イシュー度が高い | 本来目指すべき領域 | 最も価値が高い仕事 |
| イシュー度が低い | 努力が無駄になる | 自己満足で終わる仕事 |
バリューのある仕事とは、この2つの軸の両方が高い状態を目指すことなのです。
やるべきことを100分の1にする思考の本質
本書が示す思考の本質は、取り組むべきイシュー、つまり本質的な問いを徹底的に見極めることで、無駄な作業をそぎ落とすことにあります。
本当に解くべき問題が見つかれば、やるべきことは自然と絞られます。
その結果、検討すべき選択肢が100分の1にまで減り、限られたリソースを最も価値のある一点に集中投下できます。
具体的にはどうやってイシューを見極めるの?



本書で紹介される「仮説ドリブン」や「アウトプットドリブン」といった手法を用います。
このアプローチによって、仕事の生産性は向上し、最小の労力で最大の成果を生み出すことが可能になります。
全ての土台となる「イシュー」と陥りがちな「犬の道」
仕事の価値は、労働時間の長さや作業量で決まるわけではありません。
本書が示す最も重要な考え方は、「何をやるか」というイシューの見極めこそが、生産性の高い仕事の出発点であるということです。
ここでは、本書の根幹をなす「イシュー」の定義と、多くの人が無意識に陥ってしまう生産性の低い働き方である「犬の道」について解説します。
この2つの概念を理解することが、価値のある仕事を生み出すための第一歩です。
単なる課題ではない「イシュー」の本当の意味
本書における「イシュー」とは、単なる課題やテーマではありません。
それは「今、この局面で本当に白黒つけるべき、本質的な問い」を指します。
例えば、「自社製品の売上が低い」というのは課題にすぎません。
これを「売上低迷の最大の要因は、チャネル戦略と価格戦略のどちらにあるのか?」というように、答えを出すべき問いに変換したものがイシューです。
このようにイシューを特定することで、取り組むべきことが100分の1に絞り込まれるケースも少なくありません。
「課題」と「イシュー」の違いは理解できたけど、良いイシューってどうやって見つけるの?



答えを出すことでその後のアクションが大きく変わる、分岐点になるような問いを探すのがポイントです。
イシューを見極めることで、思考の解像度が上がり、次に何をすべきかが明確になります。
がむしゃらな努力が無駄になる「犬の道」の罠
多くの人が成果を出せない原因として、本書では「犬の道」という働き方を挙げています。
「犬の道」とは、解くべき問題、つまりイシューを見極めずに、がむしゃらに作業量をこなして解決しようとする働き方のことです。
「とにかく情報を集めよう」「やれることから手当たり次第に着手しよう」といった思考は、犬の道への入り口といえます。
この働き方では、たとえ労働時間を2倍にしても、生み出される価値はほとんど変わらないのです。
まさに自分のことだ…。どうすればこの罠から抜け出せるんだろう?



まずは「仕事を始める前に立ち止まり、本当に解くべき問題は何かを考える」習慣をつけましょう。
労働時間と成果が比例しない根本原因は、この「犬の道」にあります。
価値のある仕事をするためには、まずこの罠から抜け出す必要があるのです。
質の高いイシューを見極めるための3つの条件
では、どうすれば質の高いイシューを見極めることができるのでしょうか。
本書では、良いイシューには3つの共通した条件があると解説しています。
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 本質的な選択肢である | その答えによって、その後の行動に大きな影響が出る |
| 深い仮説がある | 常識を覆すような、新しい発見や構造が見える可能性がある |
| 答えを出せる | 自分のリソースやスキルで、実際に答えを導き出せる範囲の問題である |
これら3つの条件を念頭に置いて問いを立てることで、取り組む価値のある本質的なイシューを見つけ出せます。
イシュー特定のための情報収集術
質の高いイシューを特定するためには情報収集が不可欠ですが、やみくもに情報を集めるのは「犬の道」そのものです。
イシュー特定のための情報収集は、あくまで仮説を立てるために行います。
本書では、一次情報(現場のヒアリングや自分の分析など)に触れることの重要性を説いています。
例えば、その分野の専門家数人に話を聞くだけで、問題の構造や論点の8割は把握できることもあります。
情報収集だけでいつも時間がかかりすぎてしまう…。



情報を「網羅的に集める」のではなく、「仮説を検証するために必要な情報だけを狙って取りに行く」意識が大切です。
情報の量ではなく、目的に焦点を当てた質の高い情報収集が、イシュー特定への近道となります。
仮説ドリブンで思考の効率を上げる
質の高いイシューを特定できたら、次に行うのが仮説を立てることです。
仮説ドリブンとは、「イシューを特定したら、まずスタンスをとって仮の答えを立てる」という思考法を指します。
最初に仮説を立てることで、証明すべきことが明確になり、集めるべき情報や必要な分析だけを実行できるようになります。
例えば「売上低迷の要因は価格戦略にある」という仮説を立てれば、価格に関するデータだけを集めて検証すればよく、無駄な分析を徹底的に排除可能です。
最初に答えの仮説を立て、そこから逆算して思考を進めることで、最短距離で結論にたどり着けます。
イシュードリブンを実現する4つのステップ
イシュードリブン、つまり「イシューを見極めてから答えを出す」という思考法を実践するための具体的なプロセスを解説します。
本書では、このプロセスを4つのステップに分けており、順番通りに進めることが質の高いアウトプットを生む鍵になります。
これから解説する4つのステップは、コンサルティングファームなどで行われる知的生産の現場で磨かれた、実践的な方法論です。
一つひとつ見ていきましょう。
ステップ1 イシューの見極め
最初のステップは、取り組むべき「イシュー」を特定することです。
ここでいうイシューとは、単なる「課題」ではなく、「今、本当に白黒をつけるべき本質的な問い」を指します。
例えば、「自社の売上が低い」という課題ではなく、「売上低迷の最大の要因は、新規顧客の獲得数と既存顧客のリピート率のどちらにあるのか?」のように、答えを出すべき問いとして設定します。
この見極めの精度が、後続のすべての作業の質を決定づけます。
何でもかんでも問題にするのではなく、解くべき問いを絞り込むのですね



その通りです。質の高いイシューは、その後の行動を大きく変える力を持っています
まずは時間をかけてでも、本当に解く価値のあるイシューは何かを考え抜くことが、生産性向上の第一歩となるのです。
ステップ2 ストーリーラインの構築と分解
イシューを見極めたら、次はその問いにどう答えるかの「ストーリーライン」を構築します。
ストーリーラインとは、最終的な結論に至るまでの論理的な構造や話の流れのことです。
具体的には、特定したイシューをいくつかの「サブイシュー」に分解します。
例えば、「売上低迷の要因」という大きなイシューを、「顧客層別の売上動向は?」「製品別の利益率は?」「競合の動向は?」といった答えを出すべき小さな問いに分解していく作業を行います。
| 大イシュー | サブイシュー1 | サブイシュー2 | サブイシュー3 |
|---|---|---|---|
| 新規事業Aの成功可能性 | 市場規模と成長性は十分か | 競合優位性を築けるか | 収益モデルは成立するか |
このようにイシューを分解してストーリーラインを組み立てることで、考えるべき論点が明確になり、チーム内での目線合わせも容易になります。
ステップ3 分析イメージの絵コンテ化
ストーリーラインが完成したら、次はそのストーリーを検証するための分析イメージを「絵コンテ」に落とし込みます。
絵コンテとは、最終的なアウトプットとして示すグラフや図の具体的なイメージを、実際の分析に着手する前に手書きなどで描くことです。
例えば、「顧客層別の売上動向」を検証する場合、横軸に「年代」、縦軸に「売上金額」を取った棒グラフを描いてみます。
このとき、どのような分析結果が出れば仮説が証明されるのかまでを具体的にイメージするのがポイントです。
分析を始める前に、もう答えのイメージを描いてしまうのですね



はい、それによって本当に必要なデータと分析作業だけを見極め、無駄な作業をなくせます
実際に手と頭を動かして絵コンテを描くことで、必要なデータの種類や分析の軸が明確になり、分析作業の手戻りを防ぎます。
ステップ4 アウトプットの作成とメッセージの伝達
最後のステップは、絵コンテに沿って実際の分析を行い、最終的なアウトプットを作成することです。
ここでのポイントは、分析結果をただ羅列するのではなく、相手に伝えるべき「メッセージ」を磨き上げることにあります。
分析によって得られた事実から、「だから何が言えるのか」「次に何をすべきか」という示唆を抽出します。
プレゼンテーション資料を作成する際は、1つのチャートにつき1つのメッセージを原則とし、聞き手が直感的に理解できるよう工夫を凝らします。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 目的の明確化 | 誰に、何を理解してもらい、どう動いてほしいのかを定義する |
| 論理の構造化 | 主張と根拠を明確に分け、聞き手が納得できる流れを作る |
| 表現の簡潔化 | 専門用語を避け、一目で理解できる言葉と図解を用いる |
どんなに優れた分析も、相手に伝わらなければ価値を生みません。
聞き手の立場に立ち、行動に繋がるメッセージを伝えることが、イシュードリブンの最終ゴールです。
2025年発売の改訂版と旧版の違い
2010年の発売から多くのビジネスパーソンに愛読されてきた本書が、2024年9月に待望の改訂版として生まれ変わりました。
時代の変化に合わせて内容が更新されており、今から本書を手に取るなら、その違いを理解しておくことが重要です。
| 項目 | イシューからはじめよ[改訂版] | イシューからはじめよ(旧版) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年9月22日 | 2010年11月24日 |
| ページ数 | 272ページ | 248ページ |
| 価格(税込) | 2,200円 | 1,760円 |
| 追加コンテンツ | 新規コラム2本、改訂版あとがき | なし |
| 内容の更新 | 事例の差し替え、全文の推敲 | なし |
これから知的生産の思考法を学ぶのであれば、最新の知見が盛り込まれた改訂版を選ぶことをおすすめします。
改訂版で追加された新規コラム
改訂版の大きな特徴は、新たに書き下ろされた2つのコラムが収録されている点です。
旧版の普遍的な思考法はそのままに、現代のビジネスパーソンが直面する課題に合わせた視点が加えられています。
具体的には、「課題解決の2つの型」と「なぜ今『イシューからはじめよ』なのか」というテーマのコラムが追加され、ページ数も旧版から24ページ増量しました。
| 新規コラム | 内容の概要 |
|---|---|
| 課題解決の2つの型 | 問題解決におけるアプローチの型を整理し、より実践的に使いこなすための視点 |
| なぜ今『イシューからはじめよ』なのか | AIの台頭や社会の変化が激しい現代において、本書の思考法が持つ意味と重要性 |
追加コラムでは、具体的にどんなことが学べるのでしょうか?



時代の変化に対応した、より実践的な課題解決のアプローチが学べます。
これらのコラムを読むことで、本書で解説される思考法を、今の自分の仕事にどう活かせばよいのか、より深く理解できるようになります。
差し替えられた事例と全文の推敲
改訂版はコラムの追加だけでなく、書籍全体にわたって内容が丁寧にアップデートされていることも見逃せません。
より今の時代に合った内容で、思考法を学べるように工夫されています。
特に、時代の変化を感じさせる一部の事例が現代的なものに差し替えられているため、初めて読む方でもスムーズに内容を自分ごととして捉えることが可能です。
また、著者自身による全文の推敲によって、メッセージがより明確に伝わるように磨き上げられています。
思考の本質はそのままに、さらに洗練された一冊へと進化しました。
なぜ今『イシューからはじめよ』を読むべきなのか
改訂版のコラムタイトルにもなっているこの問いは、情報過多で変化の速い現代を生きる私たちにとって、極めて重要性を増しています。
答えのない問題に向き合う機会が増えたからです。
AIの進化や働き方の多様化により、約15年前の初版発行時とは比較にならないほど、私たち一人ひとりに「本当に解くべき問い」を見極める力が求められるようになりました。
ただ目の前のタスクをこなすだけでは価値を生み出しにくい時代だからこそ、本書が説く本質的な思考法が、あなたのキャリアを切り拓くための強力な武器になります。
購入するなら旧版か新版か
もしあなたがこれから『イシューから始めよ』を読もうと考えているなら、間違いなく2024年9月に発売された改訂版をおすすめします。
価格は旧版より440円高くなりますが、追加された2つの新規コラムや、現代に合わせて更新された内容を考えれば、その投資価値は十分にあります。
旧版で解説されている思考の本質は色褪せませんが、今の時代に合わせた視点や事例と共に学べるメリットは大きいです。
もう旧版を持っているのですが、買い直すべきですか?



旧版で学べる本質は変わりませんが、最新の視点を得たいなら改訂版です。
すでに旧版を読んで内容を理解している方は、書店で追加コラム部分を読んでみるのも良いでしょう。
しかし、初めて読む方や、改めて深く学び直したいと考えている方は、最新の知見が詰まった改訂版を手に取ることで、より大きな学びを得られます。
書籍の基本情報と著者・安宅和人氏の紹介
本書『イシューから始めよ』を深く理解するためには、その内容だけでなく、著者である安宅和人氏がどのような人物なのかを知ることが欠かせません。
著者の稀有な経歴こそが、本書で語られる思考法の説得力と普遍性を裏付けているのです。
ここでは、著者と書籍の基本情報、そして本書を手軽に学ぶ方法を紹介します。
| 学習方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 書籍(原作) | 思考法を体系的・網羅的に学べる | 読み通すのに時間がかかる、内容が難解な部分も | じっくり時間をかけて本質を理解したい人 |
| 漫画版 | 図や物語で直感的に理解できる | 原作の細かなニュアンスは省略される | 活字が苦手な人、まず全体像を掴みたい人 |
| Audible版 | 通勤中など「ながら時間」で学べる | 図やグラフなど視覚情報が伝わりにくい | 忙しくて本を読む時間がない人 |
著者のバックグラウンドを知ることで、なぜこの本がこれほど多くのビジネスパーソンに支持されるのかが見えてきます。
あなたに合った方法で、まずは本書のエッセンスに触れてみてください。
著者・安宅和人氏の経歴
本書の著者である安宅和人(あたか かずと)氏は、脳科学者、経営コンサルタント、そして事業会社の戦略責任者という、三つの異なる分野でトップレベルの実績を持つ人物です。
東京大学大学院で修士号を取得後、イェール大学で脳神経科学の博士号を取得。
その後、世界的な経営コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニーで11年間コンサルタントとして活躍しました。
2008年からはヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)で最高戦略責任者(CSO)などを歴任し、現在はシニアストラテジストを務める傍ら、慶應義塾大学環境情報学部で教授としても教鞭を執っています。
すごい経歴の人だけど、なぜこの思考法を生み出せたんだろう?



科学的知見とビジネスの最前線での経験が、この普遍的な思考法の土台なのです。
脳科学の深い知見と、グローバルなビジネス現場での実践経験が掛け合わさっている点こそ、安宅氏の提唱する思考法の信頼性の源泉です。
『イシューから始めよ』のあらすじ
本書は、「生産性を高めるためには、がむしゃらに働くのではなく、まず『今、本当に答えを出すべき問題=イシュー』を見極めよ」と説く一冊です。
多くの人が陥りがちな、労働時間とアウトプットの質が比例しない働き方を「犬の道」と表現し、そこから脱却するための思考法を体系的に解説します。
仕事の価値は「イシュー度(解くべき問題の質)」と「解の質(答えの深さ)」の二軸で決まるという考え方に基づき、取り組むべきことを100分の1に絞り込むための具体的なステップを示してくれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 著者 | 安宅和人 |
| 出版社 | 英治出版 |
| 発売日(旧版) | 2010年11月24日 |
| 発売日(改訂版) | 2024年9月22日 |
| ページ数(旧版) | 248ページ |
| ページ数(改訂版) | 272ページ |
| 特徴 | 全ての知的生産活動に応用できる思考のフレームワーク |
この本は単なるスキルやテクニックを教えるのではなく、仕事に対する根本的な向き合い方そのものを変革させる力を持っています。
読者からのレビューや感想
『イシューから始めよ』は、多くの読者から絶賛される一方で、「内容が難しい」という声も聞かれる書籍です。
購入を検討する際は、自分にとって有益かどうかを判断するために、両方の意見を知っておくことが役立ちます。
「もっと早く出会いたかった」という声があるように、特に若手のビジネスパーソンにとっては、キャリアの早い段階で読むことでその後の仕事の進め方が大きく変わる一冊となるでしょう。
| 評価 | レビュー・感想の要点 |
|---|---|
| 良い評価 | 「仕事の進め方のOSが書き換わった」「無駄な作業が減り、本質的な業務に集中できるようになった」「すべての社会人、特に若手は必読の書」 |
| 悪い評価 | 「コンサル業界の専門用語が多く、内容が難しい」「具体例が少なく、自分の仕事にどう活かせばいいか分かりにくい」「当たり前のことが書いてあると感じた」 |
本書は、課題設定や仮説構築といった上流工程に携わる機会の多いプロジェクトリーダーやマネージャー層にとって、特に実践的な示唆を与えてくれます。
Audibleや漫画で手軽に学ぶ方法
「原作を読む時間がないけれど、内容は知りたい」という忙しい方には、書籍以外の方法で本書のエッセンスを学ぶ選択肢があります。
特にAudible(オーディブル)版と漫画版は、効率的にインプットしたい人に適した媒体です。
活字が苦手な方でも、ストーリー仕立ての漫画であれば、本書の難解なコンセプトを直感的に理解することが可能です。
- Audible版: プロのナレーターによる朗読で、通勤中や家事をしながら「聴く読書」ができます。何度も繰り返し聞くことで、思考法が自然と身につきます。
- 漫画版(まんがでわかる イシューからはじめよ): アパレルメーカーを舞台にしたストーリーを通じて、主人公が「イシュー」を見極め、問題を解決していく過程を追体験できます。
本を読む時間がなくても、これなら自分にもできそう!



まずは漫画やAudibleで概要を掴み、興味を持った部分を原作で深掘りするのがおすすめです。
自分のライフスタイルや学習の好みに合わせて最適な方法を選ぶことで、この重要な思考法を無理なく自分のものにしていきましょう。
よくある質問(FAQ)
- 『イシューから始めよ』の思考法は、コンサルタントでなくても役立ちますか?
-
はい、もちろんです。
本書で紹介される思考法は、特定の職業に限定されるものではありません。
企画職、エンジニア、研究者など、知的生産に関わるすべてのビジネスパーソンにとって、問題解決の質を上げる強力な武器になります。
まず「本当に解くべき課題は何か?」という課題設定から始める習慣が身につきます。
- 本書を読むと「意味ない」仕事が減ると聞きましたが、具体的にはどういうことですか?
-
本書でいう「意味ない」仕事とは、答えを出しても価値が生まれない「イシュー度の低い」仕事のことです。
この本を読むと、仕事に取り掛かる前に「これは今、本当に白黒つけるべき問題か?」と自問するようになります。
その結果、やらなくてもよい作業が明確になり、本当にバリューのある仕事に時間と労力を集中できるのです。
- 「仮説ドリブン」という考え方が難しいと感じます。新人でも実践できるコツはありますか?
-
最初から完璧な仮説を立てる必要はありません。
まずは「おそらく、こうではないか?」という大胆な仮の答えを、情報が不十分な段階で立ててみることから始めます。
例えば「この問題の根本原因はAのはずだ」と一旦決めてしまうのです。
そうすることで、何を調べるべきかが明確になり、思考の効率が格段に上がります。
- 改訂版と旧版では、内容に大きな違いはありますか?
-
はい、重要な違いがあります。
2024年発売の改訂版では、AI時代における本書の重要性を説く新規コラムが2本追加されました。
さらに、一部の事例が現代的なものに差し替えられ、文章全体がより分かりやすく洗練されています。
思考法の本質は不変ですが、今から学ぶのであれば、最新の視点が加わった新版を強くおすすめします。
- この本で紹介されているフレームワークを、実際の仕事でどう使えばいいですか?
-
例えばプロジェクトの企画を任された場合、まず「この企画で解決すべき最も重要なビジネス課題は何か?」というイシューを設定します。
次に、その課題を解決するための論理的なストーリーラインを組み立て、提案資料のグラフなどのイメージを絵コンテとして描くのです。
このフレームワークに沿って進めることで、手戻りがなく質の高いアウトプットを生み出せます。
- Audibleや漫画版でも、本書の要約として十分に学べますか?
-
はい、本書のエッセンスを効率的に学ぶ上で非常に有効です。
Audible(オーディブル)は移動時間に、漫画版は活字が苦手な方でも直感的に思考法を理解できます。
ただし、著者である安宅和人氏の言葉の深みや細かなニュアンスを完全に掴むには、原作の書籍が一番です。
まずはこれらの媒体で全体像を掴み、さらに深く学びたくなった際に原作を手に取るのがおすすめです。
まとめ
この記事では、安宅和人氏の名著『イシューから始めよ』が示す、生産性を劇的に高める思考法を解説しました。
最も重要なのは、がむしゃらに作業量をこなすのではなく、まず「本当に解くべき問題は何か」を見極めることです。
- 仕事の価値を作業量ではなく「イシュー度」で捉える考え方
- 多くの人が陥る、成果に繋がらない働き方「犬の道」の罠
- イシューを見極めてから答えを出すための具体的な4ステップ
もしあなたが日々の業務に追われ、徒労感を抱えているなら、まずは本書の思考法に触れてみてください。
書籍はもちろん、漫画やAudibleといった手軽な方法から、あなたの働き方を変える第一歩を踏み出しましょう。