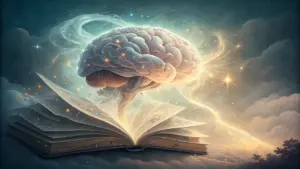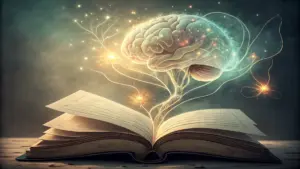上司に企画を提案しても「もっと考えて」と突き返されてしまう経験はありませんか。
その悩みは、本書『解像度を上げる』で解説されている思考の道具を手に入れることで解決できます。
この記事では、スタートアップ支援の専門家である馬田隆明氏の著書を要約し、曖昧な思考を明確にするための4つの視点と思考法をわかりやすく解説します。
どうすれば、もっと深く考えて説得力のある企画を作れるんだろう…



本書で解説されている思考のフレームワークが、あなたの悩みを解決する道しるべとなります。
- 『解像度を上げる』で解説されている4つの視点
- 曖昧な思考を晴らすための具体的な行動法
- 本書を読むことで得られる仕事上の変化
企画が通らない悩みを解決する思考の道具
上司に企画を提案しても「もっと考えて」と突き返されてしまう、そんな経験はありませんか。
その悩みは、思考の深さや広さが足りていないことが原因です。
本書『解像度を上げる』は、曖昧な考えを明確な言葉にするための「思考の道具」が詰まった一冊です。
この本を手に取ることで、あなたの企画は見違えるほど説得力を持ち始めます。
「もっと考えて」というフィードバックからの脱却
上司からの「もっと考えて」というフィードバックは、決してあなたへの人格否定ではありません。
これは、物事の捉え方や説明における思考の「解像度」が低いことへの指摘なのです。
例えば、企画のメリットだけを語り、想定されるリスクや他の選択肢との比較が十分にできていないと、相手はGOサインを出しにくいものです。
解像度を上げることで、相手が抱くであろう疑問や懸念に先回りして答えを提示できるようになります。
「もっと考えて」って、どうすればいいのか分からない…



まずは、なぜ自分の考えが浅いと思われてしまうのか、その原因を知ることから始めましょう。
本書は、その曖昧なフィードバックを具体的な行動に移すための、頼もしい道しるべとなります。
なぜ、あなたの考えは浅いと思われてしまうのか
考えが浅いと思われてしまう根本的な原因は、物事を一つの側面からしか捉えられていない点にあります。
自分では深く考えたつもりでも、「競合他社との詳細な比較ができない」「長期的な視点での目標を語れない」といった状態では、相手に物足りない印象を与えてしまいます。
以下のチェックリストで、ご自身の思考の解像度を確認してみましょう。
| チェック項目 | 説明 |
|---|---|
| 簡潔な説明 | 重要な点を明確かつ簡潔に話せるか |
| 自信のある言動 | 自分の考えを自信を持って言い切れるか |
| 独自の視点 | 他の人が気づかない独自の洞察があるか |
| 多角的な説明 | 様々な角度から物事を説明できるか |
| 競合比較 | 競合他社との違いを詳細に比較できるか |
| 長期的な視点 | 短期および長期的な数値目標を説明できるか |
これらの項目に自信を持って「はい」と答えられない場合、それが「浅い」という評価につながっているのです。
曖昧な思考を晴らすための行動法
曖昧な思考を晴らすために最も重要なのは、「情報収集→思考→行動」というサイクルを素早く何度も繰り返すことです。
完璧な分析を終えるまで行動できない、という考え方は一度手放しましょう。
本書では、まず行動してみて、そこから得られた事実や反応をもとに思考を深めていくという、実践的な学びの方法が紹介されています。
完璧な分析ができないと、行動してはいけないと思っていました。



大丈夫です。まずは小さな一歩から始めて、思考の解像度を少しずつ上げていきましょう。
小さな成功と失敗を繰り返すプロセスこそが、思考を鍛え、解像度を高める一番の近道なのです。
『解像度を上げる』の要点、思考の輪郭を捉える4つの視点
本書で解説されている思考法の中核をなすのが「4つの視点」です。
ビジネスで成果を出すためには、「課題」と「解決策」という2つの要素の解像度を上げることが欠かせません。
そのために、物事を「深さ」「広さ」「構造」「時間」という視点で多角的に捉え直す方法が示されています。
| 視点 | 概要 | 思考を深める問いかけの例 |
|---|---|---|
| 深さ | 物事の根本的な原因や本質を探る | 「なぜ、そうなっているのか?」 |
| 広さ | 多様な視点や選択肢を検討する | 「他の見方や可能性はないか?」 |
| 構造 | 情報の全体像と要素間の関係を把握する | 「全体はどのような要素で構成されているか?」 |
| 時間 | 過去の経緯を踏まえ、未来の変化を予測する | 「これまでどう変化し、これからどうなるか?」 |
これらの視点を意識的に使い分けることで、これまでぼんやりとしていた思考の輪郭がはっきりと見えてきます。
結果として、より的確な意思決定ができるようになるのです。
視点1「深さ」なぜを繰り返して本質を探る
「深さ」の視点とは、物事の根本的な原因や本質を突き詰めるための思考法を指します。
表面的な事象に惑わされず、その背後にある本当の原因を探り当てる力が身につきます。
具体的な方法として、本書では「なぜそうなっているのか?」という問いを最低でも5回、できれば7回ほど繰り返すことが推奨されています。
例えば、企画が通らない理由を「説明が分かりにくいから」で終わらせず、「なぜ分かりにくいのか?」「なぜその情報を盛り込んだのか?」と掘り下げていくことで、真の課題にたどり着けるのです。
なぜ?と聞かれても、すぐ答えに詰まってしまう…



最初は浅くても大丈夫です。繰り返すうちに本質が見えてきますよ
この「なぜ」を繰り返す思考の習慣は、対症療法的な解決策ではなく、問題の根源にアプローチするための第一歩となります。
視点2「広さ」前提を疑い多角的に捉える
「広さ」の視点とは、自分の思い込みや固定観念から離れ、多様な角度から物事を捉える視点のことです。
一つの見方に固執せず、視野を広げることで、これまで気づかなかった選択肢やリスクを発見できます。
例えば、新しい企画を考える際に、自分の部署の都合だけでなく、「営業担当者の視点」「開発者の視点」「そして何より顧客の視点」というように、最低でも3つ以上の異なる立場から物事を考える習慣が重要です。
そうすることで、より多くの人が納得できる、実行可能性の高い計画へと磨き上げられます。
自分のアイデアが一番良いと思ってしまうことが多いかも…



あえて反対の立場から考えてみると、新しい発見があります
この視点を持つことで、自分の思考の癖に気づき、より客観的でバランスの取れた判断を下せるようになります。
視点3「構造」情報を整理して全体像を掴む
「構造」の視点とは、情報や物事の構成要素と、それらの関係性を明らかにするための思考法を指します。
複雑に絡み合った問題を分解し、整理することで、全体像を正確に把握するのに役立ちます。
上司から「全体像が見えない」と指摘される場合、この視点が欠けていることが多いです。
本書では、情報を図解したり、付箋を使って要素を分類したりして視覚化する方法が紹介されています。
3C分析などのビジネスフレームワークを活用するのも、情報を整理し、思考の抜け漏れを防ぐのに有効な手段です。
情報が多すぎて、どう整理すればいいか分からない…



まずは紙に書き出して、グループ分けしてみるのがおすすめです
この視点を身につければ、複雑な問題もシンプルに整理でき、誰にでも分かりやすく論理的な説明が可能になります。
視点4「時間」過去から学び未来を予測する
「時間」の視点とは、物事を静的な「点」ではなく、過去から未来へと続く動的な「線」として捉える視点です。
過去の経緯や変化のパターンを分析し、将来起こりうることを予測する力が養われます。
ただ現状を分析するだけでなく、過去のデータを分析して変化の傾向を掴み、将来起こりうる複数のシナリオを準備することが大切です。
あなたの企画が短期的にどのような結果を生み、長期的には市場にどんな影響を与えるのかまで語れるようになれば、提案の説得力は大きく高まります。
目の前のことで手一杯で、未来のことまで考えられていない…



過去の成功例や失敗例を振り返るだけでも、未来のヒントになります
時間軸を意識することで、より長期的で持続可能な視点を持った意思決定が可能になり、変化の激しい時代でも的確な舵取りができるようになります。
課題と解決策、2つの解像度を高める重要性
本書では、「課題」と「解決策」という2つの要素の解像度を高めることが繰り返し強調されています。
多くのビジネスパーソンは、表面的な問題(症状)を「課題」だと誤解し、性急に解決策へ飛びついてしまう傾向があります。
これは、熱が出たという症状に対して、原因(インフルエンザなのか食あたりなのか)を特定せずに、ただ解熱剤を処方するようなものです。
これでは根本的な解決には至りません。
真に解像度を上げるためには、まず「課題」そのものを深く、広く、構造的に、時間軸で捉え直す必要があります。
| 解像度の状態 | 課題の捉え方 | 解決策の質 |
|---|---|---|
| 低い | 表面的な症状を問題と誤認 | 対症療法的で効果が薄い |
| 高い | 根本的な原因を特定 | 本質的で持続的な効果がある |
正しい課題設定こそが、質の高い解決策を生み出すための最も重要なステップです。
本書で紹介されている4つの視点は、そのための強力な思考の道具となります。
読者の評判と本書から得られる変化
本書を手に取ることで、あなたの思考と行動にどのような良い変化が生まれるのか。
ここが最も大切なポイントです。
実際に読んだ方からは、物事の捉え方が変わり、日々の仕事の進め方に良い影響が出たという声が数多く届いています。
| 変化するポイント | 読書前の状態(Before) | 読書後の状態(After) |
|---|---|---|
| 思考の質 | 思いつきで断片的に考える | 体系立てて多角的に考察 |
| 企画の説得力 | 上司から「なぜ?」と何度も問われる | 背景や根拠を論理的に説明できる |
| 課題発見能力 | 目の前の現象に振り回される | 問題の根本原因を特定できる |
| 行動の効率 | 手戻りが多く時間がかかる | 最短で的確な解決策を実行できる |
このように本書は、単に知識を得るだけでなく、仕事の成果に直結する実践的なスキルを身につけるための羅針盤となる一冊です。
読書メーターでの評価や感想の傾向
読書メーターとは、日本最大級の読書管理・共有ウェブサービスです。
多くの読書家が利用するこの場所で、本書がどう受け止められているかを見ていきましょう。
2024年5月時点で登録者数は1,800人を超え、295件もの感想・レビューが投稿されており、ビジネス書の中でも高い関心を集めていることが分かります。
| 評価のポイント | 肯定的な感想の傾向 | 注意点として挙げられる感想 |
|---|---|---|
| 内容の分かりやすさ | 図解が多く直感的に理解しやすい | やや学術的な表現も含まれる |
| 実践性 | すぐに業務で試せる行動法が豊富 | 全てを実践するには意識的な努力が必要 |
| 思考法 | 自分の思考の癖に気づかされる | 他の思考法に関する書籍と共通する部分もある |
| 網羅性 | 思考のプロセスが体系的にまとめられている | ページ数が多く読むのに時間がかかる |
本当に自分でも実践できる内容なのかな…?



はい、本書はスライドが元になっているため図解が多く、具体的な行動法が示されているため、すぐに試せるという感想が多いですよ。
全体として、曖昧な思考を整理するための「型」を学び、具体的な行動に移したいと考えるビジネスパーソンから強く支持されている傾向にあります。
実践で使える思考フレームワークの習得
本書の核心は、「深さ・広さ・構造・時間」という4つの視点で構成された、再現性の高い思考フレームワークを習得できる点にあります。
これは机上の空論ではなく、例えば「なぜ」を最低でも5回繰り返して本質を探る、情報を整理して関係性を図解するなど、日々の業務ですぐに使える具体的な行動にまで落とし込まれています。
このフレームワークを意識するだけで、思考の質は大きく変わるのです。
| 視点 | 思考を整理するための行動例 |
|---|---|
| 深さ | 課題に対して「なぜ?」を繰り返し、根本原因を探る |
| 広さ | 顧客や競合など、自分以外の立場からも物事を考える |
| 構造 | 要素を付箋に書き出し、グループ分けして関係性を可視化 |
| 時間 | 過去のデータから変化の傾向を掴み、未来を予測する |
色々なフレームワークを覚えるのは大変そう…



まずは4つの視点を意識するだけで大丈夫です。意識することで、自然と情報を見る目が変わってきます。
この4つの視点を繰り返し使うことで、思考のクセが修正されていきます。
結果として、物事を冷静に、そして多角的に捉える力が自然と身につくのです。
説得力ある企画立案への道筋
上司や取引先に企画が通らない大きな原因は、提案の「解像度」が低く、相手に意図や全体像が伝わっていないことにあります。
本書は、その解像度を上げるための具体的な道筋を示してくれます。
4つの視点を用いて企画の解像度を上げることで、上司からの「もっと具体的に考えて」というフィードバックを、納得と称賛に変えることができます。
企画を立てる際に、以下のチェックリストを活用してみてください。
| 視点 | 企画のチェック項目 |
|---|---|
| 深さ | 解決しようとしている課題の本質は何か |
| 広さ | 顧客、競合、自社の他部署にとってどのような意味を持つか |
| 構造 | 企画の全体像と各要素のつながりは明確か |
| 時間 | 短期的、長期的にどのような成果と影響が予測されるか |
上司を納得させるには、どう説明すればいいんだろう?



課題の構造を図解し、なぜこの解決策が最適なのかを4つの視点から説明することで、論理的な説得力が生まれます。
これまで曖昧だった企画の輪郭がはっきりとし、誰が聞いても「なるほど」と頷けるような、骨太なロジックを組み立てられるようになります。
課題解決のスピードと正確さの向上
解像度が上がると、問題の本質を素早く見抜けるようになるため、日々の課題解決のスピードと正確さが大きく向上します。
目の前で起きている表面的な事象に振り回されなくなります。
最短ルートで根本原因にアプローチできるため、これまで発生していた手戻りや無駄な検討作業が大幅に減少するのです。
| 業務プロセス | 解像度が低い状態(Before) | 解像度が高い状態(After) |
|---|---|---|
| 情報収集 | 手当たり次第に情報を集めて混乱 | 必要な情報を見極めて効率的に収集 |
| 原因分析 | 見当違いの原因を追って時間を浪費 | データや事実に基づき根本原因を特定 |
| 解決策の立案 | 対処療法的な策に終始する | 本質的な解決につながる打ち手を考案 |
| 意思決定 | 判断に迷い、行動が遅れる | 根拠を持って迅速に判断を下す |
いつも目の前のことで手一杯になってしまう…



時間軸の視点を持つことで、長期的な視点から優先順位を判断できるようになりますよ。
日々の小さなトラブルから大きなプロジェクトの課題まで、あらゆる場面で的確な判断を下せるようになります。
その結果、仕事全体の生産性が高まり、より創造的な業務に時間を使えるようになるのです。
著者・馬田隆明と『解像度を上げる』の基本情報
本書『解像度を上げる』を深く理解するためには、著者がどのような人物で、書籍がどのような背景で生まれたのかを知ることが重要です。
著者である馬田隆明氏の経歴や書籍の概要、そして手軽に読める電子書籍やオーディオブックでの入手方法について紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 著者 | 馬田隆明 |
| 価格 | 2,420円(税込) |
| 発売日 | 2022/11/17 |
| 発行 | 英治出版 |
| ページ数 | 352ページ |
| ISBN | 9784862763181 |
これらの基本情報を押さえることで、本書がなぜ多くのビジネスパーソンに支持されているのか、その理由の一端が見えてきます。
著者・馬田隆明氏の経歴と他の著作
本書の著者である馬田隆明氏は、東京大学FoundXのディレクターとして、スタートアップ支援と起業家教育に従事する専門家です。
トロント大学を卒業後、日本マイクロソフトでの勤務を経て、2016年から東京大学に所属し、数多くの起業家を育ててきました。
その実践的な知見が本書にも凝縮されています。
どんな人が書いた本なのか気になります



スタートアップ支援の最前線にいる方の、現場で役立つ知見が詰まっていますよ
| 著作名 |
|---|
| 逆説のスタートアップ思考 |
| 成功する起業家は居場所を選ぶ |
| 未来を実装する |
スタートアップ支援の豊富な経験を持つ馬田氏だからこそ書ける、再現性の高い思考法が本書の大きな魅力です。
書籍のあらすじと目次構成
『解像度を上げる』は、曖昧な思考を明晰にするための思考法と行動法を解説したビジネス書です。
「深さ」「広さ」「構造」「時間」という4つの視点を使い、物事を捉え直す方法が中心テーマになっています。
もともとは2021年にオンライン上で公開され、最も閲覧されたスライドが元になっており、352ページにわたってその内容が深掘りされています。
具体的にどんなことが書かれているんだろう?



課題と解決策、2つの解像度を高める方法が全8章で体系的に学べます
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 第1章 | 解像度を上げる4つの視点 |
| 第2章 | あなたの今の解像度を診断しよう |
| 第3章 | 型を意識しながら、まず行動からはじめて、粘り強く取り組み続ける |
| 第4章 | 課題の解像度を上げる―「深さ」 |
| 第5章 | 課題の解像度を上げる―「広さ」「構造」「時間」 |
| 第6章 | 解決策の解像度を上げる―「広さ」「構造」「時間」 |
| 第7章 | 実験して検証する |
| 第8章 | 未来の解像度を上げる |
この構成に沿って読み進めることで、解像度を上げるための思考法を段階的に身につけられるようになっています。
KindleやAudibleでの入手方法
本書は紙の書籍だけでなく、電子書籍やオーディオブックでも手軽に入手できます。
特に忙しいビジネスパーソンには、通勤中や移動中に学べるAudibleがおすすめです。
紙の書籍は定価2,420円(税込)で販売されていますが、電子書籍版であれば少し安く購入できる場合もあります。
本を読む時間がないけど、内容は知りたいな…



耳で学べるAudibleなら、スキマ時間を有効活用できますよ
| 形式 | 特徴 |
|---|---|
| 単行本 | 書き込みながらじっくり読める |
| Kindle版 | スマートフォンやタブレットでいつでも読める |
| Audible版 | 移動中や作業中に耳で聴いて学べる |
自分のライフスタイルに合わせて最適な方法を選び、思考法を身につけていきましょう。
よくある質問(FAQ)
- この本で解説されている思考法は、どのような職種の人におすすめですか?
-
企画職やマーケターだけでなく、課題解決に取り組むすべてのビジネスパーソンにおすすめです。
本書の思考法は、物事の本質を捉え、的確な打ち手を考えるための普遍的な方法論を紹介しています。
そのため、エンジニアや営業職、管理職の方々が日々の業務で直面する問題にも応用することが可能です。
- 本を読む時間がないのですが、要点を効率的に知る方法はありますか?
-
はい、あります。
本書はもともとオンラインで公開されたスライドが元になっていますので、まずはそちらで概要を掴むのも一つの方法です。
また、移動中や作業中に耳で学べるAudible(オーディオブック)版も提供されています。
自分の生活スタイルに合わせて、スキマ時間を活用してインプットすることをおすすめします。
- 本書で紹介されている「4つの視点」を、日常生活で実践する簡単な方法はありますか?
-
まずは「深さ」の視点を意識することから始めてみてください。
例えば、ニュース記事を読んだときに「なぜこの出来事が起きたのだろう?」と自分に問いかけてみる習慣をつけるのが簡単な方法です。
一つの答えで満足せず、さらに「それはなぜ?」と2〜3回掘り下げるだけで、物事を見る目が変わっていくのを実感できます。
- 著者の馬田隆明さんは、どのような経歴の方なのですか?
-
著者の馬田隆明さんは、東京大学でスタートアップの支援や起業家教育に携わっている専門家です。
日本マイクロソフトなどを経て、現在は数多くの起業家を育てる立場にあります。
本書の内容は、そうしたスタートアップ支援の最前線で培われた、実践的で現場に即した知見に基づいているのが特徴です。
- この本は、他の思考法に関する本と何が違いますか?
-
多くの思考法の本が理論の解説に重点を置くのに対し、本書は「情報収集→思考→行動」というサイクルを回し、実践を通じて解像度を上げていく具体的な行動法にまで踏み込んでいる点が大きな違いです。
抽象的な考え方だけでなく、日々の仕事ですぐに試せる手順が示されています。
- 「課題解決」のために、まず何から始めるべきだと書かれていますか?
-
まず、目の前にある問題をそのまま「課題」と捉えるのではなく、その課題自体の解像度を上げることから始めるべきだと述べられています。
多くの人は急いで解決策を探そうとしますが、本書では「本当に解くべき問題は何なのか」を特定するプロセスが最も重要であると強調されています。
まとめ
この記事では、馬田隆明氏の著書『解像度を上げる』について、曖昧な思考を明確にするための4つの視点を軸に要約しました。
上司に企画を突き返されてしまう悩みを解決する、具体的な思考法が詰まった一冊です。
- 思考を整理する4つの視点(深さ・広さ・構造・時間)
- 解決策の前に「課題」そのものを深く捉える重要性
- 日々の業務ですぐに試せる具体的な行動法
もしあなたが「もっと考えて」という言葉にどう応えればよいか分からず悩んでいるなら、本書で紹介されている思考の道具を手に取ってみてください。