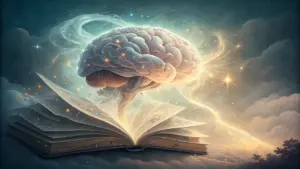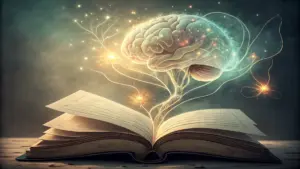チームの生産性を高める鍵は、メンバーが安心して本音を言える環境づくりにあります。
この記事では、多くのリーダーが参考にする書籍『心理的安全性のつくりかた』を要約し、チームの状態を測る4つの因子や、明日から実践できる具体的な行動を解説します。
どうすれば、メンバーが萎縮せずに意見を言えるチームになるんだろう…



本書が示す「4つの因子」とリーダーの具体的な振る舞いに、その答えがあります
- 心理的安全性とは何かという基本的な定義
- チームの状態を測る「話しやすさ」など4つの因子
- リーダーが実践すべき「きっかけ・行動・みかえり」の法則
- 書籍『心理的安全性のつくりかた』の概要と読むべき人
心理的安全性とは?Googleが突き止めた成功チームの共通点
「心理的安全性」という言葉を聞いて、どんな職場を想像しますか。
実は、チームの生産性を高めるうえで最も重要な要素だと、アメリカのIT企業であるGoogleの研究で明らかになりました。
単なる仲が良いだけの職場ではなく、メンバーが対人関係のリスクを恐れずに、安心して自分の意見や考えを発言できる状態を指します。
心理的安全性が低いチームでは、メンバーはどのような不安を感じ、行動が制限されてしまうのでしょうか。
メンバーの行動を縛る4つの不安
心理的安全性が低いチームでは、メンバーは常に対人関係のリスクに晒されています。
これは、良かれと思って取った行動が、自分にとって不利益な評価につながるかもしれないという根強い不安のことです。
書籍『心理的安全性のつくりかた』では、この不安を4つの種類に分類しています。
これらの不安が、メンバーから本来のパフォーマンスや積極性を奪ってしまうのです。
| 不安の種類 | メンバーが取ってしまう行動 |
|---|---|
| 無知だと思われたくない | 必要な質問や相談をしない |
| 無能だと思われたくない | 自分のミスを隠したり意見を言わない |
| 邪魔だと思われたくない | 助けを求めず一人で抱え込む |
| 否定的だと思われたくない | 反対意見を言わず議論を避ける |
うちのチーム、まさにこの状態かもしれません…



これらの不安を取り除くことが、心理的安全性づくりの第一歩です
これらの不安は個人の性格の問題ではなく、チームの環境が生み出しています。
メンバーが萎縮することなく本来の力を発揮できる環境づくりが求められます。
「ヌルい職場」と「学習する職場」の決定的な違い
「心理的安全性が高い職場」と聞くと、意見の対立がなく和気あいあいとした「ヌルい職場」をイメージするかもしれません。
しかし、この二つは仕事に求める基準の高さで明確に区別されます。
本書では、心理的安全性の高低と仕事の基準の高低を組み合わせた4つの職場タイプが紹介されています。
私たちが目指すべきなのは、心理的安全性が高く、同時に仕事の基準も高い「学習する職場」です。
| 仕事の基準が低い | 仕事の基準が高い | |
|---|---|---|
| 心理的安全性が高い | ヌルい職場 | 学習する職場(理想) |
| 心理的安全性が低い | さむい職場 | 不安な職場 |
ただ仲が良いだけではダメなんですね



はい、健全な意見の衝突があってこそ、チームは成長できます
心理的安全性を確保したうえで高い基準を求めることで、チームは失敗から学び、継続的に成果を上げられる「学習する職場」へと進化していくのです。
なぜ日本の組織で心理的安全性が重要なのか
これまで見てきた心理的安全性の考え方は、特に日本の組織文化において重要な意味を持ちます。
同調圧力が強く、周囲の空気を読むことが求められがちな環境では、メンバーが率直な意見を表明しにくい場面が少なくありません。
上司や先輩の意見に反対しづらい、一度の失敗が許されないといった雰囲気は、新しいアイデアの芽を摘み、組織の硬直化を招きます。
変化の激しい現代において、従業員一人ひとりが自律的に考え、行動できる環境づくりは企業の存続に不可欠です。
確かに、波風を立てないように発言を控えてしまうことはあります…



心理的安全性を高めることで、その「言えなかった意見」がチームの財産になります
心理的安全性を日本の組織に根付かせることは、メンバーの主体性を引き出します。
そして、変化に強いしなやかな組織をつくるための鍵となるのです。
チームの心理的安全性を高める4つの因子
本書では、日本の組織文化に合わせて、チームの心理的安全性を高めるための「四つの因子」が紹介されています。
これらは、あなたのチームの状態を客観的に把握するための、信頼できる「ものさし」となります。
| 因子 | 概要 |
|---|---|
| 話しやすさ | 地位や経験に関わらず、誰もが気兼ねなく発言できる |
| 助け合い | 困難な状況で、自然に助けを求め、協力し合える |
| 挑戦 | 失敗を恐れずに新しいアイデアを試し、そこから学べる |
| 新奇歓迎 | 異なる意見や新しいメンバーを個性として尊重し、受け入れる |
これら四つの因子は、それぞれが独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。
特に「話しやすさ」は、他の三つの因子全ての土台となる重要な要素です。
話しやすさ|誰もが気兼ねなく発言できる風土
「話しやすさ」とは、チームの誰であっても、懸念点や反対意見を気兼ねなく口にできる状態を指します。
これは、心理的安全性の土台となる最も基本的な因子です。
メンバーが「これを言ったら、無知だと思われないか」といった不安を感じることなく、素朴な疑問や意見を表明できる環境が求められます。
例えば、会議で若手の意見に対して、リーダーが率先して「面白い視点だね」と肯定的に受け止める姿勢を見せることで、発言の心理的なハードルは下がっていきます。
うちの会議、いつも同じ人しか発言しないな…



まずはリーダーが「何か懸念点はない?」と具体的に問いかけることから始めてみましょう
役職や経験に関わらず誰もが安心して声を上げられる環境は、問題の早期発見や、これまでにないアイデアが生まれるきっかけをつくります。
助け合い|失敗を個人でなくチームで乗り越える文化
「助け合い」とは、困難な状況に直面したとき、メンバーがためらわずに助けを求め、周囲も快く協力できる文化のことです。
トラブルが発生した際に個人を責めるのではなく、「チームの学びの機会」として捉え、全員で解決策や再発防止策を考える姿勢が、この文化を育みます。
ミスを報告したメンバーに対して、リーダーが「報告してくれてありがとう」と感謝を伝えるだけで、チーム内の信頼関係は深まるのです。
若手からの報告が遅くて、問題が大きくなってから発覚することがあるんだよな…



ミスを報告してくれたこと自体を「ありがとう」と評価するだけで、報告のハードルはぐっと下がりますよ
個人の失敗を減点法で評価するのではなく、チームで乗り越えるべき課題として向き合う文化が、結果的にチーム全体の課題解決能力を高めます。
挑戦|前例のない試みから学びを得る姿勢
「挑戦」とは、失敗を恐れずに新しいアイデアを試し、たとえうまくいかなくても、その結果からチーム全体で学んでいこうとする姿勢を指します。
変化の激しい現代では、過去の成功体験が通用しない場面も少なくありません。
たとえ成功確率が30%程度のアイデアでも、「まずは試してみよう」と背中を押せるかが、チームの成長の分かれ道となります。
失敗は罰せられるものではなく、貴重なデータであるという認識をチームで共有することが大切です。
どうせ前例がないから却下されるだろう、という空気がチームにある気がする…



小さな挑戦とそこからの学びをチームで共有し、称賛する習慣をつくるのがおすすめです
挑戦を歓迎する文化は、メンバーの自律性を促し、変化に対応できるしなやかな組織をつくるための原動力になるのです。
新奇歓迎|多様な個性を尊重し受け入れる環境
「新奇歓迎」とは、自分とは異なる意見やバックグラウンドを持つメンバーを、異物として排除するのではなく、チームの新たな視点として歓迎する環境のことです。
中途採用者や異動してきたメンバーが持つ、既存の常識にとらわれない視点は、組織の課題を浮き彫りにする貴重な機会となります。
新しいメンバーがもたらす「なぜ、こうなっているんですか?」という素朴な疑問を、業務改善のきっかけとして活かせるかが、チームの器の大きさを決めます。
新しいメンバーがなかなかチームに馴染めていないように見える…



その人の個性や得意なことを知るための雑談の場を設けるなど、意図的な関わりが大切です
多様な個性が尊重され、それぞれの強みが発揮されるチームは、画一的な思考に陥りません。
複雑な問題に対して、より創造的な解決策を見出すことができます。
リーダーからはじめる心理的安全性のつくりかた
チームの心理的安全性を高める上で、メンバー自身の意識も大切ですが、最も影響力が大きいのはリーダーの振る舞いです。
リーダーが意識的に行動を変えることで、チームの空気は大きく変わります。
ここでは、本書で紹介されているリーダーが実践すべき「心理的柔軟性」と、メンバーの行動を変えるための具体的な法則について解説します。
鍵となるリーダーの「心理的柔軟性」
本書で鍵として紹介されているのが、リーダーの「心理的柔軟性」です。
これは、予期せぬ出来事や困難な状況に直面した際に、感情に流されず、チームの目的に向かってしなやかに行動を切り替えられる能力を指します。
この心理的柔軟性は、大きく3つの要素から成り立っています。
リーダーがこれらの要素を意識することで、チームは安定し、安心して挑戦できる土台が築かれます。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 変わらないものを受け入れる | 組織のルールや予期せぬトラブルなど、自分では変えられない現実を冷静に受け止める |
| 大切なことへ向かう | チームが目指すべき目標やビジョンを明確にし、そこに向かって行動し続ける |
| 客観的に見分ける | 自分の感情や思い込みから距離を置き、「今、チームにとって何が必要か」を俯瞰的に判断する |
リーダー自身の心の持ちようが、そんなにチームに影響するんですね。



はい、リーダーの心の状態が安定していることが、メンバーの安心感につながるんです。
リーダーが感情に振り回されず、常にチームの「大切なこと」に立ち返る姿勢を見せることで、メンバーは安心してリーダーを信頼し、日々の業務に取り組めます。
行動を促す「きっかけ・行動・みかえり」の法則
メンバーの行動を変えたいとき、精神論で「もっと積極的に発言しよう」と呼びかけるだけでは効果は薄いです。
本書では、行動科学に基づき、具体的な「行動」そのものに焦点を当てるアプローチを推奨しています。
その中心となるのが、「きっかけ・行動・みかえり」の法則です。
人の行動は、「きっかけ」によって引き起こされ、その直後に良い「みかえり」があると強化され、習慣化していきます。
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| 1. 行動を決める | チームに増やしたい行動(例:相談する)を明確にする |
| 2. きっかけとみかえりを設計する | 行動を促す「きっかけ」(声かけ)と、行動後の「みかえり」(感謝や承認)を考える |
| 3. リーダーが実践する | リーダーが率先して「きっかけ」を作り、メンバーが行動したらすかさず「みかえり」を返す |
この法則を意識的に使うことで、リーダーはメンバーに強制することなく、望ましい行動を自然に増やしていくことが可能です。
会議で本音の意見を引き出すための具体的なアプローチ
「会議で当たり障りのない意見しか出ない」という悩みは、多くのリーダーが抱えています。
これは、メンバーが「否定されたくない」「無知だと思われたくない」と感じているサインです。
この状況を変えるには、リーダーが意図的に「どんな意見を言っても大丈夫」という「きっかけ」を作ることが重要です。
例えば、会議の冒頭で「今日は結論を出すのが目的ではありません。
色々な視点のアイデアを出すことを目的にしましょう」と宣言します。
そして、メンバーから意見が出たら、その内容に関わらず「面白い視点だね、ありがとう」と肯定的な「みかえり」を返します。
この小さな積み重ねが、「この場では安心して発言できる」という信頼関係を築きます。
なるほど、会議のルールそのものを変えてしまえばいいんですね。



その通りです。目的を変えるだけで、発言のハードルはぐっと下がりますよ。
リーダーが率先して心理的に安全な場をつくることで、メンバーは安心して多様な意見を出せるようになり、結果としてチームの創造性や問題解決能力は向上するのです。
ミスの報告が遅れる状況を改善する一言
若手メンバーからのミスの報告が遅れ、問題が大きくなってしまうこともよくある課題です。
この根本原因は、「失敗を報告すると怒られる」という不安にあります。
この状況を改善する鍵は、ミスが起きた後のリーダーの最初の反応です。
普段から「何かトラブルがあったら、すぐに教えてほしい。
絶対に個人を責めないから」という「きっかけ」を伝えておきます。
そして、メンバーが勇気を出してミスを報告した際には、「隠さずに報告してくれてありがとう。
これはチームの問題だから、一緒に解決策を考えよう」というポジティブな「みかえり」を返します。
| 反応の比較 | 結果 |
|---|---|
| 良い反応 | 「報告ありがとう。チームで解決しよう」 |
| 悪い反応 | 「なぜそんなミスをしたんだ!」 |
ミスを個人攻撃の対象とせず、チームの学習機会として捉えるリーダーの姿勢が、メンバーに安心感を与えます。
この一貫した態度が、報告しやすい正直な文化を育て、大きな問題の発生を未然に防ぐことにつながるのです。
書籍『心理的安全性のつくりかた』の基本情報
チームの生産性や一体感について、漠然とした課題を感じているリーダーは多いです。
本書は、そのような悩みを解決するために、行動科学に基づいた再現性の高いアプローチを教えてくれます。
チームづくりの教科書として、多くのマネージャーに支持されている一冊です。
このセクションでは、本書の著者プロフィールや全体像を解説し、どのような方に役立つ書籍なのかを明らかにします。
著者・石井遼介氏のプロフィール
本書の著者は、組織心理学や行動科学を専門とする石井遼介氏です。
株式会社ZENTechの代表取締役を務める、組織開発のプロフェッショナルです。
公認心理師や臨床心理士といった資格も持ち、科学的な知見に基づいて数多くの企業の組織改革に携わっています。
専門家としての深い知識と豊富な現場経験が、本書の内容に説得力をもたらしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 石井 遼介(いしい りょうすけ) |
| 肩書 | 株式会社ZENTech 代表取締役 / 組織心理学者 |
| 専門 | 心理的安全性、組織開発、行動科学 |
| その他 | 公認心理師、臨床心理士 |
専門家の知見が凝縮されているからこそ、本書は多くのリーダーにとって信頼できる指針となるのです。
本書の構成と主な内容
本書は、心理的安全性の理論的な解説から、チームで実践するための具体的なワークショップまで、体系的にまとめられています。
単なる知識のインプットで終わらず、読者が行動に移すことを強く意識した構成になっています。
理論編では心理的安全性の4つの因子やリーダーに求められる心理的柔軟性について、実践編では「きっかけ・行動・みかえり」のフレームワークを使った具体的なアプローチが紹介されています。
| 章 | 主なテーマ |
|---|---|
| 第1章 | 心理的安全性の重要性とGoogleの研究 |
| 第2章 | 心理的安全性を高める4つの因子 |
| 第3章 | リーダーに求められる心理的柔軟性 |
| 第4章 | 行動を変える「きっかけ・行動・みかえり」 |
| 第5章 | ケーススタディと具体的な実践例 |
| 付録 | チームで実践できるワークショップ |
理論だけじゃなくて、明日から使える具体的な方法が知りたいな



大丈夫です。本書は理論から具体的な実践方法まで網羅していますよ
このように、本書を読み進めることで、心理的安全性に関する理解を深めると同時に、自分のチームで何をすべきかが明確になります。
このような課題を持つリーダーやマネージャーにおすすめ
本書は、特にチームの雰囲気やコミュニケーションに課題を感じ、具体的な解決策を探しているリーダーやマネージャーに最適です。
精神論に頼らず、メンバーの行動を変えるための科学的なアプローチを学びたい方に役立ちます。
もし、あなたのチームが以下のような状況に当てはまるなら、本書から多くのヒントを得られます。
| おすすめな人 |
|---|
| 会議で意見が活発に出ないことに悩んでいる |
| メンバーがミスを恐れて報告が遅れがちだと感じている |
| チームの雰囲気が悪く、メンバー間の協力が少ない |
| リモートワークでチームの一体感が薄れていると感じる |
| 精神論ではなく、科学的根拠に基づいたマネジメントをしたい |
これらの課題に一つでも心当たりがある方は、本書を手に取ってみる価値があります。
あなたのマネジメントをアップデートし、チームをより良い方向へ導くきっかけとなるでしょう。
よくある質問(FAQ)
- リーダーだけでなく、チームメンバーにできることはありますか?
-
はい、あります。
同僚が意見を言ったときに「良い視点ですね」と肯定的に反応したり、困っている様子のメンバーに「何か手伝えることはありますか」と声をかけたりする行動が大切です。
一人ひとりの小さな行動が、チーム全体の話しやすさや助け合いの文化を育み、強い信頼関係を築きます。
- チームの心理的安全性を客観的に測定する方法はありますか?
-
本書では、チームの状態を測るための7つの質問が紹介されています。
例えば、「このチームでは、他のメンバーにミスを指摘してもらえるか」といった質問への回答を通じて、自分たちのチームの現状を客観的に把握するきっかけを得ることが可能です。
- 心理的安全性を高めると、生産性が上がる以外にどんなメリットがあるのですか?
-
生産性の向上はもちろんですが、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意)や幸福度が高まるというメリットもあります。
メンバーが安心して働ける職場は離職率の低下にもつながり、結果として組織全体の持続的な成長を支える土台となるのです。
- リーダーに求められる「心理的柔軟性」は、どうすれば身につきますか?
-
自分の感情や思考を客観的に観察する習慣をつけることが有効です。
例えば、問題が発生したときに感情的に反応するのではなく、一呼吸おいて「今、チームの目標達成のために最も大切なことは何か」と自問自答します。
こうした訓練を繰り返すことで、冷静な判断力を養えます。
- 「四つの因子」のうち、自分のチームは何から手をつければ良いでしょうか?
-
まずは、他の三つの因子の土台となる「話しやすさ」から始めることを推奨します。
会議で反対意見が出にくい、質問が少ないなどの課題がある場合、そこが改善の出発点です。
リーダーが率先して意見を求め、どんな発言も歓迎する姿勢を示すことが、チームを変えるきっかけになります。
- この本で解説されている心理的安全性のつくりかたは、リモートワークのチームにも応用できますか?
-
はい、応用できます。
リモートワーク環境では、本書で紹介されている「きっかけ」と「みかえり」の法則が特に重要です。
チャットでの質問に素早く丁寧に返信する、小さな成果を全体に共有して称賛するなど、意図的な行動でコミュニケーションを補うことが、物理的な距離を超えた信頼関係を築く鍵になります。
まとめ
この記事では、書籍『心理的安全性のつくりかた』を要約し、チームの生産性を高めるための具体的な方法を解説しました。
特に、リーダーがメンバーの望ましい行動を自然に引き出す「きっかけ・行動・みかえり」の法則は、すぐに実践できる強力な手法です。
- 心理的安全性がチームの生産性を高める土台
- チームの状態を測る「話しやすさ」など四つの因子
- リーダーに求められる心のあり方と具体的な振る舞い
- 小さな成功体験を積み重ねて信頼関係を築く方法
もしあなたのチームの雰囲気を変えたいと考えているなら、まずは会議で「今日はどんな意見でも歓迎します」と宣言するなど、チームの「話しやすさ」を高めるための小さなきっかけづくりから始めてみましょう。