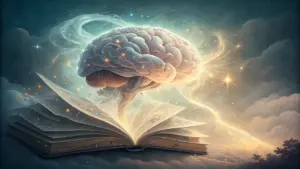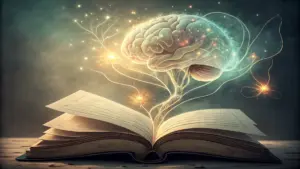SNS疲れや漠然とした不安の正体を解き明かす『スマホ時代の哲学』を要約します。
この本で最も重要なのは、情報から距離を置くだけでなく、失われた「孤独」の時間を積極的に取り戻すという考え方です。
なぜ私たちは常に誰かと繋がっていないと不安になるのか、その根本原因を哲学者の言葉をヒントに解き明かします。
本書は、情報に振り回されずに自分らしく生きるための具体的な方法を教えてくれる一冊です。
いつもスマホを見てしまう生活を変えるヒントが欲しい…



本書の要約を通じて、情報との上手な付き合い方がわかります
- 『スマホ時代の哲学』が解決する現代人の悩み
- SNS疲れから抜け出すための具体的な思考法
- 哲学を実生活に活かすためのヒント
- 増補改訂版で新たに追加された内容
SNS疲れに効く現代人のための哲学書
スマートフォンが手放せず、SNSでの人間関係や溢れる情報に疲れていませんか。
『スマホ時代の哲学』は、そんな現代人が抱える漠然とした不安や孤独感の正体を解き明かし、自分らしく生きるためのヒントを与えてくれる一冊です。
本書が示すのは、情報から距離を置くだけでなく、失われた「孤独」の時間を積極的に取り戻すことの重要性です。
この本を読めば、なぜ私たちが常に誰かと繋がっていないと不安になるのか、その根本的な原因がわかります。
哲学者の言葉を手がかりに、情報と上手に付き合い、心穏やかな毎日を取り戻すための具体的な方法が見つかるでしょう。
常時接続がもたらす不安の正体
「常時接続」とは、スマートフォンなどによって、いつでもどこでもインターネットや他者と繋がっている状態を指します。
一見すると便利ですが、この状態が私たちの心に絶え間ない不安を生み出す原因になっています。
私たちは無意識のうちに、SNSの通知や新しい情報といったわかりやすい刺激で、寂しさや不安を埋めようとしているのです。
例えば、1日に何度もSNSをチェックしないと落ち着かなかったり、友人からのメッセージに即座に返信しなければならないというプレッシャーを感じたりする経験はありませんか。
このような状態は、私たちの集中力を細切れにし、一つの物事を深く考える時間を奪ってしまいます。
いつもスマホを見ていないと、何か見逃している気がして落ち着きません…



その不安こそが、常時接続がもたらす罠なのです
常に情報に触れていることで得られる安心感は一時的なものであり、本質的な心の平穏には繋がりません。
まずは、自分が常時接続という状態にあり、それが不安の原因になっていると自覚することが、SNS疲れから抜け出すための第一歩になります。
結論を急がない力「ネガティヴ・ケイパビリティ」
本書で紹介される「ネガティヴ・ケイパビリティ」とは、答えがすぐに出ない不確実な状況や、よくわからない物事に対して、安易に結論を出さずに持ちこたえる能力のことです。
情報が溢れ、すぐに答えを求められる現代社会において、白黒はっきりさせずに物事とじっくり向き合う力は、とても重要になります。
私たちはSNSなどで意見が対立する場面を見ると、ついどちらが正しいのかすぐに判断したくなります。
しかし、ネガティヴ・ケイパビリティを意識することで、短期的な感情に流されず、多角的な視点から物事を捉える余裕が生まれます。
この力は、複雑な問題を粘り強く考え抜く思考力や、他者との深い対話を生み出す土台となるのです。
すぐに答えを出さないことは、思考の放棄ではありません。
むしろ、不確実性を受け入れ、自分の中の多様な考えを育むことで、より本質的な理解に到達できます。
この力を養うことが、情報に振り回されない自分を確立する鍵となるのです。
現代を生き抜くための哲学者の言葉
『スマホ時代の哲学』では、哲学は難解な学問ではなく、現代社会の悩みに寄り添ってくれる実践的な知恵として紹介されています。
ニーチェのような過去の哲学者の言葉から、村上春樹や『新世紀エヴァンゲリオン』といった身近なカルチャーまでを例に挙げながら、私たちの悩みを解きほぐしてくれるのが本書の魅力です。
本書で紹介される2500年以上の歴史を持つ哲学の知見は、SNSでの承認欲求や人間関係の悩み、尽きることのない不安といった問題に対して、新しい視点を提供してくれます。
哲学って難しそうだけど、本当に私の悩みに役立つのでしょうか?



大丈夫です。本書は、哲学者の言葉を現代の状況に置き換えて優しく解説してくれます
先人たちが考え抜いた言葉に触れることで、自分の悩みが決して特別なものではないと気づけます。
哲学者の言葉は、情報過多の時代で自分を見失わず、確かな足取りで生きていくための心強い羅針盤になるのです。
要約でわかるスマホ時代の哲学の3つのポイント
『スマホ時代の哲学』には、情報にあふれた現代を生き抜くための知恵が詰まっています。
本書で語られる数多くのヒントの中から、特にSNS疲れや日々の不安に悩む方が押さえておきたい要点を3つに絞って解説します。
ここで紹介するポイントは、自分自身と向き合い、主体的に生きるためのヒントになるはずです。
自分と向き合うための「孤独」という時間
本書は、スマートフォンによる「常時接続」が私たちの生活から「孤独」な時間を奪っていると指摘します。
一人で静かに自分と対話する時間が失われると、私たちは他人の評価を過度に気にしたり、絶え間ない情報に触れていないと不安になったりするのです。
本書の第3章「常時接続で失われた〈孤独〉」では、この孤独が決して寂しいものではなく、むしろ自己を確立するために不可欠な時間であると説かれています。
あえてスマートフォンから離れ、孤独な時間を持つことで、SNS疲れの原因となる他者との過剰なつながりから解放されるでしょう。
いつも誰かと繋がっていないと不安になるのはなぜ?



それは、一人で静かに考える時間を失っているサインです
意識的に孤独な時間を作り出すことは、情報過多の社会で自分を見失わないための第一歩となります。
本質的な思考力を養う「自分の頭で考えない」技術
本書が提案するユニークな考え方が「自分の頭で考えない」という技術です。
これは思考を放棄することではなく、自分の狭い視野に固執せず、過去の偉大な哲学者たちの知恵を借りて物事を多角的に捉える思考法を指します。
第2章「自分の頭で考えないための哲学」で解説されるこの技術は、情報に振り回されず物事の本質を見抜く「考える力」を養います。
哲学という2500年以上続く知見の蓄積は、現代社会が抱える問題に対する答えのヒントを与えてくれます。
先人たちが築き上げた思考のフレームワークを活用することで、私たちはより深く、豊かに世界を理解できるようになるのです。
情報が多すぎて、何が正しいのかわからなくなります…



まずは自分の考えに固執せず、哲学者の視点を借りてみましょう
この技術を身につけることで、フェイクニュースや偏った意見に惑わされることなく、自分自身の判断軸を確立できます。
自分を変えるシグナルとしての「退屈」との付き合い方
私たちは、少しでも時間があるとスマートフォンを手に取り、SNSや動画で「退屈」を埋めようとします。
本書は、その「退屈」こそが自分自身を変えるための重要なシグナルであると教えてくれます。
第5章や第6章で語られるように、ハイテンションな刺激や多忙さで退屈から目を背け続けると、自分が本当に何をしたいのかを見失ってしまいます。
何となく感じる虚しさや物足りなさは、今の生き方を見直すためのサインです。
その感覚から逃げずに向き合うことで、新しい目標や本当に情熱を注げるものが見つかるきっかけになります。
ついスマホを見て時間を潰してしまい、後で虚しくなります



その退屈こそ、新しい自分に出会うチャンスのサインです
退屈な時間を受け入れる勇気が、スマートフォンへの依存から抜け出し、より充実した人生を歩むための鍵となります。
増補改訂版でさらに深化した内容
2025年4月18日に発売された増補改訂版では、旧版から18,000字を超える加筆が行われました。
読者からの質問に答えるQ&Aや、各界の著名人による解説・推薦文が追加されています。
| 追加要素 | 内容 |
|---|---|
| Q&A | 読者からの質問に著者が答える実践的な内容 |
| 解説 | 発酵メディア研究者ドミニク・チェン氏による寄稿 |
| 推薦文 | 作家の三宅香帆氏と漫画家の魚豊氏からのコメント |
これらの追加コンテンツにより、本書で語られる哲学をより多角的に、そして深く自分自身の問題として捉えられるようになっています。
より理解を深める実践的なQ&Aの追加
増補改訂版には、限定付録として「『スマホ時代の哲学』を実践する人のためのQ&A」が収録されました。
本書を読んだ読者から寄せられた疑問に、著者の谷川嘉浩氏が丁寧に答える内容です。
哲学的な思索を、私たちの日常生活にどう落とし込んでいけばよいのか、その具体的なヒントが示されています。
理論だけでなく、実践を伴って初めて、本書の価値を本当の意味で理解できるのかもしれません。
本で学んだことを、どうやって毎日の生活に活かせばいいの?



このQ&Aが、あなたの悩みを解決する具体的なヒントになりますよ
本書のメッセージを受け取り、日々の行動を変えるための最初の一歩として、このQ&Aは大きな助けとなります。
発酵メディア研究者ドミニク・チェン氏による解説
巻末には、発酵メディア研究者というユニークな肩書を持つドミニク・チェン氏による解説「『スマホ時代の哲学』の発酵」が収録されています。
チェン氏は、本書で提示される哲学的な問いが、まるで発酵食品のように、読者の中で時間をかけてじっくりと熟成し、新たな意味や価値を生み出していく様子を見事に描き出しています。
情報がすぐに消費されてしまう現代において、本書がいかに長く付き合える一冊であるかを教えてくれます。
この解説を読むことで、一度読んだだけでは気づかなかった本書の奥深さや、社会における新たな役割を発見できるのです。
三宅香帆氏と漫画家・魚豊氏が語る本書の魅力
本書には、作家の三宅香帆氏と、『チ。
―地球の運動について―』で知られる漫画家の魚豊氏から、熱い推薦の言葉が寄せられています。
SNSによって失われたものを、
https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-3142-2
哲学者とともに取り戻す旅に出る。
そんな素敵な本ほかにないです!
――新書大賞2025受賞『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』著者
三宅香帆氏
即時(アジャイル)で常時(ユビキタス)なスマホ時代に、
https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-3142-2
超遅効で来る、孤独の消化不良(グルメ)
それでも、尚、「哲学」は美味い!!
高解像度モニターの中に満腹感を探すより
本書の導きとともに、知恵の樹の実の素晴らしき胃もたれにありつけ!
――『チ。―地球の運動について―』作者
魚豊氏
他の分野のクリエイターは、この本をどう読んだんだろう?



第一線で活躍するお二人の言葉が、本書の普遍的な魅力を伝えています
それぞれ異なるフィールドで言葉や物語を紡ぐクリエイターからの推薦は、本書が単なる哲学書にとどまらず、現代を生きるすべての人々の心に響く力を持っていることの証明です。
著者・谷川嘉浩と書籍の概要
本書『スマホ時代の哲学』を深く理解するために、まずは著者である谷川嘉浩氏の人物像と、書籍そのものの情報を知ることが重要です。
特に、著者がどのような背景を持つ哲学者なのかを知ると、本書のメッセージがより心に響くものになります。
ここでは、著者プロフィール、書籍の基本情報、そして購入を検討する上で欠かせない読者の感想や書評を詳しく紹介します。
著者・谷川嘉浩のプロフィール
著者の谷川嘉浩氏は、1990年生まれの気鋭の哲学者です。
現在は京都市立芸術大学で講師を務めながら、専門の哲学にとどまらず、メディア論や社会学、デザインの実技教育など、現代社会と密接に関わる幅広い分野で活動しています。
その柔軟な視点が、難解に思われがちな哲学を私たちの日常に引き寄せてくれます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年 |
| 居住地 | 京都市 |
| 現職 | 京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師 |
| 専門分野 | 哲学、メディア論、社会学、デザイン |
| 主な単著 | 『鶴見俊輔の言葉と倫理』『信仰と想像力の哲学』 |
どんな経歴の人が書いた本なんだろう?



専門分野だけでなく広い視野を持つ著者だからこそ、現代を生きる私たちの悩みに的確な言葉を届けてくれるのです。
谷川氏の多角的な活動が、本書『スマホ時代の哲学』に深みと説得力を与えていると言えます。
書籍の発売日や価格・目次一覧
本書はメディアでも話題となった旧版に、18,000字を超える大幅な増補と改訂を加えた新書版です。
2025年4月18日に発売され、価格は1,540円(税込)で手に入れることができます。
本書がどのようなテーマを扱っているのか、目次から全体の流れをつかんでみましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 書籍名 | 増補改訂版 スマホ時代の哲学 |
| 発売日 | 2025年4月18日 |
| 価格 | 1,540円 (税込) |
| ISBN | 978-4-7993-3142-2 |
| ページ数 | 312ページ |
| 章 | タイトル |
|---|---|
| はじめに | |
| 第1章 | 迷うためのフィールドガイド、あるいはゾンビ映画で死なない生き方 |
| 第2章 | 自分の頭で考えないための哲学――天才たちの問題解決を踏まえて考える力 |
| 第3章 | 常時接続で失われた〈孤独〉――スマホ時代の哲学 |
| 第4章 | 孤独と趣味のつくりかた――ネガティヴ・ケイパビリティがもたらす対話 |
| 第5章 | ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会 |
| 第6章 | 快楽的なダルさの裂け目から見える退屈は、自分を変えるシグナル |
| おわりに | |
| あとがき | |
| 増補改訂版 限定付録 | 「『スマホ時代の哲学』を実践する人のためのQ&A」 |
| あとがき | 増補改訂版によせて |
| 解説 | 『スマホ時代の哲学』の発酵(解説:ドミニク・チェン氏) |
目次を見るだけでも、現代人が抱える「孤独」や「退屈」といったテーマに深く切り込んでいることがわかります。
購入前に知りたい読者の感想や書評
本書は読書レビューサイト「読書メーター」で74%の高評価を獲得しており、多くの読者から深く支持されていることがうかがえます。
同サイトでの登録数は1,300件を超え、その注目度の高さを示しています。
ここでは、各界の著名人から寄せられた推薦の声を感想として紹介します。
SNSによって失われたものを、
https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-3142-2
哲学者とともに取り戻す旅に出る。
そんな素敵な本ほかにないです!
――新書大賞2025受賞『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』著者
三宅香帆氏
即時(アジャイル)で常時(ユビキタス)なスマホ時代に、
https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-3142-2
超遅効で来る、孤独の消化不良(グルメ)
それでも、尚、「哲学」は美味い!!
高解像度モニターの中に満腹感を探すより
本書の導きとともに、知恵の樹の実の素晴らしき胃もたれにありつけ!
――『チ。―地球の運動について―』作者
魚豊氏
実際に読んだ人はどんな感想を持っているのかな?



作家や漫画家といったクリエイターからも熱い支持が寄せられており、内容の確かさが伝わってきますね。
これらの書評は、本書が単なる哲学の入門書ではなく、現代を生きるすべての人々にとって重要な気づきを与えてくれる一冊であることを証明しています。
よくある質問(FAQ)
- 哲学に詳しくなくても『スマホ時代の哲学』の内容は理解できますか?
-
はい、哲学の知識が全くなくても問題ありません。
本書は、ニーチェのような哲学者の言葉を引用しつつも、専門用語を多用せず、私たちの身近な悩みやSNSでの出来事を例に挙げて解説してくれます。
まるで著者の谷川嘉浩さんと対話しているかのように読み進められるので、哲学書を初めて読む方にもおすすめの一冊です。
- 本書が提案する「孤独」と、流行りの「デジタルデトックス」はどう違うのですか?
-
デジタルデトックスは、スマートフォンから物理的に距離を置く「手段」に重点を置いています。
一方、『スマホ時代の哲学』で語られる「孤独」は、そうして生まれた時間で積極的に自分と向き合い、内面を豊かにするための「目的」を重視する考え方です。
単に情報から離れるだけでなく、その時間をどう過ごすかが重要だと本書は教えてくれます。
- この本を読むことで、私たちの生活にどんな良い変化が期待できますか?
-
本書を読むと、まずSNS疲れや情報過多による漠然とした不安の正体が明確になります。
そして、なぜ自分が他人の評価を気にしてしまうのかを理解できるでしょう。
読み終える頃には、情報に振り回されずに物事の本質を捉える「考える力」が養われ、日々のコミュニケーションや人間関係を、より落ち着いた心で築いていけるようになります。
- 旧版と増補改訂版では、どちらを読むのがおすすめでしょうか?
-
これから初めて読む方には、断然、増補改訂版をおすすめします。
旧版の内容はすべて含まれている上に、読者からの質問に答えるQ&Aが追加されており、本書の考え方をどう実生活に活かすかという具体的なヒントが得られます。
また、ドミニク・チェン氏による解説は、本書の価値を新たな視点から発見させてくれるでしょう。
- 著者の谷川嘉浩さんは、どのような考えを持つ哲学者なのでしょうか?
-
谷川嘉浩さんは、大学で研究するだけでなく、メディア論やデザインなど幅広い分野で活動し、現代社会が抱える問題に哲学の視点から積極的に関わっている哲学者です。
彼の特徴は、哲学を難解な学問としてではなく、私たちが日々の不安や悩みを乗り越えるための「実践的な知恵」として伝えようとする姿勢にあります。
- すぐに答えを求めがちな性格ですが、「ネガティヴ・ケイパビリティ」を身につけることはできますか?
-
はい、すぐに身につくものではありませんが、意識することで誰でも養うことができます。
本書は、白黒はっきりさせられない状況に耐える力を「ネガティヴ・ケイパビリティ」と呼び、その重要性を説いています。
まずは、SNSで意見が対立する話題を見たときに、すぐに結論を出さずに「なぜ意見が分かれるのだろう」と多角的に考えることから始めてみるのが良いでしょう。
まとめ
『スマホ時代の哲学』の要点を解説しました。
本書は、SNS疲れや漠然とした不安の正体を哲学の視点から解き明かし、自分と向き合うための「孤独」な時間を取り戻すことの重要性を教えてくれる一冊です。
- SNS疲れや不安の原因である「常時接続」の正体
- 自分自身を確立するための「孤独」な時間の重要性
- 情報に振り回されない思考法「ネガティヴ・ケイパビリティ」
- 哲学を日常に活かすための具体的なヒント
情報に振り回される毎日から抜け出し、自分のペースでじっくり考える時間を取り戻したい方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。