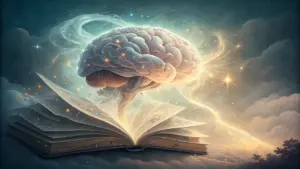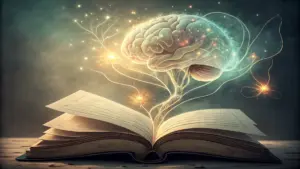仕事や勉強に集中できない、夜になっても寝つきが悪いといった不調の原因は、あなたが毎日使っているスマートフォンにあるのです。
世界的ベストセラー『スマホ脳』は、私たちの脳が現代のデジタル社会に適応しきれていないという衝撃の事実を、科学的な根拠に基づいて解き明かす一冊です。
この記事では、本書の要点を7つのポイントに凝縮し、具体的な対策までわかりやすく要約しました。
なぜスマホに依存してしまうのかという仕組みから、著者アンデシュ・ハンセンが推奨する最も効果的な処方箋まで詳しく知ることができます。
スマホとの付き合い方を見直したいけど、何から始めればいいの?



本書では、誰でも今日から実践できる簡単な改善策が紹介されています。
- スマホが集中力や睡眠の質を低下させる仕組み
- 脳がスマホに依存してしまう科学的な理由
- 今日からすぐに実践できる具体的なスマホ脳の対策
- 最高の処方箋として「運動」が推奨されるワケ
ベストセラー本『スマホ脳』とは
私たちの集中力を奪い、睡眠の質を下げ、時には心の健康まで脅かすスマートフォンの存在。
その影響の正体を脳科学の観点から解き明かし、世界的な話題を呼んだのが書籍『スマホ脳』です。
本書が伝える最も重要なメッセージは、私たちの脳は現代のデジタル社会のスピードに適応しきれていないという事実です。
この見出しでは、著者アンデシュ・ハンセン氏の警告、本書の核となる理論、そして世界中で社会現象となった背景を解説します。
著者アンデシュ・ハンセンが鳴らす警鐘
著者であるアンデシュ・ハンセン氏は、スウェーデンで絶大な人気を誇る精神科医です。
彼は本書で、スマートフォンへの接触が私たちの脳機能や精神状態に深刻な影響を及ぼしていると、最新の研究データをもとに警鐘を鳴らしています。
実際に、私たちは1日に平均4時間、多い人では2600回以上もスマートフォンに触れているというデータがあります。
ハンセン氏は、この「デジタルなドラッグ」とも言える状態が、人間の進化の歴史から見ると極めて不自然なものであり、様々な不調を引き起こす原因だと指摘するのです。
毎日何気なく使っているだけなのに、そんなに悪影響があるのかな?



ハンセン氏は、その漠然とした不安や不調こそが、スマートフォンが脳に与える影響のサインだと語っています。
彼の警告は、単にスマートフォンを否定するものではありません。
その仕組みを正しく理解し、意識的に付き合い方を変えることで、私たちは心身の健康を取り戻せると説いています。
人間の脳はデジタル社会に適応していないという事実
本書の根幹をなすのは、「人間の脳は、生存を最優先する原始時代からほとんど進化しておらず、デジタル情報が溢れる現代社会にはまだ適応できていない」という考え方です。
私たちの祖先にとって、新しい情報を得ることや仲間からの承認は、生き延びるために不可欠でした。
現代において、その役割を担っているのがスマートフォンの通知やSNSの「いいね!」です。
これらが脳の報酬系を刺激し、快楽物質であるドーパミンを放出させます。
この仕組みによって、私たちは特に重要な情報でなくても、ついスマートフォンを手に取ってしまう「スマホ脳 依存」の状態に陥るのです。
この脳の仕組みを理解することで、集中力が続かないのは自分の意志が弱いからではなく、脳の自然な反応によるものだとわかります。
世界中で社会現象を巻き起こした理由
『スマホ脳』がスウェーデンをはじめ世界中でベストセラーとなった最大の理由は、多くの人々が感じていた漠然とした不調や不安に、「スマホ脳」という分かりやすい名前と科学的根拠を与えた点にあります。
日本国内でもその反響は大きく、読書情報サイト「読書メーター」には発売から数年で17,000件以上の登録と3,800件を超える感想が寄せられています。
これは、国や文化を問わず、多くの現代人がスマートフォンとの付き合い方に悩み、解決策を求めている証拠と言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 著者 | アンデシュ・ハンセン |
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発売日 | 2020/11/18 |
| ページ数 | 256ページ |
本書は、個人の問題と思われがちだった集中力の低下や気分の落ち込みが、実は人類共通の課題であることを示しました。
その結果、多くの読者から共感を得て、社会全体でデジタル機器との向き合い方を考えるきっかけを与えたのです。
要約でわかる『スマホ脳』7つの重要ポイント
『スマホ脳』が解き明かす、スマートフォンが私たちの脳に与える影響は、私たちが日常で感じている不調の根本原因を鋭く指摘しています。
ここでは、本書の核心とも言える7つの重要ポイントを一つずつ見ていきましょう。
ポイント1-脳がスマホに依存するドーパミンの仕組み
脳がスマートフォンに惹きつけられるのは、快楽物質であるドーパミンが関わる「報酬系」という脳の仕組みが巧みに利用されているからです。
ドーパミンは本来、私たちが生き延びるための行動を促す重要な役割を担っています。
しかし、SNSの「いいね!」やゲームのクリア通知といったデジタルの刺激が、この報酬系を絶え間なくハッキングします。
ソースによると、私たちは平均して1日に2600回以上もスマートフォンに触れていると言われており、そのたびに脳はドーパミンという「ご褒美」を求め、結果として「スマホ脳 依存」の状態に陥ってしまうのです。
通知が来るたびに、ついスマホを見てしまうのは、このせいだったのか…



そうです、それは脳が快楽を求めてしまう自然な反応なのです
この脳の仕組みを理解することが、スマートフォンとの健全な関係を築くための第一歩になります。
ポイント2-存在だけで低下する集中力と記憶力
「仕事をしながらSNSをチェックする」といったマルチタスクは、一見すると効率的に思えるかもしれません。
しかし本書は、それは単に注意を素早く切り替えているだけで、脳に大きな負荷をかけ、生産性を著しく下げていると断言します。
さらに衝撃的なのは、スマートフォンがただ机の上にあるだけで、私たちの集中力や記憶力が低下するという研究結果です。
人間の脳は新しい情報や刺激に飛びつくように進化してきたため、スマートフォンの存在そのものが「何か面白いことが起きるかもしれない」という期待を脳に抱かせ、無意識のうちに認知能力を奪っていきます。
デスクに置いているだけでダメなんて、どうすればいいの?



集中したいときは、物理的にスマートフォンを別の部屋に置くのが最も効果的です
目の前のタスクに深く没頭するためには、意識的にスマートフォンを視界から外し、物理的な距離を確保する環境作りが欠かせません。
ポイント3-ブルーライトが招く睡眠の質の悪化
夜、ベッドに入ってからもついスマートフォンを眺めてしまう習慣は、睡眠の質を著しく低下させます。
その主な原因は、画面から発せられるブルーライトが、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまうからです。
脳はブルーライトを浴びると「まだ昼間だ」と錯覚し、覚醒状態を維持しようとします。
その結果、寝付きが悪くなる、眠りが浅くなる、朝すっきりと起きられないといった「スマホ脳 睡眠」の問題を引き起こすのです。
本書によれば、夜間にわずか2時間スマートフォンを使用するだけで、メラトニンの分泌量は20%以上も減少するとされています。
最近よく眠れないのは、寝る前のスマホが原因だったんだ…



寝室にスマートフォンを持ち込まないルールを作るだけで、睡眠の質は大きく改善しますよ
心身の回復に不可欠な質の高い睡眠を取り戻すためにも、寝る前のスマートフォン使用を控えることが極めて重要です。
ポイント4-SNSが生む孤独感とうつのリスク
SNSは本来、人との繋がりを深めるためのツールですが、使い方を誤ると、皮肉にも他者との比較から生まれる劣等感や孤独感を増幅させ、「スマホ脳 うつ」のリスクを高める危険性をはらんでいます。
私たちはSNS上で、他人の人生の最も輝いている瞬間(ハイライト)を断続的に見せられます。
それと自分の日常を無意識に比較することで、嫉妬心や焦燥感に駆られてしまうのです。
20代の若者が生涯でSNSに費やす時間は約5年分にも上るとのデータもあり、その精神的な影響は決して無視できません。
友達のキラキラした投稿を見ると、なんだか焦ってしまう…



SNSは他人の「ハイライト」だけを集めたものだと割り切ることが大切です
デジタル上の繋がりだけに依存せず、現実世界での直接的なコミュニケーションを大切にすることが、心の健康を保つ上で求められます。
ポイント5-子どもの学力や発達への深刻な影響
大人の脳でさえこれほどの影響を受けるのですから、発達途上にある子どもの脳への悪影響はさらに深刻です。
「スマホ脳 子ども 影響」は、本書が特に強く警鐘を鳴らすテーマの一つです。
リンクや通知など注意を散漫にさせる要素が多いデジタル教科書は、紙媒体に比べて学習内容の記憶定着率が低いという研究結果が報告されています。
また、スマートフォンやタブレットの長時間使用は、外遊びや運動の時間を奪います。
その結果、算数や理論的な思考を学ぶ上で土台となる運動能力の発達を阻害する可能性も指摘されています。
デジタル教科書って、一概に良いとは言えないのですね



便利なツールですが、使い方や使用時間には保護者の注意深い配慮が必要です
子どもたちの健やかな成長を守るため、家庭内でデジタル機器との付き合い方に関する明確なルールを設けることが不可欠です。
ポイント6-開発者スティーブ・ジョブズが我が子を遠ざけた背景
この問題の根深さを何よりも雄弁に物語るのが、iPhoneやiPadといった革新的な製品を生み出したアップルの創業者、故スティーブ・ジョブズが、自身の家庭では子どもたちのデジタル機器使用を厳しく制限していたという事実です。
彼はあるインタビューで、自分の子どもたちについて「iPadはそばに置くことすらしない」と語りました。
これは、製品を開発した当本人こそが、その抗いがたい魅力と脳に与える強力な依存性、特に子どもの発達への悪影響を誰よりも深く理解していたことの証左です。
作った本人が使わせなかったなんて、衝撃的すぎる…



それほど、私たちの脳を惹きつける強力な魅力と危険性を併せ持っているのです
最も便利な道具を世に送り出した人物のこの行動は、私たち利用者に対して、スマートフォンとの関係性を根本から見直すよう強く促しています。
ポイント7-最高の処方箋としての運動の効果
『スマホ脳』は、スマートフォンの危険性を指摘するだけでなく、明確で誰にでも実践可能な解決策を提示しています。
その最高の処方箋こそ、「運動」です。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を習慣にすると、脳の血流が増加し、記憶を司る海馬などで新しい神経細胞が生まれます。
運動はストレス耐性を高め、気分を安定させる効果があるだけでなく、集中力や記憶力、創造性といった脳機能そのものを直接的に向上させるのです。
週に数回、30分程度の軽い運動からでも、その効果は十分に得られます。
スマホをいじる時間を、少し運動に変えるだけでいいんだ



そうです、運動は「脳疲労 回復」に最も効果的な方法の一つなのです
スマートフォンから意識的に離れて体を動かすことは、デジタル社会で疲弊した脳をリフレッシュさせ、心と体の健やかなバランスを取り戻すための最も有効な手段と言えます。
今日から実践できるスマホ脳の治し方
『スマホ脳』では、スマートフォンとの付き合い方を見直すための実践的な方法が紹介されています。
最も重要なのは、意識的にスマートフォンから離れる時間を作ることです。
難しいことではなく、少しの工夫で「スマホ脳」の状態は改善できます。
本書で紹介されている5つの簡単な方法を見ていきましょう。
スクリーンタイムの把握
まずは現状把握から始めます。
スクリーンタイムとは、スマートフォンやタブレットなどの画面を見ていた時間のことです。
多くの人が自分の利用時間を過小評価しており、iPhoneやAndroidの標準機能で確認すると、1日の平均利用時間が4時間を超えているという事実に驚きます。
| 設定アプリの項目 | 確認できること |
|---|---|
| スクリーンタイム (iPhone) | アプリごとの利用時間 |
| デジタルウェルビーイング (Android) | 1日の通知回数 |
| 曜日ごとの利用状況 | スマホを持ち上げた回数 |
まずは自分のスマホ利用時間を知るのが大事なんだね。



はい、客観的な数字を見ることで、意識が大きく変わりますよ。
自分のスマートフォンの使い方を客観的に知ることが、対策を始めるためのスタートラインになります。
不要な通知のオフ設定
集中力を奪う最大の原因は、次から次へと届く通知です。
私たちの脳は通知が来るたびに、作業を中断してでもスマートフォンを確認したくなります。
1日にスマートフォンに触れる回数は、平均で2,600回を超えるというデータもあります。
| 通知をオフにしたいアプリの例 |
|---|
| SNS (X, Instagram, Facebookなど) |
| ニュースアプリ |
| ゲームアプリ |
| ショッピングアプリ |
たしかに、通知が来るとつい見ちゃうな…



仕事や勉強に集中したい時間だけでも、SNSやニュースアプリの通知を切るのがおすすめです。
緊急性の低いアプリの通知をオフにするだけで、無駄に集中力を削がれる回数を減らせます。
物理的な距離を確保する時間
本書では、スマートフォンが視界に入るだけで集中力が低下するという研究結果が紹介されています。
スマートフォンが近くにあるというだけで脳の資源が消費されてしまうため、仕事中や勉強中はカバンの中や別の部屋に置くことが有効です。
見えない場所に置くだけでいいんだ!



はい、物理的に距離を置くことで、無意識に注意が向かうのを防ぎます。
「スマホ断ち」の時間を作ることで、脳を休ませ、本来のパフォーマンスを取り戻すことができます。
寝室への持ち込み禁止の徹底
睡眠の質を低下させる大きな要因が、寝る前のスマートフォン利用です。
画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。
結果として寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
質の良い睡眠のためには、就寝1〜2時間前にはスマートフォンの使用をやめるのが理想です。
夜寝る前につい見ちゃうのがやめられない…。



寝室に充電器を置かず、リビングなどで充電するルールを作ると徹底しやすくなりますよ。
スマートフォンを目覚まし代わりにしている場合は、安価な目覚まし時計を別に用意することで、寝室への持ち込みを防げます。
軽い運動の習慣化
『スマホ脳』の著者が最高の処方箋として繰り返し強調しているのが、運動です。
ウォーキングやジョギングといった軽い運動は、ストレスを軽減し、集中力を高める効果があります。
スマートフォンを触る時間を少し運動に充てるだけで、脳機能が活性化するのです。
運動がスマホ脳に効くなんて意外!



運動は脳の血流を良くし、新しい神経細胞の生成を促すため、デジタル疲れの解消に最適です。
散歩をしながらポッドキャストを聴くなど、デジタル機器と上手に付き合いながら運動を取り入れるのも良い方法です。
『スマホ脳』の購読がおすすめな人の特徴
本書は、特定の誰かではなく、スマートフォンと共に現代を生きるすべての人に多くの気づきを与えてくれます。
もしあなたが、集中力の低下、睡眠不足、漠然とした不安感など、原因のわからない心身の不調を抱えているなら、その答えは本書の中にあるはずです。
特に、スマートフォンとの付き合い方を本気で見直したいと考えている人にとっては、必読の一冊といえます。
以下では、どのような悩みを抱える人に『スマホ脳』が特に役立つのか、4つの特徴に分けて解説します。
仕事や勉強の生産性を高めたい人
仕事や勉強中に、スマートフォンの通知が気になって集中力が途切れてしまう経験はありませんか。
本書では、スマートフォンがすぐ近くにあるだけで、私たちの集中力やワーキングメモリ(作業記憶)が著しく低下するという研究結果が示されています。
これは、脳のリソースの一部が「スマートフォンを無視する」というタスクに無意識に割かれてしまうためです。
私たちの多くは、1日に平均2,600回以上もスマートフォンに触れているというデータがあります。
これでは、一つの物事に深く集中する時間を確保するのが困難なのも当然です。
生産性の低下に悩んでいる方は、その原因が自分の能力ではなく、スマートフォンの使い方にあることに気づくでしょう。
仕事のメールをチェックするつもりが、ついSNSを開いて30分も経っていた…なんてことがよくあります。



その無意識の行動こそ、脳がスマートフォンにハイジャックされている証拠です。
本書で紹介されているデジタルデトックスの方法を実践すれば、脳を本来の集中できる状態に戻し、仕事や学習の効率を大きく向上させることが可能です。
質の高い睡眠を取り戻したい人
寝る直前までベッドの中でスマートフォンを眺めている習慣は、睡眠の質を著しく低下させる原因です。
スマートフォンやタブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。
これにより、脳が昼間だと錯覚してしまい、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。
さらに、SNSやニュースアプリで刺激的な情報に触れると、脳が興奮状態になりリラックスできません。
本書によれば、質の悪い睡眠は翌日の集中力低下や気分の落ち込みに直結し、長期的にはうつ病のリスクを高めることさえあります。
夜中に目が覚めてしまうことが増えたのは、寝る前のスマホが原因だったのかもしれませんね。



本書が提案する「寝室にスマートフォンを持ち込まない」というルールを試すだけで、睡眠の質は変わりますよ。
ぐっすり眠ってすっきりと目覚めたい、日中の眠気やだるさを解消したいと願う人にとって、本書が示す睡眠改善の知識は即効性のある処方箋となります。
SNSとの健全な付き合い方を模索する人
SNSは便利なコミュニケーションツールですが、同時に精神的な疲労の原因にもなっています。
他人の華やかな投稿を見て落ち込んだり、「いいね」の数を過剰に気にしたりすることで、私たちの脳は常に刺激とストレスに晒されています。
これは、SNSの通知が脳の報酬系を刺激し、ドーパミンを放出させることで、私たちを依存状態に陥らせるように設計されているからです。
ある調査では、20代が生涯でSNSに費やす時間は約5年分にもなると試算されています。
SNSから距離を置きたいのに、つい開いてしまうという自己嫌悪に悩む人は少なくありません。
本書は、そうしたSNS疲れのメカニズムを脳科学の視点から解き明かしてくれます。
友達の投稿を見ると羨ましくなって、なんだか自分が惨めに感じてしまいます。



その感情はあなただけのものではありません。本書を読めば、その仕組みが客観的に理解できます。
SNSがなぜ私たちを惹きつけ、そして疲れさせるのかを理解することで、感情的に振り回されることなく、自分にとって心地よい距離感でSNSを活用していくヒントが得られるでしょう。
子どものデジタル機器利用に悩む保護者
デジタルネイティブ世代の子どもたちにとって、スマートフォンやタブレットは当たり前の存在です。
しかし、その影響について不安を感じる保護者の方も多いのではないでしょうか。
本書は、子どもの脳が発達途上であるがゆえに、デジタル機器から特に大きな影響を受ける危険性を指摘しています。
長時間のスクリーンタイムが、学力やコミュニケーション能力の発達を妨げる可能性があるのです。
衝撃的なのは、アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズが、自分の子どもにはiPadの使用を厳しく制限していたという事実です。
これは、製品の開発者自身が、その強力な中毒性と発達へのリスクを深く理解していたことを物語っています。
子どもにどうやってスマホとの付き合い方を教えればいいのか、本当に悩みます。



その悩みに向き合うために、まずは大人が正しい知識を持つことが大切です。
本書は、子どものスマートフォン利用に明確なルールを設けたいと考える保護者にとって、科学的根拠に基づいた力強い指針となります。
子どもたちの未来を守るために、親として何をすべきかを考えるきっかけを与えてくれる一冊です。
よくある質問(FAQ)
- 「スマホ脳」になると、具体的にどのような症状が出ますか?
-
集中力が続かなくなる、寝付きが悪くなるといった症状のほかに、以前よりもイライラしやすくなったり、理由のない不安を感じたりするなど、精神状態の変化も現れます。
物事を深く考えるのが苦手になり、記憶力が落ちたと感じることもあります。
これらは脳が常に多くの情報にさらされ、脳疲労が回復できていないサインです。
- なぜ「スマホ脳」の対策として運動が良いのですか?
-
運動は、スマートフォンが引き起こす脳機能の低下に対する最も効果的な対策だからです。
ウォーキングのような軽い運動でも脳の血流が改善し、記憶などをつかさどる「海馬」という部分の働きが活発になります。
さらに、ストレスを解消する効果で心のバランスも整えるため、心身両面からの改善が期待できます。
- 本書で推奨されているデジタルデトックスで、すぐに試せる方法はありますか?
-
まずは意識的に「歩きスマホ」をやめることから始めるのが、簡単でおすすめの方法です。
スマートフォンから顔を上げて周りの景色に目を向けるだけで、脳を休ませる良いきっかけになります。
また、食事中や人と話している間はスマートフォンをカバンにしまう、という小さなルールも効果的なデジタルデトックスの方法です。
- スマホを見ると出る「ドーパミン」とは、悪い物質なのでしょうか?
-
ドーパミン自体は、意欲や学習能力を高めるために重要な役割を果たす、決して悪い物質ではありません。
しかし、スマートフォンの通知などで頻繁に放出されると、脳の報酬系がその刺激に慣れてしまいます。
その結果、より強い刺激がないと満足できなくなり、無意識にスマホを探す依存状態に陥るのです。
- デジタル教科書にはどのような問題点が指摘されていますか?
-
デジタル教科書はリンクや動画といった便利な機能を持つ一方で、学習者の注意を散漫にさせやすいという問題点があります。
そのため、紙の教科書と比べて学習内容が記憶として定着しにくいことが研究で示されています。
著者のアンデシュ・ハンセンは、発達段階にある子どもの脳にとって、集中力を保つのが難しい環境だと指摘しています。
- 『スマホ脳』の著者、アンデシュ・ハンセンとはどのような人物ですか?
-
アンデシュ・ハンセンは、スウェーデンの著名な精神科医です。
脳科学の専門家として、現代人の生活が脳や心に与える影響について研究しています。
この『スマホ脳』は新潮新書から出版された彼の代表作で、科学的な知見に基づき、スマートフォンが私たちの精神状態に与えるリスクに警鐘を鳴らしたことで世界的なベストセラーになりました。
まとめ
『スマホ脳』は、集中力の低下や睡眠不足といった現代人が抱える不調の原因が、私たちの脳がデジタル社会に適応しきれていないことにあると解き明かす一冊です。
本書では、スマートフォンが脳に与える影響の仕組みを科学的に解説し、誰でも今日から実践できる具体的な改善策を学ぶことができます。
- スマホ依存は意志の弱さではなく脳の仕組みが原因
- 集中力低下や睡眠の質の悪化など様々な不調を引き起こす
- 最高の処方箋は脳の働きを直接高める「運動」
まずはご自身のスマートフォンの利用時間を把握することから、デジタル機器との新しい付き合い方を始めてみましょう。